- Information
- DH拠点セミナー [19]
- GCOEセミナー [7]
- download [1]
- スクラップ [10]
- データ集 [9]
- 事務局連絡 [9]
- 刊行物 [19]
- News Letter [2]
- 募集情報 [75]
- 国際シンポジウム [12]
- DH-JAC2009 [49]
- タイムテーブル [2]
- 概要 [1]
- 発表要旨 [20]
- 講師プロフィール [21]
- DH-JAC2011 [1]
- 文化情報学専修 [5]
- 研究プロジェクト [9]
- 研究メンバー [11]
- 研究会・イベント [141]
2013年12月11日
立命館大学大学院 文学研究科 行動文化情報学専攻 「文化情報学専修」設置準備企画連続講演会 第7回
立命館大学大学院 文学研究科 行動文化情報学専攻 「文化情報学専修」設置準備企画連続講演会 第7回を開催します。
| 欧米における日本書籍コレクションの軌跡 | |
| 講師: | 周 欣平 氏 (カリフォルニア大学バークレー校C.V. スター東アジア図書館館長) マルラ俊江 氏 (カリフォルニア大学バークレー校C.V. スター東アジア図書館日本コレクション司書長) 小山 騰 氏 (ケンブリッジ大学図書館日本語コレクション部長) |
 | ( |
| 日時: | 2013年12月11日(水) 18:00-19:30 |
| 場所: | 立命館大学アート・リサーチセンター2階 多目的ルーム |
| 参加: | 予約不要・参加費無料 |
| プログラム: | |
| 第一部 | 「収集145年:北米における東アジア図書館とそのコレクション」 周 欣平 氏 |
| 「附:カリフォルニア大学バークレー校所蔵日本語コレクションから一部資料紹介」 マルラ俊江 氏 | |
| 第二部 | 「英国における日本語コレクション収集の歴史」 小山 騰 氏 |
| 第三部 | 「対談 日本古典籍デジタル化と日本研究の行方」 司会: 赤間 亮教授(立命館大学大学院文学研究科) |
※ 一般の方もインターネットでセミナーにご参加いただけます。(Ustream: http://www.ustream.tv/channel/dh-jac-ustream-tv)
【概要】
カリフォルニア大学バークレー校の事例:
19 世紀後半、日本および中国から木版本が、渡米する学者および学生の所有物として、また日中の諸機関からの贈り物として、アメリカ合衆国イエール大学、米国議会図書館、ハーバード大学、およびカリフォルニア大学に所蔵されるようになった。中には数百年も前に印刷された著作も含んでいたが、これらの書籍は北米の東アジア・コレクションを広める最初の種となった。この講演では、それらのコレクションとそれに関わった人物について、個々の歴史ならびに総体的なプロフィールを紹介する。
上記、東アジア・コレクションの北米における歴史的発展に関する講演に関連させて、その一例としてカリフォルニア大学バークレー校の日本語コレクションから一部資料を紹介する。
ケンブリッジ大学の事例:
英国における本格的な日本研究は、大学などを中心にして第二次世界大戦後に始まった。SOAS(ロンドン大学アジア・アフリカ学院)とケンブリッジ大学はScarborough Report で近代日本語コレクションの収集を開始し、1950 年代には英国図書館(旧大英博物館図書館)とオックスフォード大学も近代日本語コレクションの構築を開始した。1960 代には、Hayter Report によりシェフィールド大学も社会科学分野を中心とした日本語コレクションの収集を始めた。それらがいわゆる英国における四大コレクション (SOAS、ケンブリッジ、英国図書館そしてオックスフォード)であり、またシェフィールドを加えると五大コレクションになる。英国の四大日本語コレクションの一つであるケンブリッジ大学図書館の日本語コレクションを中心に、英国における日本語コレクション収集の歴史をたどってみたい。
【プロフィール】
周 欣平 Peter X. Zhou
カリフォルニア大学バークレー校C.V. スター東アジア図書館館長。武漢大学(中国) より英語学修士号、イリノイ大学アーバナ- シャンペーンより言語学博士号およ び図書館情報学修士号を修得。現職着任前は、ピッツバーグ大学、アイオワ大学、 および武漢大学で勤務。現在アジア学会東亜図書館協会会長を勤める。また、西 洋における図書館史および東アジア研究の発展について幅広く執筆および講演活 動を展開。氏の編纂になる「Collecting Asia: East Asian Libraries in North America, 1868-2008」は、過去2 世紀に渡る北米の主要学術図書館の東アジア言 語文献収集の歴史をたどった最初の単行書である。学術書6著作および論文多数 の著者または編者。
マルラ俊江 Toshie Marra:
カリフォルニア大学バークレー校日本コレクション司書。大阪外国語大学イタリ ア語学科卒業後、UCLA 東アジア図書館に勤務。1997 年には、UCLA 教育・情報 学部図書館情報学科修士課程を修了し、2000 年より2012 年までUCLA 東アジア 図書館で日本研究司書として勤務。2012 年以降、カリフォルニア大学バークレー 校日本コレクションの司書。
小山 騰 Noboru Koyama:
1985年より現在まで、ケンブリッジ大学図書館(Cambridge University Library) で、 日本語コレクションを担当(日本部長)。成城大学および慶応大学大学院(修士)で 日本史を専攻。数年にわたり国立国会図書館に勤務。その後渡英し、英国の公認 図書館員の資格を入手。現在、MCLIP (Member of the Chartered Institute of Library and Information Professionals) である。
| 主催: | 立命館大学大学院 文学研究科、立命館大学 日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点、立命館大学 アート・リサーチセンター |
| 問合せ: | 立命館大学文学部事務室 〒603‐8577 京都市北区等持院北町56‐1 TEL: 075‐465‐8187(月~金 9:00~17:30) |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 立命館大学大学院 文学研究科 行動文化情報学専攻 「文化情報学専修」設置準備企画連続講演会 第7回
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/6164
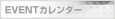
- 言語選択
- 最近のエントリー
- 紀要「アート・リサーチ」第15号の原稿を募集します(〆切:2014/9/23)
- デジタル技術が 生み出す 新たな文化効果ー洛中洛外図屏風 舟木本 編
- 祇園祭 デジタル・ミュージアム展2014
- 分業から協業へ -大学が、若冲と京の伝統工芸を未来に繋げる-
- 第12回 DH拠点セミナー
- アーカイブ
- 2014年9月 [1]
- 2014年7月 [4]
- 2014年6月 [4]
- 2014年5月 [3]
- 2014年4月 [3]
- 2014年3月 [3]
- 2014年2月 [2]
- 2014年1月 [3]
- 2013年12月 [5]
- 2013年11月 [8]
- 2013年10月 [1]
- 2013年9月 [2]
- 2013年8月 [3]
- 2013年7月 [2]
- 2013年6月 [4]
- 2013年5月 [1]
- 2013年4月 [4]
- 2013年3月 [6]
- 2013年2月 [3]
- 2013年1月 [1]
- 2012年12月 [2]
- 2012年11月 [3]
- 2012年10月 [6]
- 2012年9月 [3]
- 2012年8月 [2]
- 2012年7月 [3]
- 2012年6月 [2]
- 2012年5月 [1]
- 2012年4月 [1]
- 2012年3月 [14]
- 2012年2月 [3]
- 2012年1月 [5]
- 2011年12月 [1]
- 2011年11月 [3]
- 2011年10月 [1]
- 2011年9月 [4]
- 2011年8月 [1]
- 2011年7月 [3]
- 2011年6月 [5]
- 2011年5月 [5]
- 2011年4月 [4]
- 2011年3月 [9]
- 2011年2月 [3]
- 2011年1月 [5]
- 2010年12月 [7]
- 2010年11月 [9]
- 2010年10月 [6]
- 2010年9月 [4]
- 2010年7月 [8]
- 2010年6月 [10]
- 2010年4月 [12]
- 2010年3月 [13]
- 2010年2月 [2]
- 2010年1月 [5]
- 2009年12月 [2]
- 2009年11月 [1]
- 2009年10月 [5]
- 2009年9月 [3]
- 2009年8月 [5]
- 2009年7月 [2]
- 2009年6月 [6]
- 2009年5月 [5]
- 2009年4月 [6]
- 2009年3月 [8]
- 2009年2月 [5]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [3]
- 2008年11月 [5]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [45]
- 2008年8月 [4]
- 2008年4月 [2]
- 2007年10月 [1]
- 2007年4月 [1]