- Information
- DH拠点セミナー [19]
- GCOEセミナー [7]
- download [1]
- スクラップ [10]
- データ集 [9]
- 事務局連絡 [9]
- 刊行物 [19]
- News Letter [2]
- 募集情報 [75]
- 国際シンポジウム [12]
- DH-JAC2009 [49]
- タイムテーブル [2]
- 概要 [1]
- 発表要旨 [20]
- 講師プロフィール [21]
- DH-JAC2011 [1]
- 文化情報学専修 [5]
- 研究プロジェクト [9]
- 研究メンバー [11]
- 研究会・イベント [141]
2012年3月26日
「立命館大学・ハーバード大学デジタル・ヒューマニティーズ合同シンポジウム」報告書
日時:2012年3月3日(土)、午前9時30~午後5時45分
場所:ハーバード大学、CGIS South Building
参加者:65名
報告者:鈴木桂子(日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点 リサーチ・マネージャー)
アメリカ、ハーバード大学において、「立命館大学・ハーバード大学デジタル・ヒューマニティーズ合同シンポジウム」が3月3日に開催された。本シンポジウムは、ハーバード大学ライシャワー日本研究所と本拠点、ボストン美術館、日本学術振興会ITPプログラムによる共同開催である。本シンポジウムでは、本拠点から6名、ハーバード大学からの4名のほか、マサチューセッツ工科大学、コロンビア大学、ボストン美術館、北米日本研究資料調整協議会(NCC)から各1名の発表があり、参加者と共に活発な議論が展開された。
シンポジウムは、ライシャワー日本研究所所長Andrew Gordon教授の歓迎の挨拶から始まり、午前中は、本拠点の研究班のプロジェクトと研究活動の紹介を、各研究班リーダーとリサーチ・マネージャーが行った。
午後は、テーマ別に3つのパネル・セッションが行われた。1つ目のセッションは、Digital Archives for Japanese Studiesで、発表者がそれぞれに手掛けている日本研究関連のデジタル・アーカイブプロジェクトについて紹介した。まずBeth Katzoff氏が、コロンビア大学東アジア図書館所蔵のThe Makino Collection on the History of East Asian Filmの現状とそのアーカイブ化の今後の課題について論じられ、映画関係資料の著作権問題について特に言及された。なお、このコレクションは、現在本拠点の客員研究員である大矢敦子氏が在学中にITP派遣を通じて、コレクションのアーカイブ化に関わったものである。続いて、本拠点のITPパートナー機関であるボストン美術館の学芸員Sarah Thompson氏が、同館所蔵の在外最大規模の浮世絵コレクションの6年間にわたるアーカイブ化プロジェクトの概要と今後の展望について論じられた。Andrew Gordon教授からは、「2011年東日本大震災デジタルアーカイブ」のプロジェクトについて、震災から短期間のうちに大規模なプロジェクトを立ち上げ、震災以降人々が発信した膨大な情報のアーカイブ化が可能になった経緯が説明され、時と共に変化するボーン・デジタルな情報をいかに歴史的資料として留めていくべきであるかという事が論じられた。本拠点の赤間教授からは、本拠点が関わる様々なアーカイブの相乗効果により生み出される、新たな日本研究のあり方の可能性について提案がなされた。
ボーン・デジタルを含め、様々なメディアのアーカイブ化に取り組んでいる発表者達が共通して課題として挙げたのは、アーカイブにおける著作権問題であった。
午後2つ目のパネル・セッションCollaboration in Historical GISでは、本拠点の中谷友樹准教授から、プロジェクトとして進めている京都の歴史地理空間情報のマッピングについて紹介がなされ、続いて矢野桂司教授が、Virtual Kyotoの今後の課題について論じられた。ハーバード大学地理分析センター長Peter Bol教授は歴史地理情報の下部構造としての古地図の集積と、それを利用した学問上の発見の可能性について論じられた。
発表の後のディスカッションの時間には、Virtual Kyotoの様々な利用の可能性や、町家調査の具体的な手法について、会場より様々な質問があった。
最後のセッションは、Future Use of Multimedia Environments for Japanese Studiesというテーマで論じられた。最初の発表者であるマサチューセッツ工科大学の宮川繁教授からは、講義内容をインターネットで無償公開する Open Course Ware(OCW)、さらに国内外のデータベースからOCWへの視覚資料の積極的な利用など、大学の授業の未来像を論じられた。北米日本研究資料調整協議会会長のVictoria Lyon Bestor氏からは、北米の大学図書館のネットワークである調整協議会が作成した、日本研究をサポートするプログラムやオンライン・サービスの網羅的なサイトの紹介がなされた。ハーバード大学燕京図書館司書のKuniko Yamada McVey氏は、Digital Humanities Manifesto 2.0に絡めた日本研究のあり方について論じられた。最後に、本拠点の八村広三郎教授から、Digital Museum ProjectのVirtual Yamahoko Parade of Gion Festival部分の紹介があり、山鉾巡行の五感による体験の再現への取り組み、多様なDH研究のあり方をデモとともに発表された。このセッションでは、各発表者が従来のプリントというメディアにとらわれない知識のあり方や、その学習方法の開発に取り組んでいることから、その点について会場から様々な質問が寄せられた。
最後に、Andrew Gordon教授より、本拠点のDHを手法とした日本文化研究へ寄せる大きな期待の言葉と、拠点間の今後の交流を約して、シンポジウムは盛況の内に終了した。
●Introduction to the Digital Humanities Center for Japanese Arts and Culture (DH-JAC), Ritsumeikan University
Moderator: Andrew Gordon
Kozaburo Hachimura: Collaboration between IT and the Humanities: The Art Research Center, Ritsumeikan University
Ryo Akama: Constructing e-Research Platforms for Japanese Cultural Heritage
Keiji Yano: Virtual Kyoto: Preserving and sharing historical geo-spatial information of
Kyoto
Mitsuyuki Inaba: Research and Development on Web-based Platforms for Scholarly Communication and Learning
Kozaburo Hachimura: Digital Archives Technology Group
Keiko Suzuki: Toward the Further International Development of the Study of Japanese Arts and Cultures
●Digital archive for Japanese Studies
Moderator: Theodore Bestor, Reischauer Institute Professor of Social Anthropology and Japanese Studies and Chair, Dept. of Anthropology, Harvard University
Beth Katzoff: The Makino Collection at Columbia
Sarah Thompson: Japanese Prints Access and Documentation Project (JPADP) January 2005-June 2010
Andrew Gordon: 2011年東日本大震災デジタルアーカイブ
Ryo Akama: Digital Revolution in the Study of Japanese Art and Culture: The Digital Age Provides Epoch-making New Opportunities on Object Research
●Collaboration in Historical GIS
Moderator: Shigeru Miyagawa
Tomoki Nakaya: Mapping Historical Geospatial Information of Kyoto
Keiji Yano: The Next Challenge of Virtual Kyoto: Collaboration in Historical GIS
Peter Bol: Historical Geographic Information Systems
●Future Use of Multimedia Environments for Japanese Studies
Moderator: Peter Bol
Shigeru Miyagawa: Visualizing Cultures: Image-Driven Scholarship and Learning
Victoria Lyon Bestor: Multimedia for the Masses: Thinking about Gateway Services
Kuniko Yamada McVey: A genre in a Hurry: DH and the Japanese Studies: The Digital Humanities Manifesto 2.0
Kozaburo Hachimura: Virtual Yamahoko Parade of Gion Festival
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 「立命館大学・ハーバード大学デジタル・ヒューマニティーズ合同シンポジウム」報告書
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/4828
コメントする
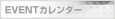
- 言語選択
- 最近のエントリー
- 紀要「アート・リサーチ」第15号の原稿を募集します(〆切:2014/9/23)
- デジタル技術が 生み出す 新たな文化効果ー洛中洛外図屏風 舟木本 編
- 祇園祭 デジタル・ミュージアム展2014
- 分業から協業へ -大学が、若冲と京の伝統工芸を未来に繋げる-
- 第12回 DH拠点セミナー
- アーカイブ
- 2014年9月 [1]
- 2014年7月 [4]
- 2014年6月 [4]
- 2014年5月 [3]
- 2014年4月 [3]
- 2014年3月 [3]
- 2014年2月 [2]
- 2014年1月 [3]
- 2013年12月 [5]
- 2013年11月 [8]
- 2013年10月 [1]
- 2013年9月 [2]
- 2013年8月 [3]
- 2013年7月 [2]
- 2013年6月 [4]
- 2013年5月 [1]
- 2013年4月 [4]
- 2013年3月 [6]
- 2013年2月 [3]
- 2013年1月 [1]
- 2012年12月 [2]
- 2012年11月 [3]
- 2012年10月 [6]
- 2012年9月 [3]
- 2012年8月 [2]
- 2012年7月 [3]
- 2012年6月 [2]
- 2012年5月 [1]
- 2012年4月 [1]
- 2012年3月 [14]
- 2012年2月 [3]
- 2012年1月 [5]
- 2011年12月 [1]
- 2011年11月 [3]
- 2011年10月 [1]
- 2011年9月 [4]
- 2011年8月 [1]
- 2011年7月 [3]
- 2011年6月 [5]
- 2011年5月 [5]
- 2011年4月 [4]
- 2011年3月 [9]
- 2011年2月 [3]
- 2011年1月 [5]
- 2010年12月 [7]
- 2010年11月 [9]
- 2010年10月 [6]
- 2010年9月 [4]
- 2010年7月 [8]
- 2010年6月 [10]
- 2010年4月 [12]
- 2010年3月 [13]
- 2010年2月 [2]
- 2010年1月 [5]
- 2009年12月 [2]
- 2009年11月 [1]
- 2009年10月 [5]
- 2009年9月 [3]
- 2009年8月 [5]
- 2009年7月 [2]
- 2009年6月 [6]
- 2009年5月 [5]
- 2009年4月 [6]
- 2009年3月 [8]
- 2009年2月 [5]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [3]
- 2008年11月 [5]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [45]
- 2008年8月 [4]
- 2008年4月 [2]
- 2007年10月 [1]
- 2007年4月 [1]