- Information
- DH拠点セミナー [19]
- GCOEセミナー [7]
- download [1]
- スクラップ [10]
- データ集 [9]
- 事務局連絡 [9]
- 刊行物 [19]
- News Letter [2]
- 募集情報 [75]
- 国際シンポジウム [12]
- DH-JAC2009 [49]
- タイムテーブル [2]
- 概要 [1]
- 発表要旨 [20]
- 講師プロフィール [21]
- DH-JAC2011 [1]
- 文化情報学専修 [5]
- 研究プロジェクト [9]
- 研究メンバー [11]
- 研究会・イベント [141]
2011年12月17日
国際シンポジウム 「文化財の現在・過去・未来 ―モノの記憶を残す方法」
下記のとおり「文化財の現在・過去・未来 ―モノの記憶を残す方法」を開催します。ぜひご参加ください。
国際シンポジウム
「文化財の現在・過去・未来 ―モノの記憶を残す方法」
シンポジウムは無事に終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。
 | ( |
日程: 2011年12月17日(土)・18日(日) 会場: 立命館大学<朱雀キャンパス> 大講義室 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)、
立命館大学アート・リサーチセンター
【参加無料・要予約】
詳細はこちらから>>文化財の現在・過去・未来 ―モノの記憶を残す方法
本シンポジウムは、2010年4月に開催した国際シンポジウム「文化財の現在・過去・未来 ―デジタルとアナログ共存の意義―」を引き継いだ続編として開催するものである。前回のシンポジウムは、文化財保護・継承に携わる人に注目したが、今回は文化財にまつわるモノに注目したい。前回指摘された問題の一つに、継承する技術はあるのに、それを支える材料がなくなりつつあるがために、遺していくことが困難になっている事例が挙げられた。今回のシンポジウムでは、文化財を支えるモノが抱える現状を明らかにし、そのモノを未来に残していくための方法を考えていく。
モノを残していくためには、モノそのものを残す方法の他に、モノの「記憶」を残す方法があると考えられる。本拠点が推進している日本文化にかかわる文化財のデジタルアーカイブ化とデータベース構築は、モノの記憶を残す手段の一つである。本シンポジウムでは、文化財保護・継承に携わる多分野の方々に、美術館・博物館、大学、行政、現場、それぞれの立場の見地から議論をし、モノの記憶を未来に永く伝えていくための可能性を検討する試みである
| 講師: | |
| 基調講演: | 千 玄室 / Genshitsu Sen(裏千家前家元) |
| 講演: | ジョン・マック / John Mack(イースト・アングリア大学日本学研究センター所長) |
| 発表: | 青柳正規 / Masanori Aoyagi(国立西洋美術館理事長) |
| 彬子女王/Princess Akiko of Mikasa(立命館大学衣笠総合研究機構PD) | |
| 河合真如 / Shinnyo Kawai(神宮司庁広報室長) | |
| サイモン・ケイナー / Simon Kaner(セインズベリー日本藝術研究所) | |
| 田辺小竹 / Shouchiku Tanabe(竹芸家) | |
| 原田昌幸 / Masayuki Harada(文化庁美術工芸課文部技官) | |
| ジョン・マック / John Mack(イースト・アングリア大学教授) | |
| 室瀬和美 / Kazumi Murose(漆芸作家) | |
| 矢野桂司 / Keiji Yano(立命館大学文学部教授) | |
| 司会: | 川嶋將生 / Masao Kawashima(立命館大学名誉教授) |
| 松本郁代 / Ikuyo Matsumoto(横浜市立大学学術院准教授) | |
| (50音順) | |
[ご予約方法]
ご予約はメールにてお申し込み下さい。お申し込みの際は必ず
●参加を予定されている方全員のお名前
●ご所属・ご職業
●ご連絡先(メールアドレス、電話番号)
●参加希望日
をお知らせ下さい。
e-mail: arc-jimu■arc.ritsumei.ac.jp(■を@に変えて下さい)
問い合わせ先:
立命館大学アート・リサーチセンター事務局
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
Tel:075-466-3411 Fax:075-466-3415
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 国際シンポジウム 「文化財の現在・過去・未来 ―モノの記憶を残す方法」
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/4202
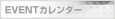
- 言語選択
- 最近のエントリー
- 紀要「アート・リサーチ」第15号の原稿を募集します(〆切:2014/9/23)
- デジタル技術が 生み出す 新たな文化効果ー洛中洛外図屏風 舟木本 編
- 祇園祭 デジタル・ミュージアム展2014
- 分業から協業へ -大学が、若冲と京の伝統工芸を未来に繋げる-
- 第12回 DH拠点セミナー
- アーカイブ
- 2014年9月 [1]
- 2014年7月 [4]
- 2014年6月 [4]
- 2014年5月 [3]
- 2014年4月 [3]
- 2014年3月 [3]
- 2014年2月 [2]
- 2014年1月 [3]
- 2013年12月 [5]
- 2013年11月 [8]
- 2013年10月 [1]
- 2013年9月 [2]
- 2013年8月 [3]
- 2013年7月 [2]
- 2013年6月 [4]
- 2013年5月 [1]
- 2013年4月 [4]
- 2013年3月 [6]
- 2013年2月 [3]
- 2013年1月 [1]
- 2012年12月 [2]
- 2012年11月 [3]
- 2012年10月 [6]
- 2012年9月 [3]
- 2012年8月 [2]
- 2012年7月 [3]
- 2012年6月 [2]
- 2012年5月 [1]
- 2012年4月 [1]
- 2012年3月 [14]
- 2012年2月 [3]
- 2012年1月 [5]
- 2011年12月 [1]
- 2011年11月 [3]
- 2011年10月 [1]
- 2011年9月 [4]
- 2011年8月 [1]
- 2011年7月 [3]
- 2011年6月 [5]
- 2011年5月 [5]
- 2011年4月 [4]
- 2011年3月 [9]
- 2011年2月 [3]
- 2011年1月 [5]
- 2010年12月 [7]
- 2010年11月 [9]
- 2010年10月 [6]
- 2010年9月 [4]
- 2010年7月 [8]
- 2010年6月 [10]
- 2010年4月 [12]
- 2010年3月 [13]
- 2010年2月 [2]
- 2010年1月 [5]
- 2009年12月 [2]
- 2009年11月 [1]
- 2009年10月 [5]
- 2009年9月 [3]
- 2009年8月 [5]
- 2009年7月 [2]
- 2009年6月 [6]
- 2009年5月 [5]
- 2009年4月 [6]
- 2009年3月 [8]
- 2009年2月 [5]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [3]
- 2008年11月 [5]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [45]
- 2008年8月 [4]
- 2008年4月 [2]
- 2007年10月 [1]
- 2007年4月 [1]