- Information
- DH拠点セミナー [19]
- GCOEセミナー [7]
- download [1]
- スクラップ [10]
- データ集 [9]
- 事務局連絡 [9]
- 刊行物 [19]
- News Letter [2]
- 募集情報 [75]
- 国際シンポジウム [12]
- DH-JAC2009 [49]
- タイムテーブル [2]
- 概要 [1]
- 発表要旨 [20]
- 講師プロフィール [21]
- DH-JAC2011 [1]
- 文化情報学専修 [5]
- 研究プロジェクト [9]
- 研究メンバー [11]
- 研究会・イベント [141]
2011年2月 9日
第1回 デジタル時代の学芸員スキルアップ講座
立命館大学デジタル・ミュージアム人材育成パート企画
第1回 デジタル時代の学芸員スキルアップ講座
ーアナログ資料とデジタルアーカイブー
2009年度に準備プロジェクトを行ない、本年度本格的に始動したデジタル・ミュージアムプロジェクトは、急速に進歩しつつあるデジタル技術や情報技術を博物館や美術館の現場で活用し、活動をより活性化させことを目的しています。立命館大学では、技術開発のみではなく、実際にミュージアムを運営スタッフである学芸員の活動を重視しており、人材育成研究パートを置いています。
ここでは、デジタル時代において学芸員に求められる情報技術や知識、ならびにデジタル技術を活用した博物館運営能力とは何なのかについて調査し、学芸員の教育カリキュラムを構築することを目指しています。
本年度は、これまで国内外でのネットワークを構築してまいりましたが、2月に実際にミュージアムの現場で働いていたり、学芸員を目指しながら大学院で学ぶ院生に参加してもらい、デジタルミュージアムの前提となる収蔵品等のデジタル化実習やデジタル技術活用の考え方について下記のような、5日間の集中ワークショップを実施します。
つきましては、下記の通りワークショップへの参加者を募集しますので、奮ってご応募ください。
なお、今回対象とする素材は、文化財や美術品、古文献、映像フィルムですが、いずれも日本で制作された作品です。日本美術や日本の文化財に興味のある方を優先します。日本語能力の有無は問いません。
記
日時:2月7日~11日 10時~17時
場所:立命館大学アート・リサーチセンター(京都・衣笠キャンパス)
受講料は無料です。
・居住国からの京都までの渡航費実費(海外からの場合)
・居住地から京都までの交通費実費(国内の場合)
・当該期間中の滞在費ならびに若干の日当
を支給します。
募集人数
国内 3~4名
国外 3~4名
学内 2~3名
内容 講義と実習・見学による構成
1日目( 7日・月) デジタル時代の学芸員とデータベース
2日目( 8日・火) 古文献のデジタルアーカイブ
3日目( 9日・水) 古典籍のデジタルアーカイブ
4日目(10日・木) 古フィルムのデジタルアーカイブ
5日目(11日・金) 立体物のデジタルアーカイブ ・ 意見交換会
なお、 参加者には、レポートの提出を求めます。
問合せ先:
立命館大学・理工リサーチオフィス(青柳) E-mail: t-aoyagi★st.ritsumei.ac.jp ※★を@にしてお送りください。
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1丁目1-1
TEL:077-561-2815(Ex.515-6547) FAX:077-561-2811(Ex.515-7509)
主催:文部科学省「デジタル・ミュージアムの展開に向けた実証実験システムの研究開発事業」(デジタルミュージアム事業))
共催:文部科学省グローバルCOE(立命館大学)「日本文化デジタルヒューマニティーズ拠点」・立命館大学アート・リサーチセンター
----------------------------------------------------------
本講座は、文部科学省デジタル・ミュージアム事業の一環として実施されます。本事業は、デジタル情報技術を応用した新たなミュージアム展開のために、文化を五感でインタラクティブ(対話的)に体感する統合システム構築に向けた研究を行います。ここでは、デジタル技術や環境を理解し、積極的に博物館の活動にこれを取り入れられるデジタル・キュレーター養成を重要な課題と位置づけています。デジタル技術を利用して展示物のもつ魅力を十分に発揮する展示を設計、デジタルデータの取得・構造化・発信のできることなど、人材の育成を行なうための教育プログラムの開発を行っています。
立命館大学アート・リサーチセンターは、文部科学省グローバルCOE「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ」拠点として、デジタル時代にふさわしく、人文学研究に有功に情報技術を取り入れながら教育・研究活動を進めている研究所です。
古典芸能などの無形文化財のデジタルアーカイブ、京都の全体をデジタルアー期イブするバーチャル京都プロジェクト、浮世絵や書籍・工芸品など世界の日本文化財をデジタルアーカイブする日本文化財世界共有プロジェクトなどが進行しています
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 第1回 デジタル時代の学芸員スキルアップ講座
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/3702
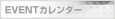
- 言語選択
- 最近のエントリー
- 紀要「アート・リサーチ」第15号の原稿を募集します(〆切:2014/9/23)
- デジタル技術が 生み出す 新たな文化効果ー洛中洛外図屏風 舟木本 編
- 祇園祭 デジタル・ミュージアム展2014
- 分業から協業へ -大学が、若冲と京の伝統工芸を未来に繋げる-
- 第12回 DH拠点セミナー
- アーカイブ
- 2014年9月 [1]
- 2014年7月 [4]
- 2014年6月 [4]
- 2014年5月 [3]
- 2014年4月 [3]
- 2014年3月 [3]
- 2014年2月 [2]
- 2014年1月 [3]
- 2013年12月 [5]
- 2013年11月 [8]
- 2013年10月 [1]
- 2013年9月 [2]
- 2013年8月 [3]
- 2013年7月 [2]
- 2013年6月 [4]
- 2013年5月 [1]
- 2013年4月 [4]
- 2013年3月 [6]
- 2013年2月 [3]
- 2013年1月 [1]
- 2012年12月 [2]
- 2012年11月 [3]
- 2012年10月 [6]
- 2012年9月 [3]
- 2012年8月 [2]
- 2012年7月 [3]
- 2012年6月 [2]
- 2012年5月 [1]
- 2012年4月 [1]
- 2012年3月 [14]
- 2012年2月 [3]
- 2012年1月 [5]
- 2011年12月 [1]
- 2011年11月 [3]
- 2011年10月 [1]
- 2011年9月 [4]
- 2011年8月 [1]
- 2011年7月 [3]
- 2011年6月 [5]
- 2011年5月 [5]
- 2011年4月 [4]
- 2011年3月 [9]
- 2011年2月 [3]
- 2011年1月 [5]
- 2010年12月 [7]
- 2010年11月 [9]
- 2010年10月 [6]
- 2010年9月 [4]
- 2010年7月 [8]
- 2010年6月 [10]
- 2010年4月 [12]
- 2010年3月 [13]
- 2010年2月 [2]
- 2010年1月 [5]
- 2009年12月 [2]
- 2009年11月 [1]
- 2009年10月 [5]
- 2009年9月 [3]
- 2009年8月 [5]
- 2009年7月 [2]
- 2009年6月 [6]
- 2009年5月 [5]
- 2009年4月 [6]
- 2009年3月 [8]
- 2009年2月 [5]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [3]
- 2008年11月 [5]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [45]
- 2008年8月 [4]
- 2008年4月 [2]
- 2007年10月 [1]
- 2007年4月 [1]