- 木村研究室
- プロジェクト活動 [30]
- シンポジウム [11]
- 発表 [21]
- 研究会 [19]
- 調査 [2]
- 講演 [1]
- 連絡 [16]
- 参考 [4]
- 他機関のデジタルアーカイブ [3]
- 他機関のデータベース [3]
- 学会情報 [5]
- 文学研究とデータベース [3]
- 日本近代文学研究 [1]
2009年11月13日
「外地」文学研究会(第10回)
「外地」文学研究会を下記のように行いました。
○日時:11月13日(金)17:00-18:00
○場所:アート・リサーチセンター第二会議室
○内容:イ・ヨンスク『「ことば」という幻影』を読む―〈国語〉と〈言語的マイノリティ〉をめぐる考察
○テキスト:イ・ヨンスク『「ことば」という幻影』「第6章 「正音」の帝国」「第7章 国語学・言語学・国学」「第12章 手話言語と言語政策」
○報告者:岩根卓史
○報告者:岩根卓史
○参考文献
滝浦真人『山田孝雄―共同体の国学の夢』講談社、2009年
石川公彌子『〈弱さ〉と〈抵抗〉の近代国学』講談社選書メチエ、2009年
澁谷智子『コーダの世界―手話の文化と声の文化』医学書院、2009年
○参加者:4名
石川公彌子『〈弱さ〉と〈抵抗〉の近代国学』講談社選書メチエ、2009年
澁谷智子『コーダの世界―手話の文化と声の文化』医学書院、2009年
○参加者:4名
近代の日本語教育史や「国語」観念の検討は、「外地」日本語文学を読む際に避けて通れない問題である。
今回は報告者の関心に基づいて問題点をピックアップする形で、伊沢修二の言語教育観、江戸期の「国学」に対する明治期の「国語学」のスタンス、手話言語という「言語的マイノリティ」の考察を扱った章を取り上げた。
個人的には、言語/非言語の境界線を引くこと自体にともなう政治性という問題が強く意識された。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 「外地」文学研究会(第10回)
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/2807
コメントする

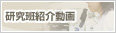
- 最近のエントリー
- 「外地」文学研究会(第13回)
- インドネシア・韓国・日本 共同セミナー
- アジアン・ディアスポラ研究会
- 「文学・文化に見る韓国併合と「朝鮮」への眼差し」
- シンポジウム「帝国日本の移動と東アジアの植民地文学」
- アーカイブ
- 2011年2月 [1]
- 2011年1月 [1]
- 2010年12月 [1]
- 2010年10月 [2]
- 2010年8月 [2]
- 2010年7月 [1]
- 2010年6月 [1]
- 2010年5月 [2]
- 2010年3月 [3]
- 2010年2月 [1]
- 2010年1月 [1]
- 2009年12月 [4]
- 2009年11月 [2]
- 2009年10月 [1]
- 2009年8月 [1]
- 2009年7月 [4]
- 2009年6月 [2]
- 2009年5月 [2]
- 2009年4月 [3]
- 2009年3月 [6]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [4]
- 2008年11月 [1]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [1]
- 2008年8月 [3]
- 2008年7月 [3]
- 2008年6月 [7]
- 2008年5月 [6]
- 2008年2月 [5]
- 2008年1月 [1]
- 2007年12月 [2]
- 2007年11月 [7]
- 2007年10月 [2]