- 木村研究室
- プロジェクト活動 [30]
- シンポジウム [11]
- 発表 [21]
- 研究会 [19]
- 調査 [2]
- 講演 [1]
- 連絡 [16]
- 参考 [4]
- 他機関のデジタルアーカイブ [3]
- 他機関のデータベース [3]
- 学会情報 [5]
- 文学研究とデータベース [3]
- 日本近代文学研究 [1]
2009年7月24日
「外地」文学研究会(第8回)
「外地」文学研究会を下記のように行いました。
○日時:7月24日(金)17:00-18:00
○場所:アート・リサーチセンター第2会議室
○内容:研究紹介――キム・スング『李箱、欲望の記号』(ウォルイン社)を読む
○報告者:岩根卓史(本学博士課程)
○参加者:4名
○報告者:岩根卓史(本学博士課程)
○参加者:4名
○参考文献
・川村湊『〈酔いどれ船〉の青春』インパクト出版、2000年
・同『ソウル都市物語』平凡社新書、2000年
・崔真碩「〈近代の鳥瞰図〉としての李箱文学」、『李箱作品集成』作品社、2006年所収
・川村湊『〈酔いどれ船〉の青春』インパクト出版、2000年
・同『ソウル都市物語』平凡社新書、2000年
・崔真碩「〈近代の鳥瞰図〉としての李箱文学」、『李箱作品集成』作品社、2006年所収
→詳細は続きをご覧下さい。
今回は、韓国における文学研究の動向を知るという主旨で、李箱の研究書であるテクストの内、序論・第四章・結論について、報告者による翻訳・紹介があった。研究史の検討と問題的からなる序章では、李箱を近代性の先駆者として見るあまり、同時代文学者との比較に留まり、彼の文学の固有性を見なかった先行研究の問題点が指摘されている。そして、著者が李箱文学を分析する理論的背景が示される。第四章では、表題にもある「欲望」の問題について、作中に登場する「売春婦」のイメージや「買春」に対する男性主人公の意識が分析されており、結論では「近代社会の男性主体の処した存在論的危機のドラマ」という李箱文学全体に対する筆者の位置づけがなされている。一部の紹介ではあったが、様々に触発される点があり、また日本近代文学研究が、李箱の文学をどう読んでいくか、という今後の問題意識を促す貴重な報告であった。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 「外地」文学研究会(第8回)
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/2500
コメントする

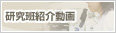
- 最近のエントリー
- 「外地」文学研究会(第13回)
- インドネシア・韓国・日本 共同セミナー
- アジアン・ディアスポラ研究会
- 「文学・文化に見る韓国併合と「朝鮮」への眼差し」
- シンポジウム「帝国日本の移動と東アジアの植民地文学」
- アーカイブ
- 2011年2月 [1]
- 2011年1月 [1]
- 2010年12月 [1]
- 2010年10月 [2]
- 2010年8月 [2]
- 2010年7月 [1]
- 2010年6月 [1]
- 2010年5月 [2]
- 2010年3月 [3]
- 2010年2月 [1]
- 2010年1月 [1]
- 2009年12月 [4]
- 2009年11月 [2]
- 2009年10月 [1]
- 2009年8月 [1]
- 2009年7月 [4]
- 2009年6月 [2]
- 2009年5月 [2]
- 2009年4月 [3]
- 2009年3月 [6]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [4]
- 2008年11月 [1]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [1]
- 2008年8月 [3]
- 2008年7月 [3]
- 2008年6月 [7]
- 2008年5月 [6]
- 2008年2月 [5]
- 2008年1月 [1]
- 2007年12月 [2]
- 2007年11月 [7]
- 2007年10月 [2]