- 木村研究室
- プロジェクト活動 [30]
- シンポジウム [11]
- 発表 [21]
- 研究会 [19]
- 調査 [2]
- 講演 [1]
- 連絡 [16]
- 参考 [4]
- 他機関のデジタルアーカイブ [3]
- 他機関のデータベース [3]
- 学会情報 [5]
- 文学研究とデータベース [3]
- 日本近代文学研究 [1]
2009年7月19日
日本文学協会・第29回研究発表大会
本拠点に関係あるテーマで、下記の発表を行いました。
○タイトル:張赫宙「迫田農場」における「地主」の表象――当時の新聞報道との比較から――
○発表者:楠井清文
○日時:7月19日(日)
○場所:静岡大学
発表要旨は続きをご覧下さい。
日本文学協会HPはこちら
○要旨:張赫宙(チャン・ヒョクチュ)「迫田農場」(『文学クオタリイ』一九三二・六)は、大地主・新井半兵衛によって小作人に開放された理想的な農場が、「×山」(釜山と推測される)の地主「迫田」に売却されてから、急に小作料の取り立てが苛烈になり、遂に農民が地主の邸宅まで押しかけ、代表達が警察に連行された後は稲刈りのストライキを決意するという物語である。他の初期作品同様、朝鮮農民の生活を主題とした作品だが、「小作争議の発生から展開の過程がスムーズに述べられている」(白川豊氏)という特徴がある。本発表では、氏も指摘するモデルとなった迫間農場の小作争議に関する当時の新聞報道を検討し、事件の経緯が物語化された過程や地主「迫田」の表象について考えたい。
○内容
発表ではまず、張赫宙が文壇登場した背景について、内地に在住する日本人の知り得ない植民地支配の「事実」を日本語文壇に伝達する、という期待の枠組の中で彼のデビューがあったことを、同時代評から論じた。そして張赫宙自身がそのような期待の中で、どのような形で初期の創作活動を行っていったか、について考察した。具体的には「迫田農場」が参照したと考えられる朝鮮語新聞『東亜日報』の記事を指摘し、作品のモデルとなった迫間農場小作争議について、日本語新聞ではほとんど報道がなく当時の読者が知り得なかったこと、そのような特異な題材を用いた点に特徴が認められると論じた。
会場からは、新聞記事をもとに張赫宙が創作を付け加えた点、特に日本人植民者の心理を描いている点にもっと注目すべきである、また張赫宙のデビューについて朝鮮の日本人達に反応がなかったのは総督府の検閲が存在するからだ、という指摘があった。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 日本文学協会・第29回研究発表大会
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/2501
コメントする

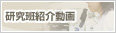
- 最近のエントリー
- 「外地」文学研究会(第13回)
- インドネシア・韓国・日本 共同セミナー
- アジアン・ディアスポラ研究会
- 「文学・文化に見る韓国併合と「朝鮮」への眼差し」
- シンポジウム「帝国日本の移動と東アジアの植民地文学」
- アーカイブ
- 2011年2月 [1]
- 2011年1月 [1]
- 2010年12月 [1]
- 2010年10月 [2]
- 2010年8月 [2]
- 2010年7月 [1]
- 2010年6月 [1]
- 2010年5月 [2]
- 2010年3月 [3]
- 2010年2月 [1]
- 2010年1月 [1]
- 2009年12月 [4]
- 2009年11月 [2]
- 2009年10月 [1]
- 2009年8月 [1]
- 2009年7月 [4]
- 2009年6月 [2]
- 2009年5月 [2]
- 2009年4月 [3]
- 2009年3月 [6]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [4]
- 2008年11月 [1]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [1]
- 2008年8月 [3]
- 2008年7月 [3]
- 2008年6月 [7]
- 2008年5月 [6]
- 2008年2月 [5]
- 2008年1月 [1]
- 2007年12月 [2]
- 2007年11月 [7]
- 2007年10月 [2]