- 木村研究室
- プロジェクト活動 [30]
- シンポジウム [11]
- 発表 [21]
- 研究会 [19]
- 調査 [2]
- 講演 [1]
- 連絡 [16]
- 参考 [4]
- 他機関のデジタルアーカイブ [3]
- 他機関のデータベース [3]
- 学会情報 [5]
- 文学研究とデータベース [3]
- 日本近代文学研究 [1]
2009年3月14日
シンポジウム内容③
○太平洋諸島の「脱植民地化」と日本文化
須藤直人(立命館大学)
太平洋諸島の文化と日本文化の相互的な影響関係やイメージの往還を、「脱植民地化」という文脈において考えたい。
パラオのアバイ(集会所)は、自然や社会との結びつきを象徴する建築物であり、世界との関係を取り結ぶ場所である。だが植民地支配と観光はアバイを「卑猥」「幼稚」な「エキゾティック」な建物に変えた。ドイツや日本の統治下にあった当時から、その側壁に描かれた物語絵が「観光のまなざし」の的となるが、アバイにおいて男性が他村から送られる女性(モゴル)と出会う制度が公娼制度と解され、アバイに宿泊することは「野蛮」な風習と見られた。彫刻家であり民族学者である土方久功の影響により、アバイの物語絵がストーリー・ボードとして旅行者向けの土産物となると、パラオにとってのアバイの意味が再び変わってゆく。他方、パラオにおいて土方と親交があった中島敦の短編にはアバイの絵物語を題材としたものが見られる。そこでアバイは、植民地支配・資本主義システムに服しながら同化されない単独性の表象という意味を与えられている。
タトゥ(刺青)も自然や社会との関係性を構築するための「衣装」であったが、同様に「野蛮」な風習と見なされると、もはやそれは「衣装」ではなくなった。サモアの作家アルバート・ウェントは、タトゥを「衣装」と見るサモア社会の見方を、日本語の「和」という言葉を用いて説明している。「裸」にされた身体に再び「衣装」を着せること、すなわち、植民地支配の影響を受け、資本主義システムに包摂されながらも、単独性を保持した関係性や主体を再構築することが脱植民地化であり、日本を訪れたウェントはそのようなサモアと共通の単独性を日本に見出している。こうした単独性を相互に結びつける場として「オセアニア」を捉える太平洋作家達に呼応する様に、ミクロネシアを訪れた池澤夏樹の小説テクストは、ストーリー・ボードと並びパラオを世界と結び付ける、18世紀に初めてイギリスを訪れたパラオ人リー・ボーの「高貴な未開人」のイメージを書き換えている。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: シンポジウム内容③
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/1535
コメントする

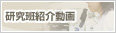
- 最近のエントリー
- 「外地」文学研究会(第13回)
- インドネシア・韓国・日本 共同セミナー
- アジアン・ディアスポラ研究会
- 「文学・文化に見る韓国併合と「朝鮮」への眼差し」
- シンポジウム「帝国日本の移動と東アジアの植民地文学」
- アーカイブ
- 2011年2月 [1]
- 2011年1月 [1]
- 2010年12月 [1]
- 2010年10月 [2]
- 2010年8月 [2]
- 2010年7月 [1]
- 2010年6月 [1]
- 2010年5月 [2]
- 2010年3月 [3]
- 2010年2月 [1]
- 2010年1月 [1]
- 2009年12月 [4]
- 2009年11月 [2]
- 2009年10月 [1]
- 2009年8月 [1]
- 2009年7月 [4]
- 2009年6月 [2]
- 2009年5月 [2]
- 2009年4月 [3]
- 2009年3月 [6]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [4]
- 2008年11月 [1]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [1]
- 2008年8月 [3]
- 2008年7月 [3]
- 2008年6月 [7]
- 2008年5月 [6]
- 2008年2月 [5]
- 2008年1月 [1]
- 2007年12月 [2]
- 2007年11月 [7]
- 2007年10月 [2]