- 木村研究室
- プロジェクト活動 [30]
- シンポジウム [11]
- 発表 [21]
- 研究会 [19]
- 調査 [2]
- 講演 [1]
- 連絡 [16]
- 参考 [4]
- 他機関のデジタルアーカイブ [3]
- 他機関のデータベース [3]
- 学会情報 [5]
- 文学研究とデータベース [3]
- 日本近代文学研究 [1]
2008年10月25日
第18回・韓国日本近代学会
要旨:本発表で中心に取り上げる佐藤清(1885~1960)は、英文学者であり詩人でもある。東京帝国大学英文科卒業後、二度の英仏留学を経て、1926年開設したばかりの京城帝国大学法文学部教授として赴任した。以後、1945年退官するまでの約20年間、彼は京城大学で英文学を講じると共に、詩人として朝鮮の日本人詩壇に関わり続けた。
今日、佐藤清に注目する理由は二つある。第一には、佐藤と他の詩人達との相関を通して、当時の朝鮮における日本人の文学活動の様相が浮かび上がって来るからである。佐藤の来航を最も歓迎したのは、内野健児ら朝鮮の日本人詩人だった。佐藤より早く1921年朝鮮に渡った内野は、『耕人』『朝』『亜細亜詩脈』等の雑誌を刊行し、朝鮮詩壇の隆盛に勤めていた。重要なのは、彼らが自分達の文学を「郷土文学」と捉え、「朝鮮」という主題を直視し、実作に忠実に生かそうとしていた点である。その意味で、彼らは「内地」中心の文学概念に批判的だった。佐藤もまた、『京城日報』「京日詩壇」選者を務め、「朝鮮郷土の詩歌」創作を目的とする同人誌『赭土』に関わるなど、朝鮮に根ざした文学の展開を理想としていた。しかし、その活動に多く加わったのは日本人であり、「郷土文学」の理念は、任展慧氏も指摘するように、植民者の視点という限界を越えるものではなかった。つまり、日本人が朝鮮を「郷土」と見なすことで、植民地支配がより自然なものとされる危険性に、彼ら自身は無自覚だったのである。このような20年代の朝鮮の日本人による文学活動の軸となった「郷土文学」の問題点を、佐藤の実作や他の詩人との相関から浮かび上がらせることが第一の目的である。
第二の理由は、20年代から40年代にかけて、韓国と日本の近代文学がどのように交錯したかを、京城大学という場を手がかりに辿ることができるからである。唯一の官立高等教育機関だった京城大学は、一般の朝鮮人に開かれたものではなかった。しかし、佐野正人氏は李孝石・崔載瑞ら30年代に活躍した文学者が英文科から輩出されていることに注目し、そこでは「トランスナショナルな場」が成立しており、朝鮮人・朝鮮文学のアイデンティティ形成に「英文学」が何らかの役割を果たしたのではないかと論じている。佐藤自身「私の生涯に最も大きい恩恵を与えられた(略)インスチチューション」として京城大学を挙げ、朝鮮人学生が「民族の解放と自由とを外国文学の研究に見出さんとしていた」ことに撃たれたと戦後回想している。植民地における「英文学」の受容という視点を通して、韓国と日本が相互に作用し合う複雑な近代文学の展開を考察すること。これが第二の目的である。
以上のように、本発表では佐藤清だけに焦点を当てるのではなく、その周辺との関わりから、(1)朝鮮での日本人の文学活動(2)「英文学」を通した植民地での近代文学の展開、の二点を明らかにしたい。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 第18回・韓国日本近代学会
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/1328
コメントする

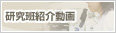
- 最近のエントリー
- 「外地」文学研究会(第13回)
- インドネシア・韓国・日本 共同セミナー
- アジアン・ディアスポラ研究会
- 「文学・文化に見る韓国併合と「朝鮮」への眼差し」
- シンポジウム「帝国日本の移動と東アジアの植民地文学」
- アーカイブ
- 2011年2月 [1]
- 2011年1月 [1]
- 2010年12月 [1]
- 2010年10月 [2]
- 2010年8月 [2]
- 2010年7月 [1]
- 2010年6月 [1]
- 2010年5月 [2]
- 2010年3月 [3]
- 2010年2月 [1]
- 2010年1月 [1]
- 2009年12月 [4]
- 2009年11月 [2]
- 2009年10月 [1]
- 2009年8月 [1]
- 2009年7月 [4]
- 2009年6月 [2]
- 2009年5月 [2]
- 2009年4月 [3]
- 2009年3月 [6]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [4]
- 2008年11月 [1]
- 2008年10月 [3]
- 2008年9月 [1]
- 2008年8月 [3]
- 2008年7月 [3]
- 2008年6月 [7]
- 2008年5月 [6]
- 2008年2月 [5]
- 2008年1月 [1]
- 2007年12月 [2]
- 2007年11月 [7]
- 2007年10月 [2]