- 赤間研究室
- 0.プロジェクト活動・連絡 [86]
- 研究会・イベント [60]
- 1京都芸能・文化 [12]
- 上方芸能研究 [14]
- 国立音楽大竹内文庫 [1]
- 能楽教育コンテンツ [4]
- 2版本と版画の美 [13]
- 1大英博物館DA [4]
- 2近世版木総合研究 [20]
- 3資料DB応用・表現 [7]
- 1ARC資料公開P [2]
- 2春画P [2]
- 3舞鶴市糸井文庫PJ [3]
- 4京都俳諧 [4]
- 5江戸文化と中国 [1]
2008年4月 9日
NewsLetter2号「版画と版本の美」プロジェクト紹介
グローバルCOE 日本文化DHのニュースレター2号が刊行されました。
⇒全部みる(ただし重い)
本プロジェクトから赤間が「版画と版本の美」プロジェクトの研究内容についてエッセーを掲載しています。
⇒ここをクリック(軽い)
-浮世絵アーカイブの現場から-
赤間 亮
立命館大学大学院文学研究科・教授
日本文化研究班リーダー
 本プロジェクトでは、江戸時代の出版・印刷文化についての研究を進めている。具体的な対象は、これまでも力を入れてきた、浮世絵や絵入板本はもちろんのこと、板木そのものや、合羽摺という京都や大阪でよく使われた彩色手法に及んでいる。これらの対象を通常の人文系の方法のみならず、デジタルアーカイブ技術を駆使して研究を進めていることが特徴となっており、そこがデジタル・ヒューマニティーズ(DH)プロジェクトに参加している所以でもある。デジタルアーカイブ技術といっても、いわゆる“技術開発”ではなく、すでに実用化された機器、ソフトウェアを駆使して効率よくデジタルコピーを生産し、デジタルファイルを様々に加工・整理して行くところに強みがあり、今回のグローバルCOE以前の大規模プロジェクト研究により培われたノウハウが生きてくる。 今回は、この内、浮世絵アーカイブについて述べてみたい。
本プロジェクトでは、江戸時代の出版・印刷文化についての研究を進めている。具体的な対象は、これまでも力を入れてきた、浮世絵や絵入板本はもちろんのこと、板木そのものや、合羽摺という京都や大阪でよく使われた彩色手法に及んでいる。これらの対象を通常の人文系の方法のみならず、デジタルアーカイブ技術を駆使して研究を進めていることが特徴となっており、そこがデジタル・ヒューマニティーズ(DH)プロジェクトに参加している所以でもある。デジタルアーカイブ技術といっても、いわゆる“技術開発”ではなく、すでに実用化された機器、ソフトウェアを駆使して効率よくデジタルコピーを生産し、デジタルファイルを様々に加工・整理して行くところに強みがあり、今回のグローバルCOE以前の大規模プロジェクト研究により培われたノウハウが生きてくる。 今回は、この内、浮世絵アーカイブについて述べてみたい。浮世絵については、今更言うまでもないことではあるが、日本国内から海外へ輸出され続けており、むしろ海外のコレクションの方が質量ともに優れていることが多い。本稿を書いているのは、2008年2月末のニューヨークであるが、マンハッタンの中央、アジア協会博物館では、「DESIGNED FOR PLEASURE」という江戸初期から幕末までの作品を集めた展覧会が開催されている。同時に、これもまたその会場から歩いて行けるあるギャラリーでは、「Early Images from the Floating World」という日本のある著名なコレクターがかつて持っていた、初期浮世絵の重要な作品群を展示販売している。このコレクションは、50年ぶりに世に出たものであり、いわば幻の作品をニューヨークで目の当りにしたことになり、私自身のショックも大きい。面白いのは、このコレクションが市場に出回ったのは、昨年の6、7月からであり、日本ではその段階ですでに話題を呼んでいたし、本拠点のアート・リサーチセンターも何冊か購入することができた。しかし、このギャラリーのオーナーに言わせると、それらは状態のあまりよくないものであり、従って日本からアメリカに持ち帰ってもあまり需要のないものだったのだそうだ。いかに海外に流れる作品群に名品が多いかが、この逸話からもわかる。
 今回の滞在の目的は、ニューヨーク在住のあるコレクターのものを対象とした調査で、その邸宅の一室を借りて行っている。最終日の展覧会の打合せには、また別のコレクターも参加してきた。彼らは、日本語を読めないのにもかかわらず、自分のコレクションの立派なカタログを作っているのである。なぜ、それが可能なのだろうか。実は、海外の研究者やディーラーあるいは、コレクター自身の方が、日本人よりも多くの作品を見ているだけでなく、研究書や図録・目録も揃っているのである。日本語の読める研究者ももちろん多いが、読めなくてもその絵が何と呼ばれているものなのかどれだけの価値のあるものなのかはわかる環境が、実は揃っているのである。 この環境は、これまで日本にいては共有化が難しかった。それを可能としたのがデジタルアーカイブ技術なのである。現在は、文系のどの研究者も、調査には一眼レフのデジタルカメラを持参し、その場で資料を撮影する姿が見られるが、本プロジェクトの方法は全く違って、一つのコレクション全体をそっくりそのまま高画質 -つまりその場で肉眼の調査記録や記憶するよりも、この複写画像の方が役に立つことが多い -でアーカイブしてしまうのである。鑑定士やディーラー、学芸員、研究者の最初の仕事として、このデジタルアーカイブを実施しておくことで齎される結果は、そうしなかった場合と比べて大きな差が出てくる。展覧会の図録や展覧会開催前の宣伝(紙・WEBを問わず)は、あっという間に進んでいく。今回の調査の詳細には触れないが、2009年度の始めに世界を驚かせることになると思う。デジタルアーカイブ技術とその活用によって、研究が飛躍的に進むものであり、本プロジェクトへの期待は世界から寄せられているため、本拠点に果す役割はきわめて大きいものと実感している。
今回の滞在の目的は、ニューヨーク在住のあるコレクターのものを対象とした調査で、その邸宅の一室を借りて行っている。最終日の展覧会の打合せには、また別のコレクターも参加してきた。彼らは、日本語を読めないのにもかかわらず、自分のコレクションの立派なカタログを作っているのである。なぜ、それが可能なのだろうか。実は、海外の研究者やディーラーあるいは、コレクター自身の方が、日本人よりも多くの作品を見ているだけでなく、研究書や図録・目録も揃っているのである。日本語の読める研究者ももちろん多いが、読めなくてもその絵が何と呼ばれているものなのかどれだけの価値のあるものなのかはわかる環境が、実は揃っているのである。 この環境は、これまで日本にいては共有化が難しかった。それを可能としたのがデジタルアーカイブ技術なのである。現在は、文系のどの研究者も、調査には一眼レフのデジタルカメラを持参し、その場で資料を撮影する姿が見られるが、本プロジェクトの方法は全く違って、一つのコレクション全体をそっくりそのまま高画質 -つまりその場で肉眼の調査記録や記憶するよりも、この複写画像の方が役に立つことが多い -でアーカイブしてしまうのである。鑑定士やディーラー、学芸員、研究者の最初の仕事として、このデジタルアーカイブを実施しておくことで齎される結果は、そうしなかった場合と比べて大きな差が出てくる。展覧会の図録や展覧会開催前の宣伝(紙・WEBを問わず)は、あっという間に進んでいく。今回の調査の詳細には触れないが、2009年度の始めに世界を驚かせることになると思う。デジタルアーカイブ技術とその活用によって、研究が飛躍的に進むものであり、本プロジェクトへの期待は世界から寄せられているため、本拠点に果す役割はきわめて大きいものと実感している。
コメントする


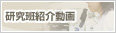
- 最近のエントリー
- アーカイブ
- 2017年8月 [1]
- 2015年7月 [1]
- 2014年7月 [1]
- 2013年7月 [2]
- 2012年1月 [1]
- 2011年11月 [2]
- 2011年9月 [1]
- 2011年8月 [1]
- 2011年7月 [2]
- 2011年5月 [2]
- 2010年11月 [1]
- 2010年10月 [1]
- 2010年9月 [2]
- 2010年8月 [2]
- 2010年7月 [2]
- 2010年6月 [2]
- 2010年3月 [1]
- 2010年2月 [1]
- 2010年1月 [1]
- 2009年12月 [1]
- 2009年11月 [2]
- 2009年10月 [1]
- 2009年9月 [1]
- 2009年8月 [1]
- 2009年7月 [1]
- 2009年6月 [1]
- 2009年4月 [4]
- 2009年3月 [5]
- 2009年2月 [2]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [5]
- 2008年11月 [4]
- 2008年10月 [4]
- 2008年9月 [5]
- 2008年8月 [4]
- 2008年7月 [3]
- 2008年6月 [4]
- 2008年5月 [3]
- 2008年4月 [9]
- 2008年3月 [3]
- 2008年2月 [3]
- 2008年1月 [2]
- 2007年12月 [5]
- 2007年11月 [5]
- 2007年10月 [4]
- 2007年9月 [5]
- 2007年8月 [13]
- 2007年7月 [9]
- 2007年6月 [10]
- 2007年5月 [12]
- 2007年4月 [9]
- 2007年3月 [6]
- 2007年2月 [8]
- 2007年1月 [11]
- 2006年12月 [15]
- 2006年11月 [29]
- 2006年10月 [1]
- 2006年1月 [3]