- 赤間研究室
- 0.プロジェクト活動・連絡 [86]
- 研究会・イベント [60]
- 1京都芸能・文化 [12]
- 上方芸能研究 [14]
- 国立音楽大竹内文庫 [1]
- 能楽教育コンテンツ [4]
- 2版本と版画の美 [13]
- 1大英博物館DA [4]
- 2近世版木総合研究 [20]
- 3資料DB応用・表現 [7]
- 1ARC資料公開P [2]
- 2春画P [2]
- 3舞鶴市糸井文庫PJ [3]
- 4京都俳諧 [4]
- 5江戸文化と中国 [1]
2008年2月29日
カリフォルニア大学バークレー校所蔵双六アーカイブ
 カリフォルニア大学バークレー校東アジア図書館所蔵双六のデジタルアーカイブが完了し、本日、日本から資料を運び返却した。
カリフォルニア大学バークレー校東アジア図書館所蔵双六のデジタルアーカイブが完了し、本日、日本から資料を運び返却した。
東アジア図書館は、アメリカ最大の東アジア系図書蔵書数を誇る専門図書館で、この3月からリニューアルオープンします。返却の機会に、開館前の図書館の見学を許可された。
左図は吹き抜けの開架図書の並ぶ館内。

右図は南に広く開口した窓からは緑豊かなキャンパスが広がる。この窓から見える左のスペースにさらに東アジア研究所が将来建設される計画という。東アジア研究の中心は、もちろん中国が最大のターゲットになるであろうが、日本部門の充実も期待される。

右図、壁には、当館所蔵の日本地図や日本の浮世絵などのデジタルアーカイブされている資料から、デザインをとり、タペストリが貼りつけられている。日本部門担当の司書石松氏は、学生がすぐに悪戯書きをし始めるだろうと笑って話された。
アート・リサーチセンターも数点の双六作品があるが、この分野は弱いと言ってよい。
双六アーカイブコレクションとしては、翔奉庵(山本正勝氏)の約5300枚がよく知られており、群を抜いているが、WEB公開されていない。個人コレクションとしては、築地双六館(吉田修氏)の約100点のコレクションがあるが、吉田氏は、「双六ネット」を運営し、双六について詳しく解説してくれている。このお二人で、出された「双六」(2004年文渓堂)は日本の双六について、わかりやすく解説した名著である。
公的なコレクションでは、現在日本では東京学芸大学図書館の教育双六コレクション(望月コレクション)134点が有名であり、112点がデジタル画像でWEB上で閲覧できる。
また、演劇博物館にも歌舞伎双六を中心として、150点以上の作品があり、これもWEB上での閲覧が可能である。さらに、都立中央図書館には、公的機関では最大コレクションの800点以上のものが登録されていている。
バークレー校については、現在、デジタル撮影が終わり、都立中央図書館の松村・加藤氏にも協力してもらい、WEB公開を目指してデータ整理を進めている。バークレー校コレクションは、全部で155点であり、比較的大きなコレクションであろう。
双六は国外に所蔵されている例をあまり聞かず、海外の双六コレクターがいるかどうかはわからない。このバークレー校のコレクションも三井家から一括してバークレー校の購入された写本・板本のコレクションの中にあったものであり、海外で収集されたものではない。
これらの双六は、廻り双六と呼ばれる種類のもので、双六の目に遭わせて、振り出しからあがりまでをコマが移動していく遊び方である。したがって、これはもちろん玩具ではあるが、錦絵技法により着色がされていて、非常に味わいの深いものである。このコレクションで面白いのは、三井家らしく、歌舞伎や遊郭などのいわゆる軟派な分野のものがないことで、当時の商家の教育方針が見えてくる。
双六をアーカイブした目的は、いくつか上げられる。一つは、バークレー校東アジア図書館が行っている日本の地図の大規模デジタルアーカイブとの共同研究の一環。これは、これまで本プロジェクトが行ってきた、日本地図データベースの延長線上にあるものであるが、双六を地図の一種とみる発想を、東アジア図書館の石松久幸氏と共有したことによる。双六にも、位置情報があり、そこを様々な参加者が移動していく。それぞれの位置には名称があり、そこではなんらかの規則(法律)を有する。いわば、実際には存在しない地理空間を持つのが双六なのである。
まだこの発想が、実際にどのようにWEB上で有効になってくるかは、摸索状態であるが、もしかるすると、5年前から私が問題を投掛けているバーチャルな地理情報や時間情報(つまりフィクションの世界・想像の世界)をどのように時間軸・地理空間に置いていくかという問題とリンクする大きなテーマとなるかも知れない。
コメントする


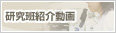
- 最近のエントリー
- アーカイブ
- 2017年8月 [1]
- 2015年7月 [1]
- 2014年7月 [1]
- 2013年7月 [2]
- 2012年1月 [1]
- 2011年11月 [2]
- 2011年9月 [1]
- 2011年8月 [1]
- 2011年7月 [2]
- 2011年5月 [2]
- 2010年11月 [1]
- 2010年10月 [1]
- 2010年9月 [2]
- 2010年8月 [2]
- 2010年7月 [2]
- 2010年6月 [2]
- 2010年3月 [1]
- 2010年2月 [1]
- 2010年1月 [1]
- 2009年12月 [1]
- 2009年11月 [2]
- 2009年10月 [1]
- 2009年9月 [1]
- 2009年8月 [1]
- 2009年7月 [1]
- 2009年6月 [1]
- 2009年4月 [4]
- 2009年3月 [5]
- 2009年2月 [2]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [5]
- 2008年11月 [4]
- 2008年10月 [4]
- 2008年9月 [5]
- 2008年8月 [4]
- 2008年7月 [3]
- 2008年6月 [4]
- 2008年5月 [3]
- 2008年4月 [9]
- 2008年3月 [3]
- 2008年2月 [3]
- 2008年1月 [2]
- 2007年12月 [5]
- 2007年11月 [5]
- 2007年10月 [4]
- 2007年9月 [5]
- 2007年8月 [13]
- 2007年7月 [9]
- 2007年6月 [10]
- 2007年5月 [12]
- 2007年4月 [9]
- 2007年3月 [6]
- 2007年2月 [8]
- 2007年1月 [11]
- 2006年12月 [15]
- 2006年11月 [29]
- 2006年10月 [1]
- 2006年1月 [3]