- 赤間研究室
- 0.プロジェクト活動・連絡 [86]
- 研究会・イベント [60]
- 1京都芸能・文化 [12]
- 上方芸能研究 [14]
- 国立音楽大竹内文庫 [1]
- 能楽教育コンテンツ [4]
- 2版本と版画の美 [13]
- 1大英博物館DA [4]
- 2近世版木総合研究 [20]
- 3資料DB応用・表現 [7]
- 1ARC資料公開P [2]
- 2春画P [2]
- 3舞鶴市糸井文庫PJ [3]
- 4京都俳諧 [4]
- 5江戸文化と中国 [1]
2007年6月28日
赤間プロジェクト研究発表
【論題】
「芝居舞台図の表現」
【発表者】 松葉
芝居小屋の内外を描いた劇場図は、創世期の阿国歌舞伎、遊女歌舞伎などを初めとして、江戸期を通して歌舞伎の歴史とともに描かれ続けていた。演劇史からは、歌舞伎が演じられてきた、土地、空間、その芸態を考える上で重要な資料と位置づけられ、美術史の立場からは、当時の風俗がいきいきと描かれた作品群として評価されてきた。しかし、出版文化が発達したことをきっかけに、芝居小屋の風景を描く、という意味に加えて、興行と深くかかわったメディア媒体としての意味合いも、芝居舞台図には加味されていくようになった。
本発表では、一点目に「風景表現」としての芝居舞台図が初期の肉筆屏風などの作品からどのように継承されていったかを確認する。二点目に、興行を伝えるという上演資料としての性格について、それらがどのようにして成立したか、また実際の興行とどう関わっていたかについて言及する。以上、二点について整理し、芝居舞台図の表現方法とその性質について検討していく。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 赤間プロジェクト研究発表
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/336
コメントする


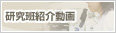
- 最近のエントリー
- アーカイブ
- 2017年8月 [1]
- 2015年7月 [1]
- 2014年7月 [1]
- 2013年7月 [2]
- 2012年1月 [1]
- 2011年11月 [2]
- 2011年9月 [1]
- 2011年8月 [1]
- 2011年7月 [2]
- 2011年5月 [2]
- 2010年11月 [1]
- 2010年10月 [1]
- 2010年9月 [2]
- 2010年8月 [2]
- 2010年7月 [2]
- 2010年6月 [2]
- 2010年3月 [1]
- 2010年2月 [1]
- 2010年1月 [1]
- 2009年12月 [1]
- 2009年11月 [2]
- 2009年10月 [1]
- 2009年9月 [1]
- 2009年8月 [1]
- 2009年7月 [1]
- 2009年6月 [1]
- 2009年4月 [4]
- 2009年3月 [5]
- 2009年2月 [2]
- 2009年1月 [5]
- 2008年12月 [5]
- 2008年11月 [4]
- 2008年10月 [4]
- 2008年9月 [5]
- 2008年8月 [4]
- 2008年7月 [3]
- 2008年6月 [4]
- 2008年5月 [3]
- 2008年4月 [9]
- 2008年3月 [3]
- 2008年2月 [3]
- 2008年1月 [2]
- 2007年12月 [5]
- 2007年11月 [5]
- 2007年10月 [4]
- 2007年9月 [5]
- 2007年8月 [13]
- 2007年7月 [9]
- 2007年6月 [10]
- 2007年5月 [12]
- 2007年4月 [9]
- 2007年3月 [6]
- 2007年2月 [8]
- 2007年1月 [11]
- 2006年12月 [15]
- 2006年11月 [29]
- 2006年10月 [1]
- 2006年1月 [3]