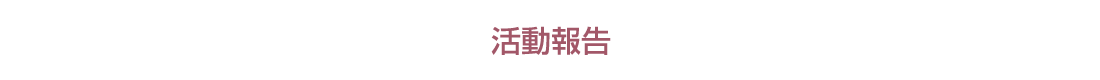研究プロジェクト - 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点
[書込]
代表者:京都市立芸術大学 美術学部・准教授 森野 彰人
富本憲吉(1886-1963)は「色絵磁器」で第1回の重要無形文化財保持者に認定され、文化勲章を受章した陶芸家である。京都市立芸術大学の前身であ る京都市立美術大学において教授・学長も務め、20世紀を代表する多数の芸術家を育成したことでも知られている。2013年、京都市立芸術大学は富本憲吉 記念館(奈良県安堵町)から富本憲吉関連資料の寄贈(940件)をうけた。本研究では、同資料中の富本と英国人陶芸家バーナード・リーチ (1887-1979)の間で交わされた書簡のデジタル画像を用い、画像データベースを構築、それをもとに研究を行う。20世紀の日本と英国を代表する陶 芸家のやりとりを翻刻・研究し、画像及び研究成果をデータベース上で公開することにより、日英の美術工芸史に新たな成果・手法を提示する。
代表者:京都府立医科大学 大学院医学研究科・助教 南川 丈夫
浮世絵は、江戸時代に発展した多色摺木版画であり、現在では日本を代表する伝統美術として伝えられている。しかし、浮世絵の版木は、仮に現存する場合で あっても、摺り工程による摩耗等により、木版画の再現が不能なほど劣化している事が多い。また、浮世絵の伝統技法は主に直伝で受け継がれてきたため、浮世 絵の製作手法や使用した材料が現在では不明であることが多い。そこで、本研究では、版木および版画を光計測・画像解析技術を駆使して科学的に分析すること で、当時の浮世絵の製作手法や材料の再現による伝統技術の復元するための基盤技術の創出を目指す。本研究は、光計測、情報処理、木版研究の専門家と浮世絵 職人の産学・文理融合型のチームで推進する。
代表者:奈良大学 文学部・教授 永井 一彰
申請者らは、近世文学研究・出版研究に関わり、「本」ではなく、近世出版の根本装置であった「板木」に主眼を置き、本からは分かり得なかった情報を板木から得て蓄積することにより、文芸や出版に関わる新視点の獲得を目指している。それにあたり本研究課題では、デジタル技術・IT技術による板木デジタルアー カイブ構築を推進し、日本文化に関わる基礎資料の分析・考察という基礎研究型の成果を創出するとともに、デジタルアーカイブ公開によって研究界全体の基盤 強化をも目指す。さらに、博物館学分野および板木所蔵機関と共同することにより、板木の保存・管理・活用に向けた所蔵機関ネットワークの構築に着手するも のである。
代表者:徳島大学 大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部・准教授 塚本 章宏
本研究課題の目的は、第1に近世近代期の京都において出版された地誌・案内記類のデジタルアーカイブを進めることにある。とりわけ、京都のあらゆる職種に 関する人物・住所情報が記載された地誌・案内記類を取り上げ、近世から近代への移行期における産業の立地や集積の地理的分布とその変遷を明らかにするため のデータ基盤を構築することを目指す。第2の目的として、デジタルアーカイブデータ(画像・テキスト形式)と、地理情報システム(GIS)の管理・分析機 能とを統合して、主要産業のデジタルアトラスを構築する。また、作成されるアトラスは「バーチャル京都」やアート・リサーチセンターのデータベースと連携 したもので、オンライン上で閲覧することが可能なものを想定している。
代表者:立命館大学 衣笠総合研究機構・客員研究員 岩切 友里子
浮世絵専門のイメージ・データベースとして、世界を代表するものにアート・リサーチセンターの浮世絵データベースとJapanese Woodblock Print Searchがある。データベースシステム開発のキーマン二人と、浮世絵専門研究者による新たな研究データベースを開発する。研究データベースは、カラロ グレゾネの日常的な蓄積を可能とする応用的な展開を目指すもので、これによって、具体的にはRoger Keyes北斎カタログ(未刊行)のデータベース 化を実現し、その上で、大英博物館での北斎展に結びつける。
代表者:京都女子大学・准教授 青木 美保子
本研究は、学術資料として俎上に上がっていない近代染織史に関連する資料の整理・蓄積をすすめるものである。近代染織史を研究するための資料は散在し、か つ未整理のものが大半であり、基礎的な資料調査が必要不可欠な段階にある。一方、近代の染織産業については聞き取り調査も研究手法の有効な手段であり、文 献資料には残らない情報を収集することができる。そこで、本研究では、近代染織研究に必要な資料整理や調査を進めつつ、資料・情報を蓄積していく場を構築 し、情報技術を駆使してその共有化を進める。この資料・情報の整理・蓄積・共有化は、染織研究関係者と染織業従事者へ新たな交流の場を提供することとな り、延いては染織業の活性化を模索する足掛かりとなるであろう。
 代表者:メトロポリタン美術館・日本部門主任学芸員 John CARPENTER
代表者:メトロポリタン美術館・日本部門主任学芸員 John CARPENTER
欧米各国に散在する日本美術・工芸品をアート・リサーチセンターのデジタル・アーカイブ技術を活用して、デジタル化し、各所蔵機関が共同で利用できる大規 模なデータベースを構築する。このデータベースを共同利用しながら、とくに、関連するドキュメント、古典籍をもデジタル化することにより、海外に輸出され た美術・工芸品がどのように理解されてきたか、コレクションそのものの総体がどのような性格を持つのか、それらが日本文化理解をどのように深めて来たかを 考察する。データベース化により、分野の異なる美術品・工芸品を結びつけ、また、未整理・新収の文化資源についても、継続的にデジタル・アーカイブするこ とに務める。可能な限り一般公開に結びつけ、この分野の研究環境の高度化を実現する。
代表者:凸版印刷株式会社 文化事業推進本部 奥窪 宏太
本研究では、これまで様々な機関において作製されてきた京都の有形無形の文化資源デジタルコンテンツを集積させ、それらを流通・活用させるためのプラットフォームを構築する。
このプラットフォームを通して、様々な文化観賞シーンにおけるユーザ体験を向上させることはもちろん、それによって文化資源のデジタルコンテンツの蓄積が さらに促進されるという、文化資源の宝庫である京都ならではのデジタル・アーカイブ・スパイラル(循環)を創出し、さらにそれらを相互に利用することに よって、それらを素材とした新たなデジタルコンテンツの構築を促進させる。
また、そうした文化資源デジタルコンテンツの流通や活用に関する著作権などに関しても、ハード・ソフトの両側面から検討する。
代表者:公益財団法人 松竹大谷図書館 武藤 祥子
松竹大谷図書館は、開館以来、演劇史や演劇資料整理の基礎となる演劇上演記録を作成してきた。この上演記録は、主に明治初年から戦前までの東京の記録と、 戦後の各地の大劇場、及び東京の小劇場の記録である。これらの上演記録は、元々図書カードによって整理されていたもので、これを完全にデータベースに移行 しつつ、不完全な情報については、資料の原典に当たるなど精緻化、考証を進めてデータの精度を上げ、日本演劇の研究と資料整理の基礎となる上演記録データ ベースを構築する。