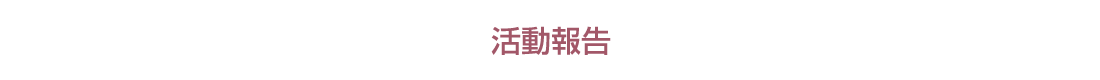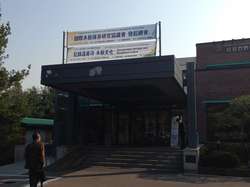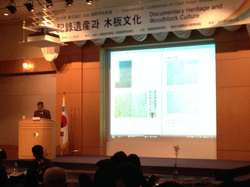研究プロジェクト - 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点
[書込]
代表者:お茶の水女子大学基幹研究院・准教授 中村 美奈子
本研究では、文化の視点から舞踊をとらえ、文理融合的アプローチから、東南アジアの民族舞踊を対象としたデジタル・アーカイブ構築モデルを提示する。従来の舞踊アーカイブでは、映像と舞踊のスコア(舞踊譜)を同時に保存するのが一般的であるが、本研究では、立命館大学ARCのモーションキャプチャシステムを用いて取得した舞踊の三次元動作データと同大学の多視点デジタル映像収録機器を用いた映像、さらに舞踊譜という、多様なデータを含む新しいタイプの舞踊アーカイブ構築を行う。舞踊譜による記譜では、同じく立命館大学で開発された舞踊譜ラバノーテーション(Labanotation)による記譜のためのシステムLabanEditorを、バリ舞踊の記譜と動作再現に適用できるように拡張する。
代表者:京都府立大学 大学院生命環境科学研究科・教授 大場 修
全市に及ぶ大きな戦災を免れた京都市には、市内に4万8千棟もの町家が今なお残る文1)。しかし現在の市街地は画一的な宅地開発や建築活動が進み、町家の数は確実に減少し続け、地域の特性や景観が失われつつある。地域の景観形成に資するまちづくりの方針を考える上で、今日の地域が形成された要因を歴史的・建築的に理解することが不可欠であるが、これまで、近代京都の市街地の形成過程と特に建築様式との関係性に焦点をあてた研究は少ない。本研究は、明治以降、とりわけ三大事業以降の京都の市街地の変遷過程を地域ごとに空間的に把握し、その背景となった社会経済状況、及びそうした社会活動の受け皿としての学区や地域、さらには住宅・建築様式等との関係性を総合的に把握することで、近代京都の市街地形成を史的に整理・解明する。
文1) 京都市・財団法人京都市景観まちづくりセンター・立命館大学"平成20・21年度「京町家まちづくり調査」記録集"平成23年3月
2014年度テーマ設定型 テーマNo. ①「京都をプラットフォームとした文化資源デジタル・コンテンツの利活用と流通の促進に関する研究」は、2015年度、「京都盆地を対象にした文化資源デジタル・コンテンツの利活用と流通を促進するプラットフォーム構築」に研究課題名を変更いたしました。
定例ミーティングを開催しました.
日時:2015年3月19日(木) 16時30分~20時
場所:竹笹堂
参加者:竹中,永井(竹笹堂),谷口(立命館大),南川(京都府立医大)
(1) 予算執行状況の確認
(2) 実験結果と分析
(3) 色材関係報告
(4) 意見交換、その他
以上
プロジェクト全体カンファレンスを終え、GloPACは
3月3日と4日の二日間に分け、ワークショップを催しております。
一日目である3月3日は、下記のように午前中に発表、午後に技術演習を行いました。
『能と歌舞伎における源平ストーリの再表現』
10:00 開会: 赤間亮(ARC), ベーテ・モニカ(JPARC)
10:20-11:00 「信光の風流能と<船弁慶>」リムベンチュー(シンガポ ール国立大学)
11:00-11:40 「<船弁慶の装束〜糸や織から着付けまで>」モニカ ベーテ (中世日本研究所)
11:50-12:20 「能由来の歌舞伎とその舞台表現を探る」ジュリー・イエッツィー (ハワイ大学、マノアキャンパス)
12:20-12:50 討論
13:30~16:00 技術演習
質疑応答や討論会においては、日本語と英語を交え、
日本の伝統芸能に関して活発な意見交換がおこなわれました。
平日の午前中にも関わらず、多くの方々にご来場いただきました。

午後は、ARCサポートボードの支援を受け、技術演習を行いました。
GloPACのメンバーこれまでの疑問の解消や、
今後のGloPACの方針について、話し合いを進めました。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ2日目の3月4日(水)は、下記の催しを行います。
「船弁慶」ワークショップ・実演会
『仕舞の技法 <船弁慶> 実演デモと説明』
時間:10:00-12:00
会場:ARC 多目的室
金剛流能楽師 宇髙竜成、宇髙徳成、ペレッキア・ディエゴ 研究機構プロジェクト研究員
・<船弁慶>のクセ
・<船弁慶>における「中の舞」〜その構造を考察
・<船弁慶>における長刀扱い
ご参加、心よりお待ちしております。
協力者皆様のおかげで,気になっていた残りの資料の撮影ができるようになりました。約1週間で3000カットを目指します。
立命館大学アート・リサーチセンター 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点 全体カンファレンスで、これまでの研究成果の報告を行いました(登壇者:南川丈夫)。
タイトル:浮世絵技法の復元的研究のための光計測・画像解析基盤技術の創出
年月日:2015年3月2日(月)
会場:立命館大学衣笠キャンパス アート・リサーチセンター 多目的ルーム
以上