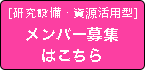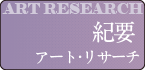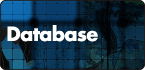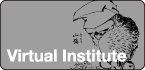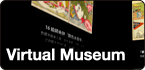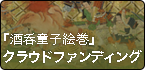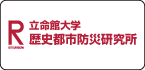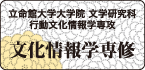| No. | 研究課題名/研究代表者所属・職名・氏名/概要(研究課題名をクリックすると表示) |
|---|
| 1 |
松平定信書簡の研究
A Study of Letters Written by Matsudaira Sadanobu |
寛政の改革を主導した幕府老中松平定信は18世紀の政治・外交等を考察する上で非常に重要な人物である。そのため、戦前では渋沢栄一『楽翁公伝』、近年では藤田覚『松平定信』、高澤憲治『松平定信政権と官制改革』など多くの研究が積み重ねられてきている。しかし、定信に関する一次史料は数多く残されており、桑名市博物館所蔵の書簡史料もそのひとつである。
そこで本研究ではこれまで検討されてこなかった書簡の翻刻を行うことで、定信研究進展の一助とする。 |
| 研究代表者:杉本竜 桑名市博物館 |
| 2 |
信州埴科郡寂蒔村御仕置五人組帳と宗門人別書上帳の解読
Decipherment of residential records of Jakumau in the Edo period |
| 天保5年2月時点の信州埴科郡寂蒔村の五人組帳と宗門人別書上帳を解読する事で、当時寂蒔村に出されていたお触れの内容と、庄屋を務めていた宮坂善右衛門家を本家とした宮坂一族の状況を把握する試みです。 |
研究代表者:Susan L. Burns シカゴ大学東アジア研究所 所長 兼 同大学歴史学部日本史専攻 教授
研究分担者:鍋島洋子 |
| 3 |
舞鶴市糸井文庫の総合的研究
A Comprehensively Study on Primary Sources in the possession of Itoi Bunko Library in Maizuru City |
本研究では、舞鶴市糸井文庫(京都府舞鶴市文化財)における未整理の資料を対象として、新たに翻刻を施す。そして、本文庫が果たした日本文学・日本文化上の役割を解明するために、これらの資料を改めて整理することを主な目的とする。
特に、浦島伝説に関する資料を対象として、これまで実施してきた国際共同研究を発展・深化させる。
そして、立命館大学アート・リサーチセンターの「舞鶴市糸井文庫閲覧システム」を通じて、新規に翻刻した資料のWEB公開を行い、国内外の研究者や一般国民に資するようにする。 |
| 研究代表者:畑恵里子 静岡英和学院大学人間社会学部人間社会学科 教授 |
|
|
| 4 |
近代木版口絵のデジタル研究環境基盤整備
Infrastructure Development of Digital Research Environment for Modern Woodblock-printed Kuchi-e (Frontispieces) |
| 本研究は、明治期における木版多色摺口絵に関するイメージデータベースを構築し、そのデジタル研究環境基盤整備に取り組むものである。同資源は当時の出版・読書文化を窺い知ることができるものであるにもかかわらず、その特性ゆえの扱いづらさから、いずれの研究分野からも敬遠されてきた。以上の背景を踏まえ、本研究は、近代木版口絵にかんするイメージデータベースを構築し、その学術的価値の再検討を通じて、同資料を人文学研究の俎上に載せることを目的とする。2023度は、1)国外所蔵作品のデジタル撮影を実施、2)1をもとにポータルデータベースを拡充、3)成果を書籍・論文としてまとめることに注力する。 |
研究代表者:朝日智雄 口絵研究家
研究分担者:赤間亮, 常木佳奈 |
| 5 |
第三期役者評判記本文を中心とする役者評判記総合情報書庫構築の研究
A Research Project on Construction of Comprehensive Digital Archives Focusing on the Third Phase Yakusha Hyobanki |
役者評判記は、歌舞伎の演技や役者の動向、興行の実態などを追うことのできる基本的な演劇資料である。そのために、万治から明和期(1658-1772)の役者評判記を翻字した『歌舞伎評判記集成』の第一期・第二期(岩波書店、1972-1977・1987-1995)がすでに刊行され、安永から享和期(1772-1804)を対象とした第三期(和泉書院、2018-)の刊行も進んでいる。
本研究では、第三期の対象となる役者評判記について、ARCのクラウドやデータベースを活用しながら翻字テキストデータの正確性を高めつつ、用字の問題、諸本異同の問題等、役者評判記の諸問題を分析することにより、より有効な役者評判記の活用のあり方を提示し、また、蓄積された正確な翻字本文を索引データベースとして構築し、さらなる広範な利用を実現することを目的とする。 |
研究代表者:神楽岡幼子 愛媛大学法文学部 教授
研究分担者:赤間亮, 倉橋正恵, 黒石陽子, 齊藤千恵, 野口隆, 水田かや乃, 金子貴昭 |
| 6 |
全国高地性集落に関するデジタル資料化およびデータベース化プロジェクト
A Digital Database Project on the high-altitude Settlements of the Yayoi Period |
弥生時代に出現する「高地性集落」は,今日,学校教科書や様々な歴史の概説書にその名が登場し,列島古代社会の発展過程を考える上でも重要な位置を占めることから,社会的関心が高いものである。本申請課題の目的は,この高地性集落に関して,日本列島各地の資料の集成・デジタル化を進めるとともに,国内・海外を問わず幅広く活用できるデータベース(「全国高地性集落データベース」(仮))を整備・公開することである。
申請者らは,2020 年度に「弥生時代高地性集落の列島的再検証」(科学研究費補助金・基盤研究(B),20H01356)と題した総合的研究プロジェクトを開始し,列島各地における高地性集落の実態について考古学的に明らかにすることを目指している。この取り組みの一方で,高地性集落に関してはこれまでに多数の調査成果が挙げられてきており,全国各地の事例や資料を一元的にまとめ,学術的研究および教育機関等での学び等に活用できるよう広く情報公開することが必要であると考えている。そこで上記科研プロジェクトとは目的を明確に区別しつつ,情報共有・連動できる体制を整えることで,関連資料のデジタル化・アーカイブ化を鋭意進めて,多方面で運用できるデータベースの構築を目指す。 |
研究代表者:森岡秀人 古代学協会 客員研究員
研究分担者:桑原久男, 國下多美樹, 若林邦彦, 伊藤淳史, 柴田昌児, 田畑直彦, 寺前直人, 森貴教, 山本亮, 宇佐美智之 |
|
|
| 7 |
Three-Dimensional Photogrammetry of Tsukioka Yoshitoshi Artworks for Detecting Symptoms of Mental Health Disorder |
| Mental health affects the productivity and creativity of artists. This research is a part of The Application of Deep Learning Methods for Detecting the Symptoms of Mental Health Disorder from Artworks Datasets. This study aims to create a 3D model of Tsukioka Yoshitoshi’s work using Photogrammetry techniques. Data will be collect from the collection of the Ritsumeikan University Library, other university libraries, and various museums in Japan. Tsukioka’s 3D photogrammetry results will be use as a dataset to detect artists’ mental health disorders. Various works of Tsukioka Yoshitoshi, such as The Lonely House on Adachi Moor, One Hundred Aspects of The Moon, New Forms of Thirty-Six Ghosts, etc. The 3D Photogrammetry Tsukioka digital archive will serve as a development of a 3D artwork database produced during Tsukioka Yoshitoshi’s mental health disorders. The 3D Photogrammetry Database will be helpful as a learning medium for Japanese Art and Art Psychology in Indonesia. |
研究代表者:Wanda Listiani Institut Seni Budaya Indonesia Bandung/Dr.
研究分担者:Anrilia Ema M.N, Ida Ayu Laksmita Sari |
| 8 |
京都映画産業のパイオニア―稲畑勝太郎と横田永之助を中心に
Pioneer of the Kyoto Film Industry―Focusing on Katsutaro Inabata and Einosuke Yokota |
| 本研究は2019年から現在まで「京都の活動写真製作及び興行における横田商会の意義」と題し、日活の創立に尽力した横田永之助と日活の前身横田商会関連の資料発掘およびアーカイブ活動、データベース構築を当該特別研究員として活動してきた。昨年映画を発明したリュミエール兄弟から日本にシネマトグラフ事業を委託された稲畑勝太郎関連のフィルムや写真や映画機材が段ボール4箱分見つかり、資料を管理する稲畑産業から研究目的のため寄贈された。以上の経緯により「京都映画産業のパイオニア」としてこれまでの横田研究と紐付け、新たにこれらの大量の資料のアーカイブおよびデータベース構築を目指す。 |
| 研究代表者:長谷憲一郎 駿河台大学 教授 |
| 9 |
京都を起点とした染色技術及びデザインのグローバルな展開に関する研究
Research of Kyoto-based Global Development of Printing Techniques and Designs |
| 本研究課題では、近代京都を起点として染色産業がどのように国内外へ展開されてきたのか、あるいは影響を受けてきたのかを染色技術やデザインを通じて明らかにする。そのために、学術資料として俎上に上がっていない近代染織史に関連する資料の整理・蓄積を進め、伝統的地場産業と位置付けられてきた京都の染織が実はグローバルな展開―近代以降の西洋技術・デザインの導入だけではなく、戦前から始まるアジア・アフリカへの製品輸出・海外事業展開も含む―をしてきたことを明らかにする。また、研究対象となる染色資料を整理してデータベース構築を進め、近代染織史研究者が研究利用し易いデータベースのあり方について工夫・検討する。更に、当該データベースを活用して染織資料の情報を一元化することを目指す。染色産業の国内外への展開については、特にアフリカンプリント、バティック、ヨーロッパでの機械捺染等の基礎調査とデジタル化を進める。 |
研究代表者:山本真紗子 日本学術振興会特別研究員(RPD)
研究分担者:上田文, 並木誠士, 青木美保子, 鈴木桂子, 杉浦未樹, 加茂瑞穂 |
| 10 |
近世・近代京都における図像を介したモノの受容史―書物・染織品を中心に
History of the Reception of Objects through Iconography in Early Modern and Modern Kyoto―Focusing on books and dyed textiles |
| 本研究では、近世から近代の京都における図像を介した書物・染織品を中心としたモノの受容史を明らかにする。特に浮世絵師・西川祐信(1671-1750)の絵本と江戸時代に制作された小袖を対象とする。例をあげれば、祐信の絵本は、明治に入ってもなお出版され続けた。祐信は同時代においても多大な評価を受けたが、その評価や影響を体系化した上で、近代の再評価の様相と対比させる。近代の時代考証家江馬務や吉川観方がいかにこれらの絵本類や古画、染織品を活用して実践的な故実研究を進めたのかという問題を主軸として、近世のモノ資料が近世と近代のどのように繋いだのかという問題を出版・風俗・染織などの複合的な文化事象を視野に入れて検討していく。 |
研究代表者:石上阿希 京都芸術大学 准教授
研究分担者:加茂瑞穂 |
| 11 |
「林土太郎・基継 映画音響コレクション」のデジタル・アーカイブ構築と発信
Digital Archiving and Promotion of “Tsuchitaro / Mototugu Hayashi’s Movie Sounds Collection” |
| 日本映画における数々の名作を担当した録音技師である林土太郎氏(正確には土に点)、長男の林基継氏が制作時に残した映画・映像の音源(約2000点)の整理およびデジタル・アーカイブの構築作業を行う。映像に関わる音源資料は、日本においてアーカイブ事例が少なくいまだ端緒的な状況であることから、本活動はその嚆矢となる。また、それらの資料に学術的な知見を付与した組織化を進めることで、新しい付加価値を有するNFTアートとして発信することを念頭に置き、国内外に大量に埋没していると想定されるこの分野の文化資源の新たな利活用について検討することを本研究プロジェクトの目的とする。 |
研究代表者:瀧川元気 京都芸術大学 准教授
研究分担者:辻俊成, 細井浩一, 山田真実 |
| 12 |
舞鶴工業高等専門学校1年生を対象としたくずし字翻刻の授業
A cursive script reprinting class for first-year students in at National Institute of Technology (KOSEN), Maizuru College |
舞鶴工業高等専門学校1年生4クラスの古典の授業において、AIでくずし字を読む授業を展開する。くずし字に親しんだことのない高専生にとって、AI技術の力を借りることで、くずし字を読むことができる体験を行い、過去のものをいかに次世代へ継承していくか、科学技術と古典が融合し合えること、融合することでどのような新たな世界を切り拓くことができるかを考えるきっかけとする。加えて、地元舞鶴市が管理する舞鶴市指定文化財 糸井文庫を紹介し、舞鶴、ひいては丹後地方がいかに豊かな伝説を内包し、現代に受容し続けて遺しているかを知る機会とする。
なお、この授業実践は、2020年から行っており、それを継続させるものである。 |
| 研究代表者:荻田みどり 舞鶴工業高等専門学校 准教授 |
| 13 |
クラウド領域を活用したアート・ドキュメンテーション学会の運営
Management for the Japan Art Documentation Society Utilizing Cloud Storage |
1989年4月に開設されたアート・ドキュメンテーション学会は、ひろく芸術一般に関する資料を記録・管理・情報化する方法論の研究と、その実践的運用の追究に携わっている。
本学会には、図書館司書、学芸員、アーキヴィスト、情報科学研究者、美術史・文学史・音楽史・メディア史・文化史・自然史研究者など、約300名の正会員、学生会員、賛助会員が所属している。従来の美術館/博物館・図書館・公文書館・アーカイヴおよび学会といった機関や職能を超領域的に融合する新しい学術団体として、本学会は、新しい未知な課題に取り組む方々の参加をえて、活動を展開している。
国際的視野にもとづいて現代社会の要請する人文学と情報学との連動を追究し、今日的要請に即したデータベースの構築、アーカイヴ・デザイン、また個別的な応用課題の解決に取り組み、着実な成果をあげる。 |
研究代表者:アート・ドキュメンテーション学会
研究分担者:田良島哲, 本間友, 楯石 もも子 |
| 14 |
Okinawan Arts & Culture under Occupation: A Study of Gima Hiroshi and Yamazato Eikichi |
| A research project examining illustrator & prints artist Gima Hiroshi, and playwright, cultural critic, and cultural official Yamazato Eikichi, as examples of Okinawan cultural figures advocating for Okinawan decolonization or independence during the Cold War / Occupation period. Dr. Tomizawa-Kay will focus on collaborations between Gima and independence activist Arakawa Akira, while Dr. Seifman will focus on Yamazato’s writings and activities as a cultural official and museum director under the Occupation-era Ryukyu Government, and on links between ideas about Ryukyuan cultural heritage and pro-independence political positions. |
研究代表者:Eriko Tomizawa-Kay Lecturer, University of East Anglia
研究分担者:Travis Seifman |
| 15 |
国の指定文化財「永源寺文書」と関連寺院所蔵文化財データベースの構築
Compilation of a database of documents nationally designated as cultural properties in the possession of Eigen-ji and related temples |
| 栗東歴史民俗博物館寄託の『永源寺文書』は、平成十四年に国の文化財指定を受けました。その際、永源寺四塔頭の什物を含む九千点余りの古文書、墨跡類の詳細な調査が行われました。開山寂室禅師の墨跡や中世文書を含むこれらの文書群は、永源寺をとりまく朝廷、幕府、地方の有力守護大名などの動向を知る格好の史料であり、中世から近代までの地方禅宗寺院の経営のあり方を解明するための貴重な記録といえます。特に資料の大部分を占める近世史料は、仏教史のみならず特定の地域の歴史文化を繙く公文書(知的財産)として積極的な活用が期待されます。 |
研究代表者:森 慈尋 花園大学国際禅学研究所客員研究員・永源寺教学部員
研究分担者:大田 壮一郎, 渡辺 恒一, 中川 敦之, 田口 幸滋, 寺前 公基, 濱野 未来 |
| 16 |
紀伊半島の海付集落を対象とする社会・空間・被災史デジタルアーカイブの構築
Construction of a Digital Archive of Social, Spatial, and Disaster History of the Kii Peninsula, Japan |
| 本研究は、紀伊半島の海付(漁業)集落を対象に、巨大災害や漸進的な縮退など、今後同地に予測される様々な危機への備えとして、近世以降の災害・復興歴等を含む集落の社会・空 間・生活文化に関する史的データベース及びデジタルアーカイブの構築とその公開を目指すものである。集落内の道・街区・地割・土地利用とその変遷、近世以降現在までの生業、民家の特徴、祭礼など伝統的生活文化の継承状況、加えて宝永・安政・昭和の東南海地震や巨大台風など、過去の被災歴とそこからの復興等に関する記録を集約する。研究成果は、空き家・空き地・高齢化や防災・減災などに関する今後の地域施策や漁業施策を念頭に各自治体とも連携しながら公表し、最終的には列島全域に共通する海付集落の持続と将来的展望に向けて社会化されうる歴史的基盤情報の提供を目的とする。 |
研究代表者:松田 法子 京都府立大学・准教授
研究分担者:河角 直美, 大場 修, 藤岡 換太郎, 福島 幸宏, 小野 映介 |
| 17 |
滋賀県愛知川における伝統的河川管理情報のデータベース化
Development of a database on traditional river management information in the Echi River, Shiga Prefecture, Japan |
| 日本では、豪雨による洪水や土砂災害が頻発し、気候変動による災害の激甚化が懸念されている。地域住民は日常生活を営むにあたり、霞堤や水害防備林、遊水地などのEco-DRR(生態系ベースの災害リスク低減)施設を作成してきた。しかし、都市化や植生の被覆によりこれらの施設の機能が低下し、その存在や位置情報が忘却の彼方にある。そこで、本研究では愛知川流域を対象とし、Eco-DRR施設をはじめとする伝統的河川管理情報のデータベースを構築することを目的とする。具体的には、ドローンを用いたEco-DRR施設の3次元計測成果や、地域住民の水害に対する伝統知などの人文情報をアーカイブする。 |
研究代表者:小倉 拓郎 兵庫教育大学・講師
研究分担者:山内 啓之, 島本 多敬, 水野 敏明, 片山 大輔, 八反地 剛 |
| 18 |
土地利用の粘着性・経路依存性についての研究
Stickiness and path dependence of land use patterns |
| 伝統的に都市経済学においては、土地利用を分析する際に、長期的に安定した状態に注目してきた。土地利用が変化している状態は、一時的なもので、いずれ長期的に安定した状態へと収斂すると考えてきたのである。しかし、実際に土地利用が変化するには時間が必要であり、移行過程がどの程度の時間を必要とするか、更に、その変化の過程が一意ではない、つまり、経路依存性をもつか、はこうした伝統的な分析の有効性を大きく左右する。そこで、本研究では、過去の土地利用がどの程度の期間土地利用を左右するか、また、経路依存性を持つか、を分析する。その際、具体的には、京都の地籍図GISデータを活用し、大正期の京都の土地利用と現在の土地利用の様子を比較する。 |
研究代表者:佐藤泰裕 東京大学大学院経済学研究科・教授
研究分担者:山岸敦 |
| 19 |
「京都ニュース」の保存と活用プロジェクト
“Kyoto News” Preservation and Utilization Project |
| 「京都ニュース」とは、1956年から1994年までの約40年間、京都市広報局が制作し、市中の映画館で上映された市政ニュース映像である。高度成長期からバブル崩壊期までの、京都における市政活動や施策、都市計画による景観の変容、折々の世相や出来事、市民生活、祭事など全容を把握することができるこれらの映像は、「京都学」の見地のみならず、各分野からの学術的なアプローチや研究素材としての価値が大きい。 これまでの研究において、京都市歴史資料館に保管されていた547巻の35mm画ネガ・音ネガ原版の調査と、ARCに寄贈された16㎜フィルムのデジタル化を行った。また、それらデジタル化した映像の一部をデータベース化するとともに、ヴァーチャルインシュティトュートによって公開する準備を整えている。今年度は、これまでにデジタル化(ナレーションのテキストやGISによる場所の特定などを含む)したすべてのデータをデータベース化し公開するとともに、デジタル・アーカイブの運用における課題等について整理する。 |
研究代表者:太田 米男 一般社団法人京都映画芸術文化研究所・代表理事
研究分担者:太田文代、宮本明子、日高由紀、矢野桂司、河角直美、宮田悠史 |
| 20 |
花供養と近世後期京都俳諧の研究
A Study on Kyoto-Haikai through the 18th and 19th Centuries Concerning Hanakuy |
| 京都東山の芭蕉堂で毎年のごとく発刊された『花供養』を全冊にわたって翻刻し、近世後期の京都および全国の俳諧の実態を明らかにする。同資料は、近世後期のおよそ100年間、作者はおよそ全国に及ぶため、近世後期の日本、特に京都の俳諧史資料として有効である。このため、これによって江戸時代の俳諧と近代俳句との連続性あるいは非連続性の検証をおこなうことを目的とする。翻刻データは、すでに公開されている原本デジタル画像と同時に参照できるようにし、研究者間の共有を図る。2017年度より、対象を『花供養』以外の芭蕉顕彰資料に広げており、当年度も引き続き調査を実施するほか、必要に応じてデジタル化を実施する。 |
研究代表者:竹内千代子 立命館大学・非常勤講師
研究分担者:堀淳子、畑忠良、松本節子、赤間亮、金子貴昭 |
| 21 |
「能具大観」翻刻及び英訳プロジェクト
Nōgu taikan Transcribe and Translate Project |
| ピッツバーグ大学図書館貴重書室は、能絵で有名な月岡耕漁の版画集「能楽図絵」「能楽百番」「能画大鑑」「狂言五十番」を所蔵しており、合わせて632枚の能絵をデジタル化し、オンライン展示「Kōgyo: The Art of Noh」で公開しています。新たに山口蓼州の版画「能具大観」102枚をオンライン展示に加えるにあたり、草書体で書かれた各版画の説明文102枚を翻刻、英訳して広く世界の利用者に提供していきます。 |
研究代表者:グッド長橋広行 ピッツバーグ大学図書館・日本・コリア研究司書
研究分担者:長谷川みどり、Elizabeth Oyler |
| 22 |
「20世紀のテレビCMデータベース」の研究教育活用
Research for the utilization of digital database “TVCM of the 20th century” |
| 本研究課題は、立命館大学アート・リサーチセンター内に構築された映像データベース「20世紀のテレビCMデータベース」を研究者に公開し、幅広く研究教育活用を支援するものである。本データベースは株式会社TCJと日本アド・コンテンツ制作協会から貸与を受け、ハイスピリット株式会社とさがスタジオから寄贈を受けた、1950~1990年代制作の日本のテレビCM約18,000本から成る。これまでの外部利用者は2019年度5名、2020年度9名、2021年度8名。研究代表者・分担者は、データベースの運営管理、データの追加・精緻化、閲覧希望者の審査、閲覧者へのアドバイスなどを行う一方で、社会学、メディア史、戦後日本文化史等の観点から自らも本データベースを研究教育に活用する。 |
研究代表者:高野光平 茨城大学人文社会科学部・教授
研究分担者:赤間亮、石田佐恵子、小川博司、竹内幸絵、辻大介、難波功士、山田奨治 |
| 23 |
矢守家絵葉書コレクションのデジタル・アーカイブの構築とその画像およびテキストに関する地理分析
Construction of a digital archive of the Yamori family postcard collection and geographical analysis of its images and texts |
| 2021年4月、立命館大学アート・リサーチセンターに寄贈された矢守家絵葉書コレクション(約1,200枚)の整理とデジタル・アーカイブ構築作業を進める。並行して、画像と文字情報によって、絵葉書が伝える、20世紀前半頃の日本国内の名所旧跡や自然、娯楽や生活風景のほか、災害の様子等について、撮影された場所と年代の特定、景観要素の抽出といった基礎的なデータ分析を行う。これらの調査・分析をもとに、地域情報の伝達媒体としての絵葉書が持っていた文化的、また、社会的な役割とその特質を明らかにすることが本研究の目的である。 |
研究代表者:杉浦和子 京都大学大学院・文学研究科・教授 (アート・リサーチセンター・客員研究員)
研究分担者:矢野桂司、河角直美、佐藤弘隆、夏目宗幸、辻俊成 |
| 24 |
黎明期広告業界誌『プレスアルト』広告現物の研究
Study on advertising materials that early advertisement trade journal " Press Art " distributed |
| 本研究は昭和12(1937)年に広告現物の頒布を目的に京都で創刊された広告業界誌『プレスアルト』の調査とデータベース化によって、広告表現を時代意識の有力な証言者と位置付けた探究に資することを目指すものである。同誌は戦時5年の停止期をはさみ昭和61(1986)年まで、およそ45年間月刊で発刊された。発行部数が極めて少なく幻の存在だったが、334号分、およそ6千点に及ぶ広告現物のほぼ全てが発行人遺族宅にて発見された。同時期の広告現物資料としては比肩する類例がないこれらを、本研究で調査しデジタルデータベース化する。付属冊子に記載の発行年、印刷種別、制作経緯等とあわせみる事が可能な形式を構築し、社会学・デザイン史・写真史・メディア史といった多方向からの学際的なアプローチが可能な広告史探究資料となることを目指す。 |
研究代表者:竹内幸絵 同志社大学社会学部・教授
研究分担者:佐藤守弘、熊倉一紗 |
| 25 |
デジタル・アーカイブの拡充と発展的活用に向けた最盛期義太夫節浄瑠璃作品の研究
Research on Gidayubushi Joruris works during the heyday for the expansion and developmental utilization of digital archives |
| 現在古典芸能として上演される人形浄瑠璃作品のほとんどは近世中期の最盛期の義太夫浄瑠璃作品である。しかし今日まで基礎資料が整わず、研究は後手に回ってきた。本研究ではその時期の未翻刻義太夫節浄瑠璃作品の翻刻を行い、広く資料として公開することを目指す。同時に翻刻したテキストデータをデジタル・アーカイブ化し、文学・言語・音曲等、多角的視点から研究できる環境作りに貢献する。 |
研究代表者:黒石陽子 東京学芸大学・教授
研究分担者:東晴美、田草川みずき、上野左絵、内山美樹子、原田真澄、坂本清恵、高井詩穂、飯島満、森貴志、桜井弘、富澤美智子、山之内英明 |
| 26 |
WEB版演劇百科大事典の構築手法に関する研究
A Research on the Construction Method of a Web-based Encyclopedia of Theatre |
| 演劇に関する総合的な事典としては、平凡社版『演劇百科大事典』があるが、すでに刊行されてから六〇年が経っている。その間の新しい研究成果、演劇活動の歴史を組み込んだ新たな演劇大事典を編集する必要がある。本研究では、編集事業そのものを、オンライン上で行い、『WEB版演劇は薬科大事典』を成立されるための、シミュレーションを行い、実質的な基盤を整えることを目的とする。 |
研究代表者:岩井眞實 名城大学外国語学部・教授
研究分担者:赤間亮、佐和田敬司、平林宜和、阿部由香子、花家彩子 |
| 27 |
村上家文書を活用した17~19世紀出版システムの再検討
Re-Examining the Publishing System from 17th through 19th Century Utilizing Murakami Family Historical Documents |
| 本研究課題は、近世出版研究、近代初期出版研究に携わる立場から、京都の板元・村上勘兵衛家が残した17世紀から19世紀におよぶ出版記録文書(村上家文書、個人所蔵)を対象に、デジタル化と公開、翻刻・読解・分析・考察を進める。それにより、近世および近代初期双方の実態を明らかにするとともに、板元による出版記録という残存量の限られている資料を共有し、学界の研究基盤を拡充する。村上家文書を近世から近代初期にわたる通時的な出版資料として位置づけ、近世出版・近代初期出版双方の実態をあぶり出すのみならず、その過渡期や変容に着目した研究を行う。本研究は科研費(22K00354)を原資とし、ARC-iJACの研究環境を活用して上記内容を進める。 |
研究代表者:樋口摩彌 同志社大学・嘱託講師
研究分担者:金子貴昭 |
| 28 |
ARCリサーチスペースを活用した板木デジタルアーカイブ拡充と近世出版の総合的研究基盤の構築
Expansion of the Woodblock Digital Archive using the ARC Research Space and construction of a comprehensive research infrastructure for Japanese early modern publishing |
| 日本の近世は、文学・思想・宗教・絵画・学問など、あらゆる分野のコンテンツが出版の俎上に乗った時代であり、それらを研究するにあたり、近世出版研究の視点は不可欠である。その研究においては、板本が重視されてきた一方、本を印刷する道具であり、また版権の所在を明示する根本装置であった板木が十分に顧みられることはなかった。本研究は、板木資料の研究利用を促進することを目的に、現存する板木を調査し、板木デジタルアーカイブを拡充する。また、板木とそれに対応する板本・出版記録を総合的に検討し、近世出版における板木の役割を考察することにより、近世出版機構の実態解明に取り組む。これら諸資料のデジタルアーカイブ活動により、近世出版デジタル研究環境の構築を目指す。 |
研究代表者:金子貴昭 京都先端科学大学・准教授
研究分担者:金子貴昭 |