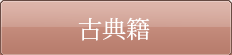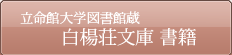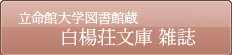D00 嵯峨・嵐山
嵐山が桜で有名になったのは、鎌倉時代前期の後嵯峨院のころ、この地に「亀山殿」と称した離宮が造営されてからのことである。造営時に、大和国の吉野山から桜を嵐山に移し替えて、秋の紅葉、夏の納涼、春の桜といった四季を通じて楽しめる地域となっていた。
今日の京都観光のなかでも人気の「保津川下り」の様子が描かれており、船の上から桜を見物する、現在と変わらない人々の様子を見ることができる。
また、嵯峨野の北部に位置し、背後に遍照寺山を置いた洛西屈指の大池である、広沢池を描いた風景画がある。広沢池のほとりにある遍照寺は、寺としてよりも観月の景勝地として有名になり、池に臨んで夜もすがら酒盃を酌み交わすところとなっていた。
- リンク
- 最近更新された記事
- はじめに
- はじめに
- 01 おとみ 与三郎
- 02 お染 久松
- 03 小町 業平
- 04 権八 小紫
- 05 小さん 金五郎
- 06 浦里 時次郎
- 07 梅川 忠兵衛
- 08 小万 源五兵衛
- 09 おかる 勘平
- 10 宗貞 小町姫
- 11 浄瑠璃御前 牛若丸
- 12 雛鳥 久我之助
- 13 朝顔 阿曽次郎
- 14 粟餅きな蔵 四つ紅葉のお滝
- 桜井コレクションについて
- 01 野郎虫
- 藤井永観文庫
- C01 東海道 京都之内 大内能上覧図
- D00 嵯峨・嵐山
- C00 御所
- B00 衣笠キャンパス周辺
- B01 都百景 御室
- B03 都百景 洛北金閣寺
- B02 都百景 洛西竜安寺
- B04 都百景 北野天満宮
- B05 滑稽都名所 平野
- B06 京都名所之内 金閣寺
- B07 京都北野天満宮 一万燈会之図 廻廊・手水屋