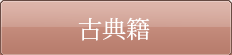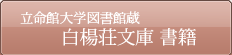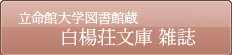上賀茂・下賀茂
上下賀茂社の葵祭と競馬は江戸時代に人気のあった年中行事であった。競馬が行われる5月5日当日は、上賀茂社の境内に設けられた桟敷に、都の人々が機先を問わず群集した。社伝では平安時代末の寛治7年(1093)以来の歴史を持ち、乗りこなしの難しい荒馬を用いて行うスリリングな勝負に人々は魅せられ、多くの見物を集める年中行事のひとつになっていた。
また、京都で祭と言えば、葵祭のことであった。幾度かの中断期をはさみ、再興したのは江戸時代の元禄7年(1694)年、5代将軍徳川綱吉の時である。現在、葵祭りは、祇園祭、時代祭とともに、京都三大祭に数えられている。 葵祭りは、もともとは賀茂祭とよばれ、上賀茂社・下鴨社の両社で行われてきた。葵祭のシンボルとして神前や参列者を飾った葵にちなんで、江戸時代に付けられた俗称である。元禄期にそれまで途絶えていた祭が復興されたのも、徳川の家紋が葵であったことが、江戸幕府の計らいがあったではないかと言われている。行列は、およそ一カ月つづく祭の行事の中心で、天皇の勅使が神へ贈り物をするためのものである。奉幣使、近衛使、楽人など華麗な装束に彩られた行列が、御所を出て都大路を東へ、そして、上下賀茂社に向かう。その姿を一目見ようと、物見高い都の人々が沿道を埋めて集まった。
- リンク
- 最近更新された記事
- はじめに
- はじめに
- 01 おとみ 与三郎
- 02 お染 久松
- 03 小町 業平
- 04 権八 小紫
- 05 小さん 金五郎
- 06 浦里 時次郎
- 07 梅川 忠兵衛
- 08 小万 源五兵衛
- 09 おかる 勘平
- 10 宗貞 小町姫
- 11 浄瑠璃御前 牛若丸
- 12 雛鳥 久我之助
- 13 朝顔 阿曽次郎
- 14 粟餅きな蔵 四つ紅葉のお滝
- 桜井コレクションについて
- 01 野郎虫
- 藤井永観文庫
- C01 東海道 京都之内 大内能上覧図
- D00 嵯峨・嵐山
- C00 御所
- B00 衣笠キャンパス周辺
- B01 都百景 御室
- B03 都百景 洛北金閣寺
- B02 都百景 洛西竜安寺
- B04 都百景 北野天満宮
- B05 滑稽都名所 平野
- B06 京都名所之内 金閣寺
- B07 京都北野天満宮 一万燈会之図 廻廊・手水屋