- 日本文化研究班
2009年1月12日
芸術・研究活動における学術ポータルサイトの現状報告
昨年12月9日に行ったGCOEセミナーの報告をまとめました。
【要 旨】
1.齊藤ちせ「日本文化・芸術研究における学術ポータルサイトの現状分析 -Webで提供されている研究ツールとして-」
2008年現在、すでに多くの大学、文化機関等が研究成果やデジタルアーカイブ資料をWeb上で公開・提供している。
本発表では、これらWebに散在する膨大な学術データベースなどの一元検索を可能にする有益な研究支援ツールとして、国内外のポータルサイト実例を何点か 取り上げる。また、それに関連し、特に北米や欧州で推進されている国境や所蔵機関のジャンルを超えた芸術文化資源共有化の動きについても報告する。
現在多くの研究成果やデジタルアーカイブ資料がWeb上で公開・提供されています。
しかし目的資料は膨大且つ雑多な情報に埋もれて検索が容易ではありません。
検索エンジンを使用しても全ての必要情報がヒットするわけではなく、何度も検索を繰り返すといった無駄を省きポータルサイトを利用することで利用者は求めている資料の所在情報等を一括で入手でき、所要の資料に簡易かつ迅速に到達できます。
ここではポータルサイトを「様々なコンテンツを有する巨大なサイト」とし、基本的にはリファレンスとファクトデータベースへの入口であると定義し、対象は図書や物等のオブジェクトとします。オブジェクトの近年の傾向として、レファレンスに画像がついたり、ファクトデータが二次的な情報を持ったり、デジタルアーカイビングすることによりその境があいまいになってきたという特徴があります。
日本でも国が先導して構築したいくつかのポータルサイトが存在します。
1.PORTA(リファレンスデータベース):国立国会図書館および資料提携機関のデジタル資料検索が可能。
2.文化遺産オンライン(ファクトデータベース):日本の文化遺産のWeb上での総覧。
3.研究資源共有化システム(ファクト+リファレンスデータ): 人間文化研究機構を構成する5機関のデータベースを横断的に検索。
日本以外では北米で世界を先導する動きがあり、例えばOCLC(Online Computer Library Center) のプロジェクトとして、
1.WorldCat(リファレンスデータベース総合的)
2.ArchiveGrid(歴史的資料に特化したリファレンスデータベース)
欧州ではEU連合の情報政策の一環として昨年欧州を網羅する文化遺産ポータルサイトのプロトタイプが立ち上がっています。
1.Europeana(ファクト+リファレンスデータ):欧州文化遺産のマルチメディア図書館のプロトタイプ。
2.MICHAEL-Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe(ファクトデータベース):
Europeana(欧州デジタル図書館)のための欧州芸術文化遺産目録ポータル。
3.TEL The European Library (リファレンスデータベース):EU諸国の国立図書館を横断する集合リソースを検索可能。
現在分散して蓄積されたデジタルアーカイブを今後どのように一括的に利活用していくのかということを考える段階に入ってきており、それは大規模なポータルサイトが次々と構築されていることからも明らかです。
勿論ここで挙げたものはすべてではなくほかにもポータルサイトは無数存在すると考えられますが、ここまで見てきていくつか気づいた点があります。
興味深い点は、北米では1960年代、欧米では1980年代末頃から、美術研究や教育、産業への活用も視野に入れた美術館、博物館、文書館、図書館のネットワーク形成の動きがあり、それは所蔵作品やリファレンスデータのデジタルアーカイブ化が前提となっていることです。
デジタルアーカイブされることにより機関の機能・性格・空間の差を越えた文化資源共有化が実現に向かっているのです。
もう一つ興味深い点は現在のこのジャンル、国境を越えたデータベース連携の動きはライブラリー(図書館)関連の機関が主導しており、そのサイトもソースデータベースを扱うものと比較して大規模で数も多いという点です。
ライブラリ関連の資料は出版物、書誌などであるため、基本情報はほぼ同じであり、標準フォーマットが作成しやすい。一方、博物館美術館の収蔵作品の形態・種類は多様でしかも書籍と異なり、唯一無比の「もの」を取り扱うため、例えば共通のメタデータの標準を決めることは困難であるためということも一つの要因であると考えられます。
膨大な量の文化遺産のデジタル化の問題。例えばEuropeanaのように200万件、1000万点を超えるアイテムを公開している大規模なポータルすら、全体のわずか1%のファクトデータがデジタル化されている状態であることや世界で見られる様々な標準化の動きなどを見ると現在は未だ過渡期であると考えられます。
現時点では北米や欧州を中心とした動きが主導していますが、将来は異なる文化や文字形態を持つ日本やアジア諸国の議論への活発な参加が期待されます。v
以上に見たように欧米を中心に各国で自国の文化遺産や文化財をデジタルアーカイビングしデータベース構築のプロジェクトが文化遺産ポータル等のプロジェクトの一環として進められていますが、自国に収蔵されているそれ以外の文化に属する美術品、例えば海外に流出した日本美術品に関しては予算も付けられずほとんど関心がはらわれていないのが実際です。
そのため、在外日本美術品(文化に関する資料)を積極的にデジタル化する、あるいは正確な資料の情報を整理する本拠点のデジタルアーカイビングの活動の意義の大きさを改めて実感しました。
RA 齊藤ちせ
参照リンク:日本文化芸術資料公開サイト
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 芸術・研究活動における学術ポータルサイトの現状報告
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/1506
コメントする

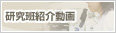
- 最近のエントリー
- 第二回西川祐信研究会
- 第八回近世視覚文化を読み解く研究会
- 板本・板木をめぐる研究集会
- 第一回西川祐信研究会の開催
- INKE Research Foundations for Understanding Books and Reading in a Digital Age: Text and Beyond
- アーカイブ
- 2012年8月 [1]
- 2012年2月 [2]
- 2011年12月 [1]
- 2011年11月 [2]
- 2011年10月 [3]
- 2011年9月 [1]
- 2011年8月 [4]
- 2011年7月 [4]
- 2011年6月 [5]
- 2011年5月 [6]
- 2011年4月 [4]
- 2011年3月 [4]
- 2011年1月 [1]
- 2010年12月 [3]
- 2010年11月 [3]
- 2010年10月 [4]
- 2010年9月 [5]
- 2010年8月 [3]
- 2010年7月 [6]
- 2010年6月 [6]
- 2010年5月 [4]
- 2010年4月 [6]
- 2010年3月 [9]
- 2010年2月 [6]
- 2010年1月 [2]
- 2009年12月 [7]
- 2009年11月 [6]
- 2009年10月 [5]
- 2009年9月 [6]
- 2009年8月 [4]
- 2009年7月 [7]
- 2009年6月 [5]
- 2009年5月 [3]
- 2009年4月 [17]
- 2009年3月 [6]
- 2009年2月 [1]
- 2009年1月 [1]
- 2008年12月 [5]
- 2008年11月 [1]
- 2008年10月 [4]
- 2008年9月 [3]
- 2008年8月 [4]
- 2008年7月 [2]
- 2008年5月 [5]
- 2008年4月 [7]
- 2008年3月 [1]
- 2008年2月 [1]
- 2007年12月 [2]
- 2007年11月 [4]
- 2007年10月 [2]
- 2007年9月 [1]
- 2007年8月 [5]