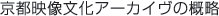
洛西撮影所街の形成につれて映画が新たな地場産業として定着した京都は、映画創出の場であるだけでなく、日本で初めて映画が映写され/によって映された都市でもある。稲畑勝太郎のシネマトグラフとともに来日したリュミエール社カメラマンのコンスタン・ジレルによって撮影された『家族の食事』などを筆頭に、京都は、いわゆる近代的視線を自らのうちに育みながら、映画を通して自らのイメージを全国・海外にむけて発信した都市といえる。
 本プロジェクトは、このような京都映画文化の生成過程と受容様態を明らかにすることを第一の目的とし、文化遺産として地域映画文化のアーカイヴ活動を推進することを第二の目的としている。研究対象は、日本映画の父と称される牧野省三のマキノ映画から、黒澤明の『羅生門』や溝口健二の作品を生みだした大映京都撮影所までを中心に据えており、プロジェクトの具体的な活動は以下、三つに大別される。
一つ目が研究基盤となる資料の収集と調査であり、この部門は地域連携の研究・教育の柱となっている。具体的には、フィルム(図1参照)や映画人所蔵の資料といったノン・フィルム・マテリアルは勿論、京都映画史に関わった京都在住映画人の制作談を中心としたオーラル・ヒストリーや、ロケーション情報の収集と記録映像化(図2参照)にも力を入れている。
本プロジェクトは、このような京都映画文化の生成過程と受容様態を明らかにすることを第一の目的とし、文化遺産として地域映画文化のアーカイヴ活動を推進することを第二の目的としている。研究対象は、日本映画の父と称される牧野省三のマキノ映画から、黒澤明の『羅生門』や溝口健二の作品を生みだした大映京都撮影所までを中心に据えており、プロジェクトの具体的な活動は以下、三つに大別される。
一つ目が研究基盤となる資料の収集と調査であり、この部門は地域連携の研究・教育の柱となっている。具体的には、フィルム(図1参照)や映画人所蔵の資料といったノン・フィルム・マテリアルは勿論、京都映画史に関わった京都在住映画人の制作談を中心としたオーラル・ヒストリーや、ロケーション情報の収集と記録映像化(図2参照)にも力を入れている。
二つ目は、収蔵庫と連携したオリジナル資料の保存であり、カタロギング後に、閲覧利用や普及用のデジタル画像を作成し、アート・リサーチセンターの収蔵庫でマテリアル別に保存している。
三つ目は研究成果の公開であり、デジタル・データはwebやビデオ、DVD、オリジナル資料は展覧会や上映会、講演会、シンポジウムなどで公開している。展覧会では、京都府京都文化博物館の開館15周年記念特別展『KYOTO映像フェスタ』(2003年)や、東京国立近代美術館フィルムセンターによる尾上松之助生誕130年記念展覧会『尾上松之助と時代劇スターの系譜』(2005年)、シンポジウムでは『映画文化の振興と保存 ―地域アーカイヴの試み―』(2003年)や、『よみがえる日本映画――映画復元の現在、フィルムとデジタルの融合』(2005年)、『よみがえる映画「三朝小唄」の記憶 ―地域文化と映画―』(2006年)などがあり、いずれも産官学連携の共同研究の成果として発表している。
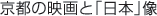
これらの活動をとおして明らかになったことは、個々の作品や撮影所の具体的な様相に加えて、マキノ映画から大映にいたる京都撮影所制作の映画が、ポジ/ネガ像の「日本」像を国内/国外にむけて形成していった、イメージ研究としての面白さである。
たとえば、マキノ映画の『三朝小唄』(1929年)や『祇園小唄 絵日傘 舞ひの袖』(1930年)においては、近代的文明の欠落による地方の危機という視点と、都会と地方という相対化意識が導入されており、都会からの男性キャラクターと、物語の舞台となる地方の女性を鉄道で結び、帝都・東京への中心化を促す文化装置の様相を顕わにしているのである。また、これらの映画内で創造された都市・京都像は、東京のあわせ鏡として東京からの/に対する視線を内包した、都市の性格をも顕わにしている。
 一方で、同時代の欧米向け映画『武士道』(1925年)に目を向けると、欧米側の欲求に応える、すなわち近代的文明の欠落した異文化としての自文化を演出する日本=京都のセルフ・イメージが見て取れるのである。 一方で、同時代の欧米向け映画『武士道』(1925年)に目を向けると、欧米側の欲求に応える、すなわち近代的文明の欠落した異文化としての自文化を演出する日本=京都のセルフ・イメージが見て取れるのである。
本稿では、このような点について、大正期の先駆的な合同映画『武士道』の背景とともに、ジャポニスムから連なる「日本」像を、日本映画が積極的に取り入れていったその様相について報告をし、今後の研究課題への足がかりとしたい。 |