
本サブ・プロジェクトでは、藤井永観文庫に所蔵される20数点に及ぶ宸翰を中心的な素材として用い、研究活動を行ってきたが、その所蔵品のなかに、国の重要文化財に指定されている「法華経要文和歌懐紙」(1巻)がある。「法華経要文」とは、法華経各品の大切な文章のことで、それに因んだ法楽の和歌を詠んだものが本懐紙である。「法華経要文和歌懐紙」と称されるものは、藤井永観文庫本のほか、妙満寺本・常照皇寺本・中村記念美術館本などが知られているが、藤井永観文庫本は、光厳天皇をはじめとして、広義門院・徽安門院・尊円親王など19名、23枚の懐紙が一巻とされたもので、1354年ころに作成されたものと推定されている。この懐紙については、1979年に発表された岩佐美代子氏による和歌史からの研究があるが、その巻物の冒頭に、光厳天皇の「和歌懐紙」がある。この光厳天皇和歌懐紙を事例の一つとして、伝承がもつあやうさについて、ふれておくことにしよう。
京都の大徳寺に、後醍醐天皇賛との伝承をもつ重要文化財「大燈国師像」がある。この後醍醐天皇賛については、明治以来、後醍醐天皇自筆のものであるのかどうか、意見の分かれるところであったが、昭和18年(1943)、赤松俊秀氏によって後醍醐説が否定され、明確に光厳天皇筆であることが主張された(「光厳天皇宸翰に就いてー大徳寺蔵伝後醍醐天皇宸賛大燈国師像の研究ー」『清閑』15冊)。赤松氏の判断となったのは、まずは書風であったが、光厳天皇宸翰の現存が少ないこともあり、赤松氏は妙満寺本「法華経要文和歌懐紙」など、少ない他の宸翰も参照しながら、慎重に考証を行い、以上のように結論づけたのである。しかし1985年4月に京都国立博物館で開催された特別展「大徳寺の名宝」では依然として後醍醐天皇賛説がとられている(同展覧会図録)、といった具合で、どの天皇の書と確定するのかは容易なことではない。
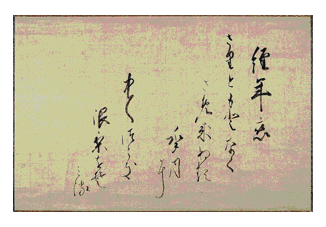 藤井永観文庫所蔵品においても、伝来に混乱がみられるものが何点かある。例えば「伝後宇多天皇宸翰仮名消息」は、それを納める外箱・内箱に、後宇多天皇とともに伏見天皇宸翰との貼紙があったり、また「後花園天皇宸翰女房奉書」を納める箱裏には、後土御門天皇の墨書があるが、一方、中蓋には後花園天皇宸翰とある。こちらの場合は内容からいって後土御門天皇ではありえなく、さらにその後土御門天皇宸翰女房奉書は、後柏原天皇筆と伝えられていたが、それも書風、書かれた内容から、後土御門天皇と判断せざるをえない、といった具合である。 藤井永観文庫所蔵品においても、伝来に混乱がみられるものが何点かある。例えば「伝後宇多天皇宸翰仮名消息」は、それを納める外箱・内箱に、後宇多天皇とともに伏見天皇宸翰との貼紙があったり、また「後花園天皇宸翰女房奉書」を納める箱裏には、後土御門天皇の墨書があるが、一方、中蓋には後花園天皇宸翰とある。こちらの場合は内容からいって後土御門天皇ではありえなく、さらにその後土御門天皇宸翰女房奉書は、後柏原天皇筆と伝えられていたが、それも書風、書かれた内容から、後土御門天皇と判断せざるをえない、といった具合である。
こうした伝承の混乱がなぜおこなったのか、その理由については先述したが、天皇の書風が比較的似通ったものであったことが、もう一つの原因として指摘できる。それが鎌倉時代後半から形づくられる宸翰様と、それを継承したその後の天皇の書、具体的には、15世紀半ばの後花園天皇当りから新たな書風が加味されていくといわれる書風である。宸翰様とその後の書風について、結論めいたことだけをここで指摘しておけば、それはけっして、代々の天皇によって、忠実に受け継がれていったものではなかったということだろう。ただ、父や祖父、あるいは曾祖父の書風を継承することはありうるし、現に、そうした形で、2、3代にわたり同系統の書風が継承されている例がみられる。後花園天皇・後土御門天皇・後柏原天皇や(図1、2参照)、江戸時代初期の後水尾天皇の書風と後西天皇・霊元天皇のそれが、きわめて近い書風であることなどが、そういった事例である。そのことを窺わせる史料として、京都御所東山御文庫に正親町天皇が孫の後陽成天皇に天皇としてのあるべき心構えを説いて与えたといわれる、「宸筆御覚書」(『宸翰英華』454号)がある。10カ条からなるその第一条に、
御手みまいらせ候へば、うつゝなき御てぶりにて候、たゞ勅筆(様)やうをあそばされ候べく候、陽光院へまいらせ候(唐)からのよりかゝりに、後柏原院みな/\のあそばされ候御てほんども御入候、よく/\それをならはせられ候べく候、
と、正親町天皇が陽光院(正親町天皇子、後陽成天皇父)や後柏原天皇の書を勉強するように指示している。一定期間、おそらくこうした形で、書風が受け継がれていったことは指摘できる。
しかし一方では、後陽成天皇と子の後水尾天皇の書風はまったく異なる。異なるという以上に、両者の書風は対極にあるといってよかろう。豪壮な後陽成天皇の書風に対し、繊細な後水尾天皇の書風、なのである(図3、4参照)。そこには、父後陽成天皇とけっして和解することのなかった後水尾天皇の、なんらかの思いがあったの
かどうかについては、いまとなってはわからない。事実として両者の書風の相違を指摘し、例え天皇の書といえども、一つの型に定まった書風のみを継承するものではなかったことを確認しておくにとどめたい。

さて、いま話題としてきた財団法人藤井永観文庫は、2005年8月をもって財団の解散手続きがすべて終了し、所蔵品約420点は、立命館大学に寄贈された。これは「京都アート・エンタテインメント創成研究」の活動が、社会的にも評価された結果であると考えているが、同時に立命館大学は、文庫の資料研究と社会への還元だけではなく、これらをできる限り現状の姿を守って後世に伝えることなど、社会的な大きな責務も合わせて果たしていかなければならない。
サブ・プロジェクト「Calligraphy and Court Culture in Premodern Japan」では、これまで藤井永観文庫所蔵品のなかの宸翰や古筆について、一点一点、以上に述べてきたような検討を積み重ねてきた。まだ残されている課題も多いが、ともかくその成果を2005年12月1日よりアート・リサーチセンターにおいて展示することにした。テーマは「天皇の詩歌と消息ー宸翰にみる書式ー」。展示される宸翰は鎌倉時代後半の後深草天皇以後、幕末の孝明天皇まで、21名の天皇と28点の宸翰である。
また本サブ・プロジェクトでは、以上のような研究活動とともに、藤井永観文庫所蔵品のデジタル・アーカイブを行っているが、その作業のなかで資料を文字単位で分割し分析するシステムの構築も検討しており、展示では、その成果の一端も示すことができれば、とも考えている。そしてそれを含めて、以上に述べた展示内容については、図録の発行とホーム・ページによって公表すべく、現在その準備をすすめている。
|