|
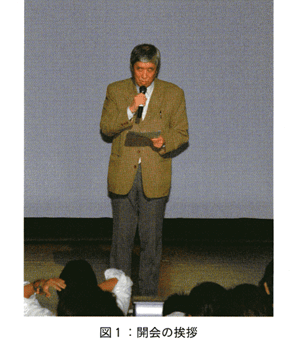

このたび立命館大学では、21世紀COEプログラム「京都アート・エンタテインメント創成研究」の一環として、日本学術会議芸術学研究連絡委員会との共催による、パフォーマンスとシンポジウム「表象芸術2003 ―アジアの歌と舞い―」を企画した。
本学の「京都アート・エンタテインメント創成研究」の重要な特徴は文理融合型の総合研究であることにある。この研究を展開するにあたって、その中核をな
してきた本学の重要な研究機関のひとつがアート・リサーチセンターである。この研究センターは、開設以来、最新のAV機器を駆使して、京都の伝統芸能であ
る、能狂言、あるいは井上流の京舞などをデジタル・アーカイヴ化して保存記録するという仕事と取り組んできた実績がある。

今年は出雲阿国が鴨河原で歌舞伎興行を行ってから四百年にあたる。いうまでもなく歌舞伎もまた上方で生まれた日本を代表する芸能であるが、関西での歌舞伎
興行はかつての勢いはもはやない。今回のイヴェントは歌舞伎四百年にちなんで、この歌舞伎を京都の伝統芸能との歴史的な関わりから眺め、さらにこの京都に
象徴される日本、そこからアジアへというコンテクストの中で、理論と実践をからめた具体的な視点から検証しようとした試みである。
つまりこのイヴェントは、京都という研究の枠組みから、さらにアジア的美意識の基層性の研究へと一歩深まることにより、国際的な広がりを持つ催しとなっ た。そのための国際協力、あるいは情報の発信の役割を担ったのが、アート・リサーチセンターに本部を置く「アジア芸術学会 The Asian Society of Art」である。この国際学会は、2001年に千葉県幕張で開催された「第十五回国際美学会議」の後、立命館大学で開催された「アフター・コングレス・シ ンポジウム・芸術のアジア ―外からの眼差しと内からの応え―」を第一回大会として位置づけることによって結成されたものである。2002年度大会は韓国 の釜山で開かれ、2003年度大会は台北で催される予定であったが、SARSの影響で明春に延期となっている。
今回の企画のもう一つの狙いとしてあったのは、言語を越えたより根元的な身体表現としての舞踊とは何かを、研究者たちだけの学術研究に留めるのではな
く、公開シンポジウムという形式で広く市民にデモンストレーションし、このパフォーミング・アート、あるいは表象芸術としての舞踊についての理解を深めて
もらおうというものであった。このパフォーマンスに積極的に協力していただいたのが、日本学術会議第一部芸術学研究連絡委員会に所属する「舞踊学会」と
「比較舞踊学会」である。この理論と実践を組み合わせた研究会は、過去にも例がなく、その成果は特筆に価するものであったと言うことが出来る。
ちなみに「比較舞踊学会」からの演目をそれぞれプログラミングしてくださったのは、石黒節子お茶の水大学教授と国枝タカ コ茨城大学講師である。
ちなみに「舞踊学会」そして「比較舞踊学会」からの演目をそれぞれプログラミングして下さったのは、石黒節子お茶の水女子大学教授と國枝タカ子茨城大学講師である。
|
 |
|
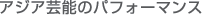
第一日目のパフォーマンスの司会進行は、立命館大学の仲間裕子教授が担当した。第一部では、日本の各地に伝播し、今日なおその面影を残す踊り、あるいは
その源流をたどりつつ演じられた舞いから、われわれは阿国歌舞伎や若衆歌舞伎の踊りのかつてのイメージを、生き生きと眼前に思い浮かべることが出来た。引
き続いて上方舞(葛タカ女氏)と志賀山流の歌舞伎踊り(志賀山葵氏)が披露された。流れるように優婉な上方舞いと江戸の粋を体現しためりはりのきいた江戸
の歌舞伎踊りという東西の舞いを、同じ舞台で比較鑑賞出来る機会など滅多にあるものではない。第二部のテーマは、近代において「芸能」から「芸術」へと変
化した舞踊、あるいは舞踏表現(平松み紀氏)と、この本来は西欧的なアートに伝統的な日本的身体表現を融合することの可能性(石黒節子氏他)が、前衛的な
実験的手法で問われた。
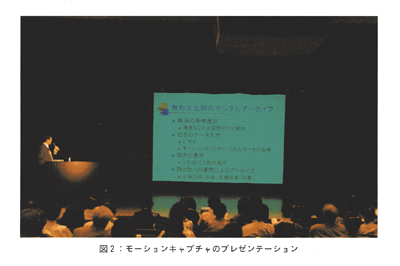 第三部では、アジアの各国から招待した一流の舞踊家と歌手によって、インドネシア(芸能山城組)、中国(袁英明氏)、そして韓国の歌舞(金貞愛氏、李知垠 氏他)が、解説付で上演、披露された。ここにいたって観客は、京都、日本、そしてアジアの芸術を貫く美意識というものの存在を、間違いなく確信したはずで ある。このきらびやかな舞台は、およそ四時間半にわたる長丁場であったにもかかわらず、だれ一人として席を立つ者がいない、熱気に満ちたものであった。上 演の半ばで、立命館大学の八村廣三郎教授によって、いま多くの舞踊関係者の注目を集めている、アート・リサーチセンターでのモーション・キャプチャによる 計測が、具体的にどのような成果を挙げているかについてのプレゼンテーションが行われた。なお当日のパフォーマンスは、それぞれに許可を得られたものに限 り、今後の貴重な研究資料としてデジタル・アーカイヴ化されて本センターに保存されることとなった。
第三部では、アジアの各国から招待した一流の舞踊家と歌手によって、インドネシア(芸能山城組)、中国(袁英明氏)、そして韓国の歌舞(金貞愛氏、李知垠 氏他)が、解説付で上演、披露された。ここにいたって観客は、京都、日本、そしてアジアの芸術を貫く美意識というものの存在を、間違いなく確信したはずで ある。このきらびやかな舞台は、およそ四時間半にわたる長丁場であったにもかかわらず、だれ一人として席を立つ者がいない、熱気に満ちたものであった。上 演の半ばで、立命館大学の八村廣三郎教授によって、いま多くの舞踊関係者の注目を集めている、アート・リサーチセンターでのモーション・キャプチャによる 計測が、具体的にどのような成果を挙げているかについてのプレゼンテーションが行われた。なお当日のパフォーマンスは、それぞれに許可を得られたものに限 り、今後の貴重な研究資料としてデジタル・アーカイヴ化されて本センターに保存されることとなった。 |
 |
|

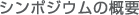
第二日目のシンポジウムは、立命館大学の川嶋將生教授による基調講演「四条河原の歴史的環境」から始まった。芸能興業地としての四条河原がどのようにして成立していったか、そしてその歴史的な変遷について、川嶋教授は綿密な資料分析を通じて興味深く語られた。
シンポジウムは「アジアの歌と舞い」というテーマをめぐって、日本学術会議登録の芸術学研究諸学会からの6名のパネリストによる発表が行われた。司会進
行は、大阪大学大学院の上倉庸敬教授(美学会)が担当した。最初に樋口聡広島大学助教授(美学会)によって、「東洋的身体論」と題する報告がなされた。近
代日本の哲学の中で、西欧の心身二元論に対して、仏教的な「修行」の考え方に着目して身体と心の在り方を一体不可分なものとして論じたのが湯浅泰雄であ
る。日本の文学や芸能における「型」の問題は、こうした身体観に帰着するというのが湯浅の主張である。近年、この修行の考え方に「哲学の実践」という視点
から、東洋思想と西欧のプラグマティズムに相通じるものが存在すると主張しているのが、リチャード・シュスターマンであり、樋口助教授は、その身体感性論
(Somaesthetics)に、東洋的身体表現の何たるかを理解するための可能性が見出せるのではないかと述べた。
続いて岸文和同志社大学教授(美術史学会)による「風俗画に見る歌舞伎」という報告があった。この報告の趣旨は、江戸の人々にとって最大の楽しみであっ
た歌舞伎と役者絵の関係、そしてこの役者絵が果たしていたコミュニケーション機能の多様性を明らかにしようとしたものである。たとえば新春を賀すシンボル
的なメディアとして、また役者のイメージを理想化する一方で、その個性を暴露的に誇張して表現し、これによって贔屓の欲望に働きかけ観劇へと誘うメディア
として作用していた等々。豊富な文献と映像を駆使して、当時の歌舞伎興行と観衆を媒介するメディアとしての役者絵の役割が、軽妙な語り口で見事に分析され
た。
 小池三枝お茶の水女子大学名誉教授(服飾美学会)は、「歌舞伎と装い」をテーマとして、歌舞伎という言葉が本来もつ「異相」の表現に着目して、これが現実 を超えた美を表現するためのものであったことを述べ、さらにもうひとつの異相として、坂田藤十郎の「装いの虚実」に言及した。そこには「虚実皮膜の間にあ り」という近松門左衛門の主張が、服飾美学の視点からする美的表現として示されているのである。 小池三枝お茶の水女子大学名誉教授(服飾美学会)は、「歌舞伎と装い」をテーマとして、歌舞伎という言葉が本来もつ「異相」の表現に着目して、これが現実 を超えた美を表現するためのものであったことを述べ、さらにもうひとつの異相として、坂田藤十郎の「装いの虚実」に言及した。そこには「虚実皮膜の間にあ り」という近松門左衛門の主張が、服飾美学の視点からする美的表現として示されているのである。
「舞踊と音楽」の関わりについて、山口修大阪大学名誉教授(東洋音楽学会)は、アジアおよびオセアニアの「表演芸術(performing
arts)」を実例として、①表演の場、②表演の時、③表演の儀礼性、④表演の身体性という観点から、舞踊と音楽の関係について、豊富なフィールドワーク
の経験に基づけて、その相補性、相互依存性、排他性について論じた。この報告によって、シンポジウムの論点は日本からアジアへと押し広げられることとなっ
た。
吉川周平京都市立芸術大学教授(舞踊学会)の報告は、「舞踊表現の東西」をとくに「かぶき<オドリ>を考える」という視点から論じたものであった。この
発表は、とくに郡司正勝の歌舞伎と舞踊の研究をベースとして、そこから「オドリ」としての特質を抽出して、これに新たな照明を当ててみようという試みで
あった。
シンポジウムの個別報告の最後は、森下はるみお茶の水女子大学名誉教授(比較舞踊学会)による「舞踊における身体づかいの東西」という発表であった。舞
踊家としての実践的な体験をふまえての今回の報告は、きわめて具体的で説得力に富むものであった。舞踊における東西の身体づかいの両極として、報告者は西
のバレエに対して、東の能・歌舞伎舞踊などの日本の伝統芸能を実例としてあげて、①体つき、②歩行、③回転・跳躍、④運動強度という観点から比較検討を
行った。そこから引き出されてきた結論は、西の舞踊表現においては、運動強度大で短時間の見せ場を作る、東の舞踊表現においては、運動強度は軽・中程度で
時間大というものであった。問題はなぜこのような身体づかいの差が生じてくるかということであり、この問題は宗教・風土・美意識などに起因するところが大
きいのではないかという問題提起がなされ、これがシンポジウムの後半の議論の話題を提供することとなった。
会場を交えての討論で興味深かったのは、身体表現の問題を論ずる以前に、現在の学校教育における、とくに体育という教科科目における身体づかいが、再考 されるべきひとつの重要な問題として浮かび上がってきたことである。また前日のパフォーマンスとからめての意見なども出されて活発な質疑応答が交わされ た。しかし、今回のシンポジウムによって、ただちに何らかの結論が導き出されたわけではない。だが立命館大学を場として、ようやく身体表現をめぐって、西 欧近代の芸術観に対置する東洋の新たな芸術観の構築のための、ジャンルを越えたコンセンサスを得ることが出来たのは確かであろう。

二日間にわたって行われた今回のパフォーマンスとシンポジウムの出席者数は、延べ700名を越え、このビッグ・イヴェントを成功裡に終えることが出来たと信ずる。
|
 |