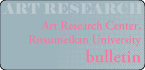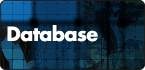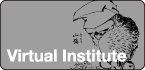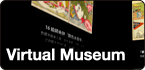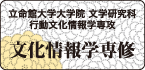| No. | Title / Affiliation / Name |
|---|
| 1 |
デジタル・アーカイブ手法を用いた近代染織資料の整理と活用
Organization and Utilization of Modern Printed Textile Research Materials through the Method of Digital Archiving |
| 京都女子大学・准教授 青木 美保子 |
| 本研究は、学術資料として俎上に上がっていない近代染織史に関連する資料の整理・蓄積をすすめるものである。近代染織史を研究するための資料は散在し、かつ未整理のものが大半であり、基礎的な資料調査が必要不可欠な段階にある。一方、近代の染織産業については聞き取り調査も研究手法の有効な手段であり、文献資料には残らない情報を収集することができる。そこで、本研究では、近代染織研究に必要な資料整理や調査を進めつつ、資料・情報を蓄積していく場を構築し、情報技術を駆使してその共有化を進める。この資料・情報の整理・蓄積・共有化は、染織研究関係者と染織業従事者へ新たな交流の場を提供することとなり、延いては染織業の活性化を模索する足掛かりとなるであろう。 |
|
|
| 2 |
浮世絵データベースシステムを応用した浮世絵の新研究
Applied approach using the ARC Ukiyo-e Database system |
| 立命館大学 衣笠総合研究機構・客員研究員 岩切 友里子 |
| 浮世絵専門のイメージ・データベースとして、世界を代表するものに赤間のアート・リサーチセンター浮世絵データベースとジョン・レシグのJapanese Woodblock Print Searchがある。浮世絵データベースシステム開発のキーマン二人と、浮世絵専門研究者による新たな研究データベースを開発する。本課題がイメージする研究データベースは、カタログレゾネの日常的な蓄積を可能とする応用的な展開を目指すもので、これによって、具体的にはRoger Keyes北斎カタログ(未刊行)のデータベース化を実現し、その上で、2017年度に開催される大英博物館での北斎展に結びつける。 |
|
|
| 3 |
近代京都の市街地の形成と建築様式・用途との関連性に関する研究 |
| 京都府立大学 大学院生命環境科学研究科・教授 大場 修 |
全市に及ぶ大きな戦災を免れた京都市には、市内に4万8千棟もの町家が今なお残る文1)。しかし現在の市街地は画一的な宅地開発や建築活動が進み、町家の数は確実に減少し続け、地域の特性や景観が失われつつある。地域の景観形成に資するまちづくりの方針を考える上で、今日の地域が形成された要因を歴史的・建築的に理解することが不可欠であるが、これまで、近代京都の市街地の形成過程と特に建築様式との関係性に焦点をあてた研究は少ない。本研究は、明治以降、とりわけ三大事業以降の京都の市街地の変遷過程を地域ごとに空間的に把握し、その背景となった社会経済状況、及びそうした社会活動の受け皿としての学区や地域、さらには住宅・建築様式等との関係性を総合的に把握することで、近代京都の市街地形成を史的に整理・解明する。
文1)京都市・財団法人京都市景観まちづくりセンター・立命館大学"平成20・21年度「京町家まちづくり調査」記録集"平成23年3月 |
|
|
| 4 |
近世近代期京都の地誌・案内記を対象としたデジタルアトラスの構築
Construction of a Digital Atlas of Topographic Documents and Guidebooks in the Early Modern Period and Modern Period of Kyoto |
| 徳島大学 大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部・准教授 塚本 章宏 |
| 本研究課題は、近世から近代への移行期の京都における、あらゆる職種に関する人物・住所情報が記載された地誌・案内記類のデジタルアーカイブを進め、産業の立地や集積の地理的分布とその変遷を明らかにするためのデータ基盤構築を目指すものである。これまでのデジタルアーカイブは、インターネットでの画像公開が主であったが、本研究課題では、地誌・案内記類の画像データベースと、地理情報システム(GIS)の管理・分析機能と連携させることで、オンライン上で主要産業のGIS地図と原資料を閲覧することができるデジタルアトラスを構築することを目指す。この成果によって、歴史学や地理学といった伝統的な研究分野のみにならず、デジタル・ヒューマニティーズの研究基盤、研究事例としても期待される。 |
|
|
| 5 |
東南アジアの舞踊のドキュメンテーションとデジタル・アーカイブ研究
A Study on documentation and digital archive of Southeast Asian dance |
| お茶の水女子大学基幹研究院・准教授 中村 美奈子 |
| 本研究では、文化の視点から舞踊をとらえ、文理融合的アプローチから、東南アジアの民族舞踊を対象としたデジタル・アーカイブ構築モデルを提示する。従来の舞踊アーカイブでは、映像と舞踊のスコア(舞踊譜)を同時に保存するのが一般的であるが、本研究では、立命館大学ARCのモーションキャプチャシステムを用いて取得した舞踊の三次元動作データと同大学の多視点デジタル映像収録機器を用いた映像、さらに舞踊譜という、多様なデータを含む新しいタイプの舞踊アーカイブ構築を行う。舞踊譜による記譜では、同じく立命館大学で開発された舞踊譜ラバノーテーション(Labanotation)による記譜のためのシステムLabanEditorを、バリ舞踊の記譜と動作再現に適用できるように拡張する。 |
|
|
| 6 |
浮世絵技法の復元的研究のための光計測・画像解析基盤技術の創出
Development of optical imaging and analysis methods for restoration study of ukiyo-e print |
| 京都府立医科大学 大学院医学研究科・助教 南川 丈夫 |
| 浮世絵は、江戸時代に発展した多色摺木版画であり、現在では日本を代表する伝統美術として伝えられている。しかし、浮世絵の版木は、仮に現存する場合であっても、摺り工程による摩耗等により、木版画の再現が不能なほど劣化している事が多い。また、浮世絵の伝統技法は主に直伝で受け継がれてきたため、浮世絵の製作手法や使用した材料が現在では不明であることが多い。そこで、本研究では、版木および版画を光計測・画像解析技術を駆使して科学的に分析することで、当時の浮世絵の製作手法や材料の再現による伝統技術の復元するための基盤技術の創出を目指す。本研究は、光計測、情報処理、木版研究、浮世絵研究の専門家と浮世絵職人の産学・文理融合型のチームで推進する。 |
|
|
| 7 |
演劇上演記録のデータ・ベース化と活用、ならびに汎用利用システム構築に関る研究 |
| 公益財団法人 松竹大谷図書館 武藤 祥子 |
| 松竹大谷図書館は、開館以来、演劇史や演劇資料整理の基礎となる演劇上演記録を作成してきた。この上演記録は、主に明治初年から戦前までの東京の記録と、戦後の各地の大劇場、及び東京の小劇場の記録である。これらの上演記録は、元々図書カードによって整理されていたもので、これを完全にデータベースに移行しつつ、不完全な情報については、資料の原典に当たるなど精緻化、考証を進めてデータの精度を上げ、日本演劇の研究と資料整理の基礎となる上演記録データベースを構築する。 |
|
|
| 8 |
富本憲吉とバーナード・リーチ往復書簡の研究-京都市立芸術大学所蔵資料を中心に
Research on Letters Exchanged Between Tomimoto Kenkichi and Bernard Leach: Tomimoto Kenkichi Archive in the Collection of Kyoto City University of Arts |
| 京都市立芸術大学 美術学部・准教授 森野 彰人 |
| 富本憲吉(1886-1963)は「色絵磁器」で第1回の重要無形文化財保持者に認定され、文化勲章を受章した陶芸家である。京都市立芸術大学の前身である京都市立美術大学において教授・学長も務め、20世紀を代表する多数の芸術家を育成したことでも知られている。2013年、京都市立芸術大学は富本憲吉記念館(奈良県安堵町)から富本憲吉関連資料の寄贈(940件)をうけた。本研究では、これまでに同資料中の富本と英国人陶芸家バーナード・リーチ(1887-1979)の間で交わされた書簡のデジタル画像を用い、英文資料を翻刻、画像データベースを構築した。20世紀の日本と英国を代表する陶芸家のやりとりを研究し、画像及び研究成果をデータベース上で公開することにより、日英の美術工芸史に新たな成果・手法を提示する。 |
|
|
| 9 |
Archiving and Utilization of Japanese Performing Arts Materials on GloPAD(Global Performing Arts Database)and JPARC(Japanese Performing Arts Resource Center) |
| Associate Professor, University of California at Santa Barbara Katherine SALTZMAN-LI |
| To develop the Global Performing Arts website, database (GloPAD), and Japan Resource Center (JPARC), we have focused on four projects: 1) Building a Nobumitsu Research Portal; 2) Enhancing the kabuki portal; and 3) Creating an Interactive Noh Costume Model. 4) Online Research Exchange and Repository for GloPAC Scholarship. Each project is designed to explore different possibilities that can be realized through the combined goals, efforts, and skills of the GloPAC and ARC teams. In the first six months we have prepared the groundwork, including technical infrastructure for online publishing on GloPAC and content to be uploaded as digital exhibitions and interactive modules. In addition, we embarked on reimagining the JPARC site to be more intuitive to current users. In the coming year we hope to implement these changes. |
|
|
| 10 |
中世語彙画像対照データベースの構築に関する基礎研究
A Research on the Construction of a Database on Medieval Vocabulary and Its Visual Presentation |
| カルガリー大学・教授 X. Jie YANG |
| デジタル環境の発達は、歴史や文学などの分野における古典の研究に新たな可能性と、かつてない課題をもたらした。本研究は、絵巻解読や研究の基礎環境を整えること目指し、これまで存在しなかった内容や様式の情報を作成しようとする。とりわけ同じテーマをめぐる詞書と画像という異なる表現媒体を併せ持つ絵巻の構成に着目し、中世の語彙と画像との対照を明らかにし、デジタル環境を用いる縦横に検索するリソースを研究者や絵巻の読者に提供する。 |
|
|