立命館大学アート・リサーチセンター ウェブサイト
立命館創始140年・学園創立110周年記念
アート・リサーチセンター 連続展覧会/若手研究者企画 連続講演会
展覧会スケジュール
6月
「祈祷と占い Healing and Divination ─中世日本人の信仰─」

- >会期近辺のイベントを確認する
- 会期: 2010年6月6日(日)から 2010年6月26日(土)まで
※ 土日は閉室。但し6日、26日は開室 - 開室時間: 9時30分から17時まで
- >Web展覧会を見る
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室 (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 関連企画: シンポジウム
「祈祷と占い Healing and Divination ─中世日本人の信仰─」
- 開催日: 2010年6月25日(金)、26日(土)の2日間
開催時間: 【25日】9:00から18:00まで 【26日】9:00から17:30まで - 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム
- プログラム: ※主な使用言語は英語を予定しています。
1日目 9:00 受付 10:00 展覧会鑑賞 11:00 川島 將生(立命館大学)
‘Manuscripts on healing and divination in the Fuji Eikan Archive’12:00 昼休憩 13:00 赤間 亮(立命館大学)
Opening Remarks 'Omens in the World of Theatre'14:00 Giorgio Premoselli(佛教大学)
‘Divination and ceremonies for the healing of diseases in mid-Heian Onmyôdô’14:30 Benedetta Lomi(ロンドン大学SOAS)
‘Striking dolls and casting spells: Onmyô exorcism in the Six Syllable Sutra ritual’15:00 Jane Alaszewski(ロンドン大学SOAS/佛教大学)
‘Illness on an island without doctors: Ritual approaches to healing on Aogashima’15:30 質疑応答 16:00 休憩 16:30 Kigen-San Licha(ロンドン大学SOAS)
‘Ghosts and foetuses: Divination and communal healing in Soto Zen kirigami’17:00 Elisabeth Tinsley(大谷大学)
‘Oracles, lineage formation and monastic education at medieval Koya-san’17:30 質疑応答 2日目 9:00 受付 9:30 松本 郁代(立命館大学)
Praying on the riverside: the devotional pagodas along the Kamogawa’10:00 Marco Gottardo(玉川大学)
‘Magic words and holy waters: popular divine medicine in the cult of Mt. Fuji’10:30 質疑応答 11:00 休憩 11:30 小林 奈央子(慶應義塾大学)
‘Healing and divination during the Ontake Oza'12:00 Andrea Castiglioni(コロンビア大学)
‘Sacred poems and celestial foxes: Healing rituals in the Echigo Shugen tradition’12:30 質疑応答 13:00 昼休憩 14:30 Tullio Lobetti(ロンドン大学SOAS)
‘Magical healing and divination in late medieval Europe in comparative perspective’15:00 ラウンドテーブル: Reconsidering Healing Practices in Japanese Religion.
司会: Lucia Dolce(ロンドン大学SOAS)・松本 郁代(立命館大学)17:30 閉会
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター
ロンドン大学SOAS(PMI2・研究プログラム「Healing and Divination in Japan」) - 企画: DH拠点 京都文化研究班 松本研究室
ロンドン大学SOAS ルチア・ドルチェ准教授(研究プログラム「Healing and Divination in Japan」代表責任者) - 入場料: 無料
- お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
7月このページの上部へ▲
「立命館大学アート・リサーチセンター新収蔵資料展 ―友禅下絵と乾板写真から―」

- >会期近辺のイベントを確認する
- 会期: 2010年7月12日(月)から 2010年7月27日(火)まで ※会期日程が変更になりました。
※ 土日祝は閉室 - 開室時間: 9時30分から17時まで
- >Web展覧会を見る
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室 (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 関連企画: 展示解説
担当者による展示解説
- 開催日時: 2010年7月15日(木)17時30分から18時まで ※当日のみ開室時間を延長します。
2010年7月23日(金)16時30分から17時まで - 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画: DH拠点 京都文化研究班 木立研究室
- 企画協力: 加藤政洋(立命館大学文学部 准教授)
松田有紀子(JSPS 特別研究員・立命館大学大学院 先端総合学術研究科) - 入場料: 無料
- お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
9月このページの上部へ▲
「王朝の雅 ―平安から近世へ―」

- >会期近辺のイベントを確認する
- 会期: 2010年9月29日(水)から 2010年10月22日(金)まで
※ 土日祝は閉室、但し10月2日(土)、3日(日)、9日(土)は開室 - 開室時間: 9時30分から17時まで
- >Web展覧会を見る
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室 (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 関連企画: 講演会
「王朝の雅 ―平安から近世へ―」公開記念講演会
- 開催日時: 2010年10月9日(土)13時から16時まで
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム
- プログラム(予定):
01. 『平安文学研究』創刊の頃のお話 /柿谷 雄三(相愛女子短期大学 名誉教授) 休憩(10分) 02. 平安文学研究と立命館 /中西 健治 (立命館大学文学部 教授) 質疑応答 休憩(10分) 03. 近世絵画の中の源氏物語 /赤間 亮 (立命館大学文学部教授) 質疑応答
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター
立命館大学2010年度中古文学会秋季大会開催事務局 - 共催: 中古文学会
立命館大学図書館 - 協力: 兵庫県篠山市教育委員会
京都府南丹市教育委員会 - 企画: 立命館大学2010年度中古文学会秋季大会開催事務局
DH拠点 日本文化研究班 赤間研究室 - 監修: 中西健治(立命館大学文学部 教授)
赤間亮(立命館大学文学部 教授) - 担当: 藤田さほ(立命館大学大学院文学研究科 博士課程後期課程)
本多潤子(立命館大学大学院文学研究科 博士課程後期課程)
李増先(立命館大学文学部 四年生) - 入場料: 無料
- お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
11月このページの上部へ▲
「花供養と“京都の芭蕉”」

- >会期近辺のイベントを確認する
- 会期: 2010年11月1日(月)から 2010年11月26日(金)まで
※ 土日祝は閉室。但し20日は開室 - 開室時間: 9時30分から17時まで
- >Web展覧会を見る
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室 (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 関連企画: シンポジウム
「花供養と“京都の芭蕉”」
- 開催日時: 2010年11月20日(土)13時から16時
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム
- プログラム(予定):
13:00 開会 13:05 竹内千代子(聖トマス大学 准教授)
京都の芭蕉さん ─芭蕉句碑と花供養会─13:35 松本節子(元 福井大学 教授)
花供養と京都俳壇14:05 岸本悠子(立命館大学大学院文学研究科 博士課程後期課程)
花供養の書肆 勝田善助14:35 小林 孔(大阪城南女子短期大学 教授)
芭蕉堂と花供養15:05 休憩 15:20 花供養、櫻井コレクションウェブサイトの紹介 15:35 座談会 16:00 閉会
- 関連企画: 特別公開
京都東山芭蕉堂の公開
- 公開日: 2010年11月19日(金)、11月21日(日)
- 公開時間: 10時30分から15時
- 参考: 京都観光オフィシャルサイト「京都観光Navi」 芭蕉堂(駒札)(外部サイト)
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画: 京都俳諧研究会、DH拠点 日本文化研究班 赤間研究室
- 担当: 石上阿希(DH拠点 PD)
- 入場料: 無料
- お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
12月このページの上部へ▲
「見る・読む・知る 歌舞伎と劇場」

- >会期近辺のイベントを確認する
- 会期: 2010年12月1日(水)から 2010年12月21日(火)まで
※ 土日祝は閉室 - 開室時間: 9時30分から17時まで
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室 (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 関連企画: ギャラリートーク
企画者によるギャラリートーク
- 開催日時: 2010年12月3日(金)16時から16時30分まで(予定)/担当: 倉橋正恵
2010年12月20日(月)16時から16時30分まで(予定)/担当: 加茂瑞穂 - 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画: DH拠点 日本文化研究班 赤間研究室
- 担当: 倉橋正恵(DH拠点 客員研究員)
加茂瑞穂(立命館大学大学院文学研究科 博士課程後期課程・DH拠点 RA) - 協力: 古川耕平(立命館大学映像学部 准教授・DH拠点 事業推進担当者)
金子貴昭(JSPS 特別研究員・DH拠点 PD)
石上阿希(DH拠点 PD) - 入場料: 無料
- お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
1月このページの上部へ▲
「京都の風景画と古地図」

- >会期近辺のイベントを確認する
- 会期: 2011年1月11日(火)から 2011年1月28日(金)まで
※ 土日は閉室 - >バーチャル浮世絵展示
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室 (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 関連企画: 講演会
特別講演会
- 開催日時: 2011年1月25日(火)18時から19時30分まで(予定)
- 講師: 大塚活美(京都府総合資料館 歴史資料課 主査)
井堂雅夫(版画家)
赤間 亮(立命館大学 教授、ARC センター長) - 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画: DH拠点 日本文化研究班・歴史地理情報研究班
- 担当: 塚本章宏(JSPS PD)
瀬戸寿一(JSPS DC2・DH拠点 RA) - 協力: 金子貴昭(JSPS PD)
桐村 喬(DH拠点 PD) - お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
2月このページの上部へ▲
「ビデオゲーム展―電子化された「遊び」の世界―」

- >会期近辺のイベントを確認する
- 会期: 2011年2月22日(火)から 2011年3月22日(火)まで
※ 土日は閉室 - 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧室 (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 関連企画: ギャラリートーク
ギャラリートーク:上村雅之×サイトウ・アキヒロ×尾鼻 崇
- 開催日時: 2011年3月2日(水)14時から17時まで(予定)
- 講師: 上村雅之(立命館大学大学院先端総合学術研究科教授/元任天堂株式会社開発第二部部長)
サイトウ・アキヒロ(立命館大学映像学部教授/IGプロジェクトゲームニクス研究室室長)
尾鼻 崇(DH拠点 PD・立命館大学大学院非常勤講師) - 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム
-
- 関連企画: 体験コーナー
ゲーム&ウォッチ体験コーナー
- 日時: 2011年2月23日(水)13時から17時
2011年3月2日(水)10時から13時
2011年3月9日(水)13時から17時
2011年3月16日(水)13時から17時 - 機種: 『VERMIN』(1980年)
『OCTOPUS』(1981年)
『MARIO BROS』(1983年) - 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 一階閲覧展示室
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画: DH拠点 Web活用技術研究班・上村雅之研究室
- 担当: 尾鼻崇(DH拠点 PD・立命館大学大学院非常勤講師)
- 協力: 任天堂株式会社
- 展示協力: 立命館大学映像学部上村・尾鼻ゼミ 学生有志
- お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
講演会スケジュール
6月このページの上部へ▲
「デジタル化の潮流の中で: ハーバード・イェンチン図書館の場合」

- 講師: マクヴェイ・山田・久仁子 /ハーバード燕京図書館 日本語コレクション担当司書
- >開催日近辺のイベントを確認する
- 開催日時: 2010年6月24日(木)18時から19時30分まで
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 講演会詳細
講演内容
1914年の姉崎正治、服部宇之吉両教授の寄贈図書から始まった、ハーバード燕京図書館(インチェン・ライブラリー)の日本語コレクションは現在、蔵書数30万冊を超え、米国内において、米国議会図書館、カリフォルニア大学バークレー校に次ぐ規模を有している。
また日本の貴重書コレクション(Rare Books Collection)の中には、江戸期の版本を中心に、約3900タイトル1万5000冊と、約500本の軸・巻物がある(2008年6月現在)。こうしたコレクションの全蔵書は、ハーバード大学図書館のオンライン目録(Hollis)から検索が可能である。
本講義では、燕京図書館日本語コレクション担当司書(Librarian for Japanese Collection)マクヴェイ・山田・久仁子氏を迎え、蔵書紹介、資料デジタル化の現状や、図書館の日本研究支援体制、ハーバードのオープン・アクセス・プログラムなどを紹介して頂く。マクヴェイ・山田・久仁子 プロフィール
1980年に国際基督教大学卒業後、東京駒場の日本近代文学館に7年間勤務。1987年に渡米し、ボストンで2年間の製本プログラムを履修。その後、1989年からの10年間、ハーバード大学ライシャワー日本研究所付属「現代日本研究資料センター」の運営責任者を勤める。
1995年ボストンのシモンズカレッジにて、図書館情報学修士を取得。1999年より現職。
昨年9月より、ハーバードの文理学部東アジア地域研究の修士課程に入学し、職務の傍ら日本の中世史を勉強中。
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画・担当: DH拠点 歴史地理情報研究班 塚本章宏(JSPS PD)
- 参加料: 無料
- お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
7月このページの上部へ▲
「書斎から桟敷へ――『東海道四谷怪談』のテキストとパフォーマンス」
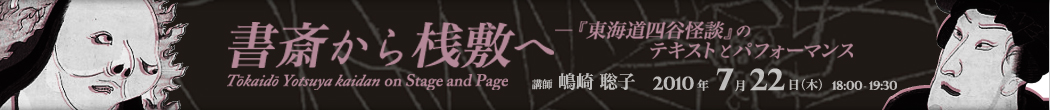
- 講師: 嶋崎聡子 /コロラド大学ボルダー校 准教授
- >開催日近辺のイベントを確認する
- 開催日時: 2010年7月22日(木)18:00から19:30まで
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 講演会詳細
講演内容
本講演では、鶴屋南北作『東海道四谷怪談』を題材にとりあげ、もともと舞台上の芸術のその上演のために存在した台帳が、20世紀初頭に読み物としてテキスト化されてゆく過程とその言説に注目し、本という媒体を通じて『四谷怪談』の解釈が変遷してゆくことを指摘する。
また、以上の論がアメリカにおける日本演劇研究のフレームワークを基盤として書かれたことをふまえ、日本国内における研究成果との視点の相違を述べることによって、欧米における日本演劇研究の位置づけを明らかにする。
その背景となる大学のカリキュラムの特色や、アメリカの日本学研究に何が必要とされてきたのかを、実際の教育現場における事例を紹介しながら考えていく。嶋崎聡子 プロフィール
2009年にコロンビア大学東アジア言語文化学部より日本文学の博士号取得。
現在はコロラド大学ボルダー校、アジア言語文化学部にて日本演劇と文学を教える。研究分野は鶴屋南北と歌舞伎、江戸戯作、出版と視角文化、テキストとパフォーマンス理論など。
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画・担当: DH拠点 日本文化研究班 松葉涼子(DH拠点 PD)
- 参加料: 無料
- お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
第4回ビデオゲーム・カンファレンス「ファミコン*との出会い vol.3」

- パネリスト: 寺川雅嗣 /シャープ株式会社 執行役員 AVシステム開発本部長
サイトウ・アキヒロ /立命館大学 教授、株式会社ビーマットジャパン CFO - 司会: 上村雅之 /立命館大学 教授、DH拠点 事業推進担当者、任天堂株式会社 アドバイザー
- >開催日近辺のイベントを確認する
- 開催日時: 2010年7月29日(木)14:00から17:30まで
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 - 参加方法: ※本講演に参加するには、事前申し込みが必要です。
定員50名。定員に達した場合、先着順となります。
応募先メールアドレスへ「氏名」、「所属」、「メールアドレス」をご記入の上ご応募ください。 - 応募先メールアドレス: game@banabana.org
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画・担当: DH拠点 Web活用技術研究班 上村研究室 尾鼻崇(DH拠点 PD)
- お問い合わせ: Eメールにてお問い合わせ下さい。bana@fc.ritsumei.ac.jp
075-465-8496(代表番号) - 受付時間(電話): 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
- 当日のマスコミ関係者による取材はご遠慮ください。
* ファミリーコンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。
11月このページの上部へ▲
文学・文化に見る韓国併合と「朝鮮」への眼差し ―せめぎ合うイメージ、植民地帝国言説の両義性―
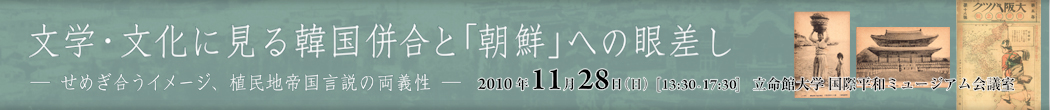
- >開催日近辺のイベントを確認する
- 開催日時: 2010年11月28日(日)13:00から17:30まで
- 会場: 立命館大学国際平和ミュージアム 二階会議室 (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
※ 会場がアート・リサーチセンターではありませんので、ご注意下さい。 -
- シンポジウム詳細
趣旨
近代日本は、植民地や占領地など、いわゆる「外地」と称された地域を組み入れることによって、多民族・多文化を包摂した帝国として展開した。「外地」に対して本国である「内地」は、帝国の政治的・文化的中心地として位置づけられた。そこでは様々なメディアを通して「外地」のイメージが消費され、それによって本国民衆は植民地帝国の意義と、その中の自分の位置(アイデンティティ)を理解した。
本年は韓国併合100年に当たるが、本企画では、韓国併合とその後の日本統治期を通じて、文学や文化の領域で形成された「朝鮮」「朝鮮人」表象と植民地帝国言説との関係を考えたい。
同化と差別という緊張した理念の混合の下で行われた韓国併合だけでなく、三・一独立運動、関東大震災など、日本の植民地体制が再編され、動揺したり危機に瀕する度に、大量のイメージが生産されてきた。それらの「朝鮮」表象からは、植民地支配の正当化や容認(維持)という面だけでなく、動揺と矛盾に満ちた支配的言説のほころびや、統治する側の不安などもまた読み取ることができる。文字や画像など、様々な形態の資料を総合的に扱うことで、このようなイメージの両義性を検討したい。- プログラム(予定):
開会の挨拶 木村一信(きむら かずあき/プール学院大学 教授、DH拠点 事業推進担当者) 研究発表 13:00 楠井清文(くすい きよふみ/立命館大学 非常勤講師、DH拠点 客員研究員)
「植民地経験の記録 ―国際平和ミュージアム所蔵絵葉書と紀行文を中心に―」13:30 質疑応答 13:45 アンドレ・ヘイグ(スタンフォード大学)
「風刺の帝国:韓国併合を視覚化した『大阪パック』併韓記念号の両義性」14:15 質疑応答 14:30 休憩 講演 14:45 中根隆行(なかね たかゆき/愛媛大学 准教授)
「韓国併合期の朝鮮表象 ―物語の拡がり/表現の軋み」15:45 休憩 15:50 水野直樹(みずの なおき/京都大学 教授)
「在朝日本人の朝鮮認識、自己認識」16:50 休憩 17:00 ディスカッション
ディスカッサント: 西 成彦(にし まさひこ/立命館大学 教授)17:30 閉会の挨拶 木村一信
-
- 関連企画: パネル展示
- 開催日時: 2010年11月21日(日)から2010年11月28日(日)までの、各日9:30から16:30(入館は16:00)まで
※月曜日休館(但し、月曜日が祝日の場合は、火曜日が休館) - 会場: 立命館大学国際平和ミュージアム 二階ロビー
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 共催: 立命館大学コリア研究センター
立命館大学国際言語文化研究所 - 協力: 立命館大学国際平和ミュージアム
- 企画: DH拠点 日本文化研究班 木村研究室
- 担当: 楠井清文(DH拠点 客員研究員)
- お問い合わせ: 075-466-3411(アート・リサーチセンター 代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
12月このページの上部へ▲
デジタル・ヒューマニティーズのいま × 人文学研究のいま
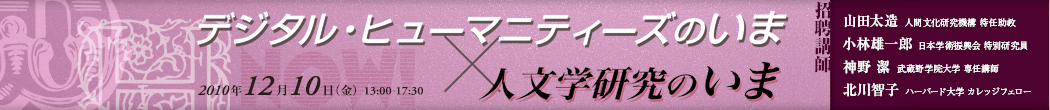
- >開催日近辺のイベントを確認する
- 開催日時: 2010年12月10日(金)13:00から17:30まで
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 -
- 講演会詳細
趣旨
デジタル・ヒューマニティーズの目的には、異分野との連携や協力を図ることが含まれている。しかし、一方ではこれと反対に、デジタル・ヒューマニティーズという分野内で領域ごとの細分化が進んでいるとともに、外との関係でも孤立化しつつあるのではないか、と感じることがある。本拠点においても、他の研究班が行っていることをなかなか理解できず、つい批判的になってしまうということがあるが、これはデジタル・ヒューマニティーズという分野内における細分化の一例ではないだろうか。また、現状では、デジタル・ヒューマニティーズにおける人文学研究は、従来のオーソドックスな人文諸学分野に対してあまり影響力を持っていない。これはデジタル・ヒューマニティーズが外との関係で孤立化している一例かと思われる。
ここ数年の間に日本でもデジタル・ヒューマニティーズという言葉が使われるようになり、学問としての内実がつくられてきた。しかし、分野内の細分化・外部との関係における孤立化は、従来の学問の枠組みを超えて、研究者間での率直な意見の交換ができていないことをまさに示しているのではないだろうか。
そこで、外部の若手研究者を招いて議論することを通じ、デジタル・ヒューマニティーズに対する拠点内外からの意見を収集し、デジタル・ヒューマニティーズの現状を改善するきっかけとしたい。- プログラム(予定): (各講演時間に質疑応答を含む)
12:30 受付開始 13:00 はじめに(企画趣旨の説明) 13:15 山田太造(やまだ たいぞう/人間文化研究機構 特任助教)
「史学研究をいかに支援するか ―歴史情報の生成・管理と利活用の支援方法」
情報学を専門としながら、東京大学史料編纂所において歴史学研究者とともに働いた経験をもつ山田氏からは、史料編纂所の人たちがおこなっている研究がどのように見えたのか、それとは反対に自分の研究が史料編纂所の人たちにはどのように受け取られていると思っていたのか、ということをうかがい、情報学研究と人文学研究との協働・そこから見えてくるDHの将来についてお話しいただきます。
13:45 休憩 13:55 小林雄一郎(こばやし ゆういちろう/日本学術振興会 特別研究員)
「言語研究における人文学と情報学の連携 ―コーパス言語学と自然言語処理を例に」
小林氏は、DHの中心的な研究分野といえるコーパス言語学・自然言語処理が専門です。そのような立場からは、同じDHを標榜する他の人文学研究について、どのように見えるのか、どこが同じでどこが違うのか、意見・感想をうかがい、今後のDH像の展望についてお話しいただきます。
14:25 休憩 14:35 神野 潔(じんの きよし/武蔵野学院大学 専任講師)
「日本中世史研究とデジタル技術」
神野氏は、法学部・法学研究科出身の日本中世法の研究者で、いわば社会科学をバックグラウンドに人文学である「日本史学」を研究されています。その経歴・視点から、本拠点や他の機関等で展開している人文科学、特に日本史学など歴史学におけるデジタル利用やその環境について、あるいは、その有効性や将来像などについて、ご意見を伺いたいと思います。
15:05 休憩 15:15 北川智子(きたがわ ともこ/ハーバード大学 カレッジフェロー)
「Narrating the Past with New Media: 「バーチャル京都」を使ったハーバード大学の日本史講義」
北川氏は、カレッジフェローとして、ハーバード大学の日本史の講義をいくつか担当されています。我々のプロジェクトで取り組んでいる「バーチャル京都」を、その講義において教材として取り上げて頂きました。文系の日本史の授業において、最新の技術で作成された3次元都市モデルをどのように利用されたのかについて、ご報告をして頂きます。これをきっかけに、ハーバード大学での人文学の授業・研究におけるデジタル技術の利用の現状や、日本と米国の人文学の違いについても、話題を広げていきたいと思います。
15:45 休憩 16:00 ディスカッション 17:30 閉会
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画・運営: DH拠点 ポストドクトラルフェロー
GCOEセミナー企画運営委員会 - 担当: 岡本隆明(DH拠点 PD)
塚本章宏(JSPS PD)
花田卓司(DH拠点 PD) - お問い合わせ: 075-466-3411(代表番号)
- 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
3月このページの上部へ▲
第5回ビデオゲーム・カンファレンス「ファミコン*との出会い vol.4」

- >開催日近辺のイベントを確認する
- パネリスト: 山崎芳郎 /元株式会社トミー取締役営業本部長
上村雅之 /立命館大学 教授、DH拠点 事業推進担当者、任天堂株式会社 アドバイザー - 司 会: サイトウ・アキヒロ /立命館大学 教授、株式会社ビーマットジャパン CFO
- 開催日時: 未定
- 会場: 立命館大学アート・リサーチセンター 二階多目的ルーム (>アクセスマップ)
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 - 参加方法: ※本講演に参加するには、事前申し込みが必要です。
定員50名。定員に達した場合、先着順となります。
応募先メールアドレスへ「氏名」、「所属」、「メールアドレス」をご記入の上ご応募ください。 - 応募先メールアドレス: game@banabana.org
- 主催: 文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)
立命館大学アート・リサーチセンター - 企画・担当: DH拠点 Web活用技術研究班 上村研究室 尾鼻崇(DH拠点 PD)
- お問い合わせ: Eメールにてお問い合わせ下さい。bana@fc.ritsumei.ac.jp
075-465-8496(代表番号) - 受付時間(電話): 9:30~17:00 (土日祝、その他の休館日を除く)
- 当日のマスコミ関係者による取材はご遠慮ください。
* ファミリーコンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。