-
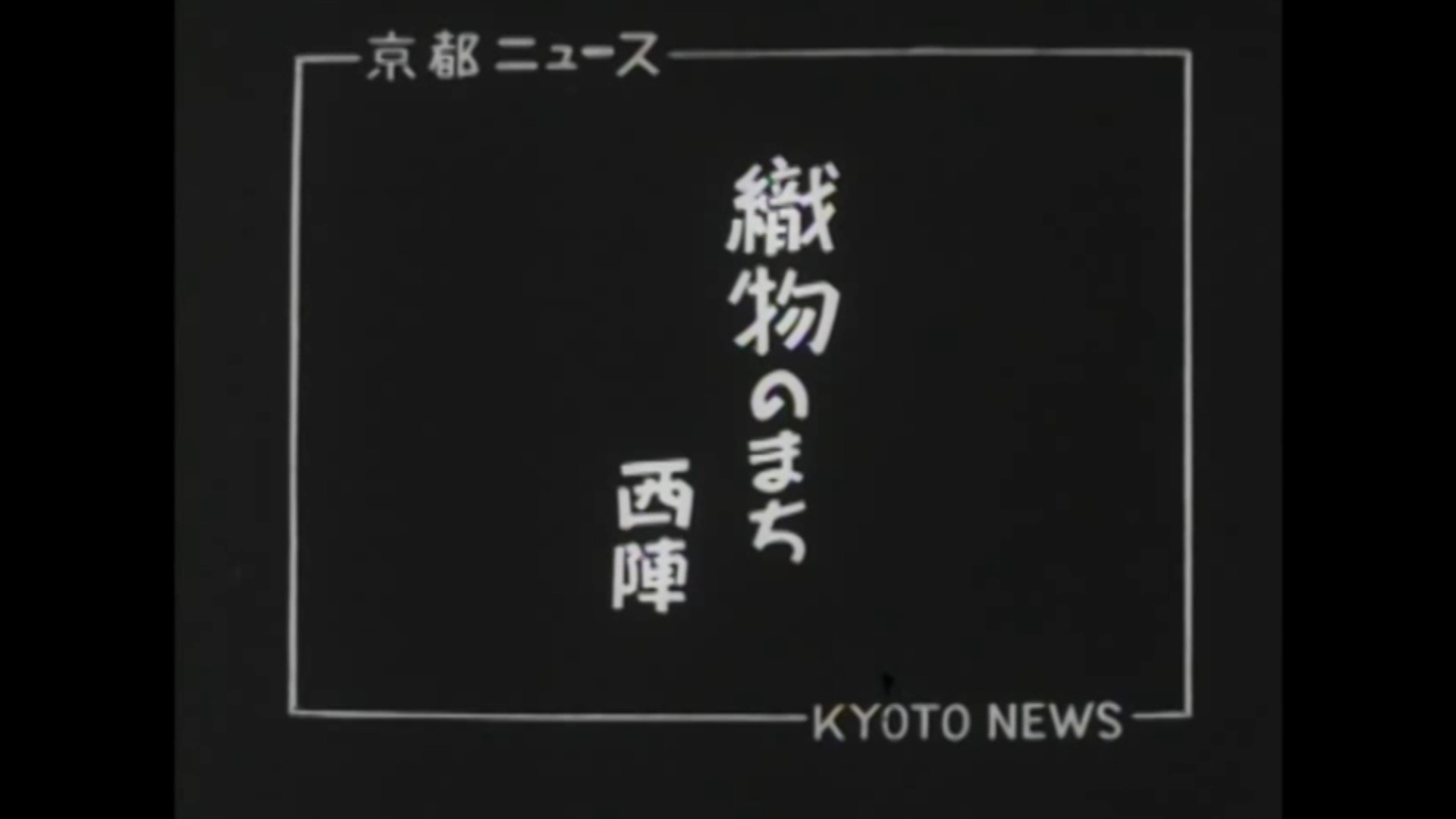
-
「京都ニュース 織物のまち 西陣」
西陣織は遠く6世紀の昔から、我が国の歴史とともに千数百年を経て現代にいたるまで、その伝統の中に生きている。織物のまち「西陣」は、京都御所の北西方、上京区から北区、右京区に渡る、昔ながらの家並みのまちである。およそ3万人の人が西陣織を業とし、年間生産額は250億円に達している。ここで生産される西陣織は、お召し、帯地をはじめ、金襴、室内装飾、ネクタイなどから洋服地?まで、多くの種類がある。軒並みに漏れる機の音は、西陣のまちの音である。西陣織は、細かい分業によって生産されている。大雑把に分けても17業種にも上り、これは、ほかの織物には見られない特色である。これらの業者のほとんどが、いわゆる中小企業である。織物の模様が図案家から届くと、細かい方眼紙に模様をかたどる。これが「指図(差図)業」。続いてこれを、「文彫り業者」が短冊形のボール紙に穴をあける。糸を晒し、染め、糊付けし、撚りをかける。これらの仕事も西陣で行われている。「染色業者」は、図案に従って糸を染める。「撚糸業者」は、糊付けを終わった糸に十分撚りをかけ、撚り上がった糸は糸繰機で糸巻にかけられる。ここで、いよいよ専門の「糸掛け工」によって織機にかけられる。西陣で使っている織機は、ジャガード式である。昔ながらの手機に代わってモーターも相当増えているが、帯はその7割までが手機である。手織りの服地も西陣で生産されている。手機から動力へ、西陣にも近代化の努力に拍車がかけられ、古い伝統の中にも新しい息吹が見られる。こうして織り上がった美しい着物、帯は、織元から市場に送り出されてゆく。そしてまた、これらを纏って脚光を浴びる美しいファッションモデルの装いから、さらに流行が生まれてゆく。こうして伝統に生きてきた西陣織は、生産の近代化を目指し、最近の着物ブームに乗って新しく伸びようとしているのである。
織物のまち 西陣(38-3)
