-
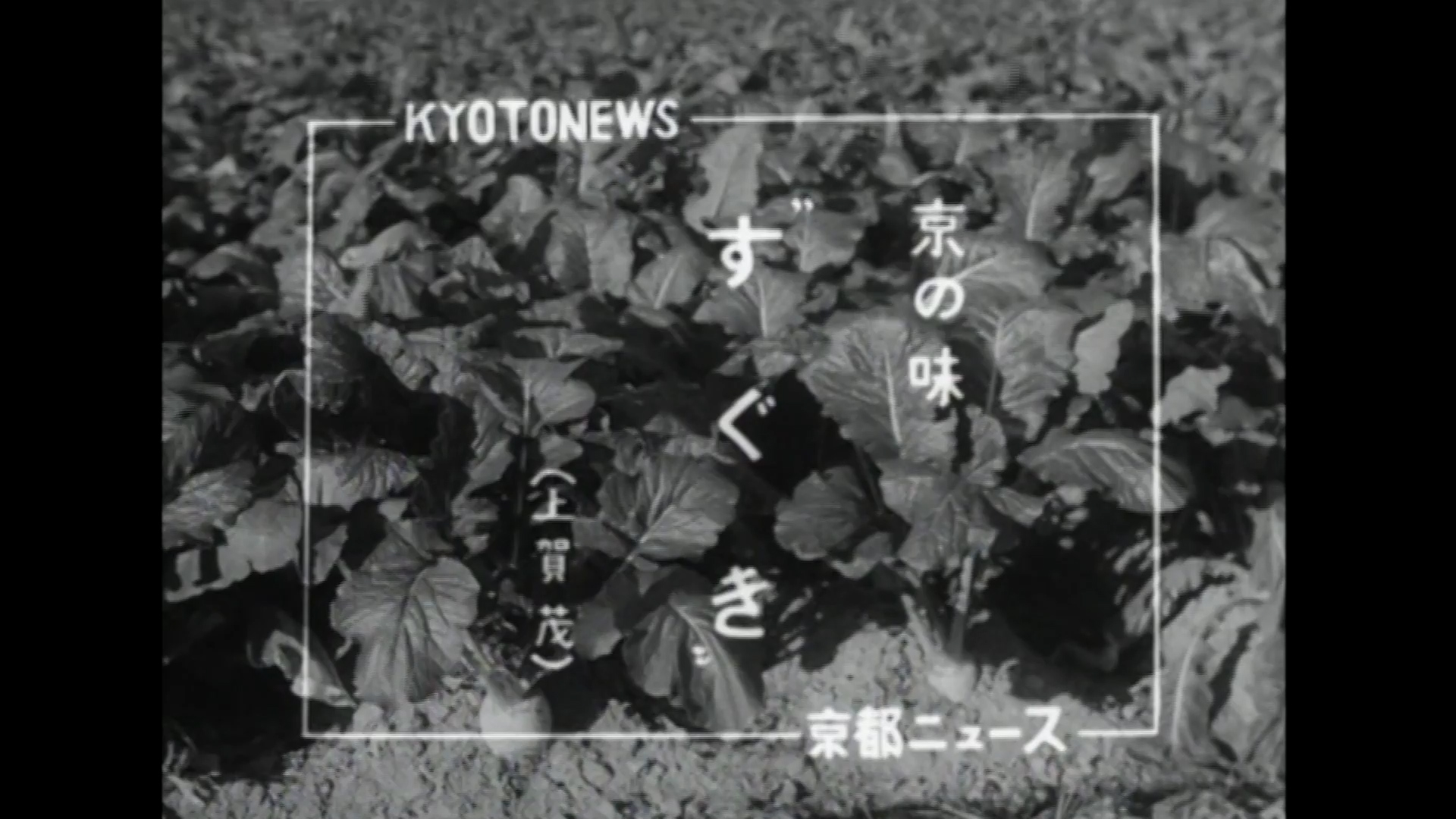
-
「京の味 "すぐき" (上賀茂)」
京の味覚の1つ、「すぐき」は、東に比叡山を臨み、鴨川に沿ったこの地域、上賀茂から作り出されます。この一帯は、気温、通風、排水、土質ともに、「すぐき」の生産には最適です。北山の奥から流れてくる水は一層味わいを増し、ほかの土地では、この独特の風味は生まれないと言われています。「すぐき」は蕪(かぶら)の一種です。稲を刈り取った後に種をまき、ほかの野菜の数倍の肥料を施し、たびたび間引きをして、その成長を助けます。収穫は丁寧に、葉を傷めないように抜き取ります。早生は10月上旬から11月、晩生は12月から2月上旬に行います。こうして収穫した「すぐき」は、いよいよ漬物にするため、農家の作業場に運び込まれます。この農家では、おじいさん、おばあさん、娘さんまで、一家総出の仕事。最初は「面取り」です。包丁で根、皮を剥ぎ取る作業です。「荒皮剥き」が終わると、今度は「仕上げ剥き」。続いて五穀樽に、根、葉のまま、「すぐき」と塩を交互に重ね、重しを加え、漬け込みます。これは、塩の浸み通るのをよくするためのもので、「荒押し」と言います。これの漬け上がるのが、12時間から20時間。これが終わると、水洗い、「本漬け」となります。一般に、この作業は朝早くから行われますが、12月の午前5時といえば、まだ薄氷も張っていようという寒さです。水洗いが終わり次第、本漬けにかかるという忍耐的な流れ作業です。水洗いした「すぐき」は渦巻きのようにして、一並びごとに塩を振りかけ、漬け込みます。これで「本漬け」は終わり。この後、直ちに天秤場へ。これは「すぐき」漬けの特有のもので、長さ4mばかりの棒の先に重しをつけた、てこの原理を応用した科学的な天秤で、4日から7日間そのままにしておきます。この後、樽は、発酵を助けるため、摂氏30度ないし40度で密閉された土室の中に、7日間閉じ込めます。こうして出来上がった「すぐき」は、大阪、神戸、東京、名古屋の市場に送り出され、1年の生産高は4500万円以上に上っています。このようにして京都市の名産「すぐき」は作り出され、私たちの食膳をにぎわせてくれるのです。
京の味「すぐき」(上賀茂)(36-5)
