-
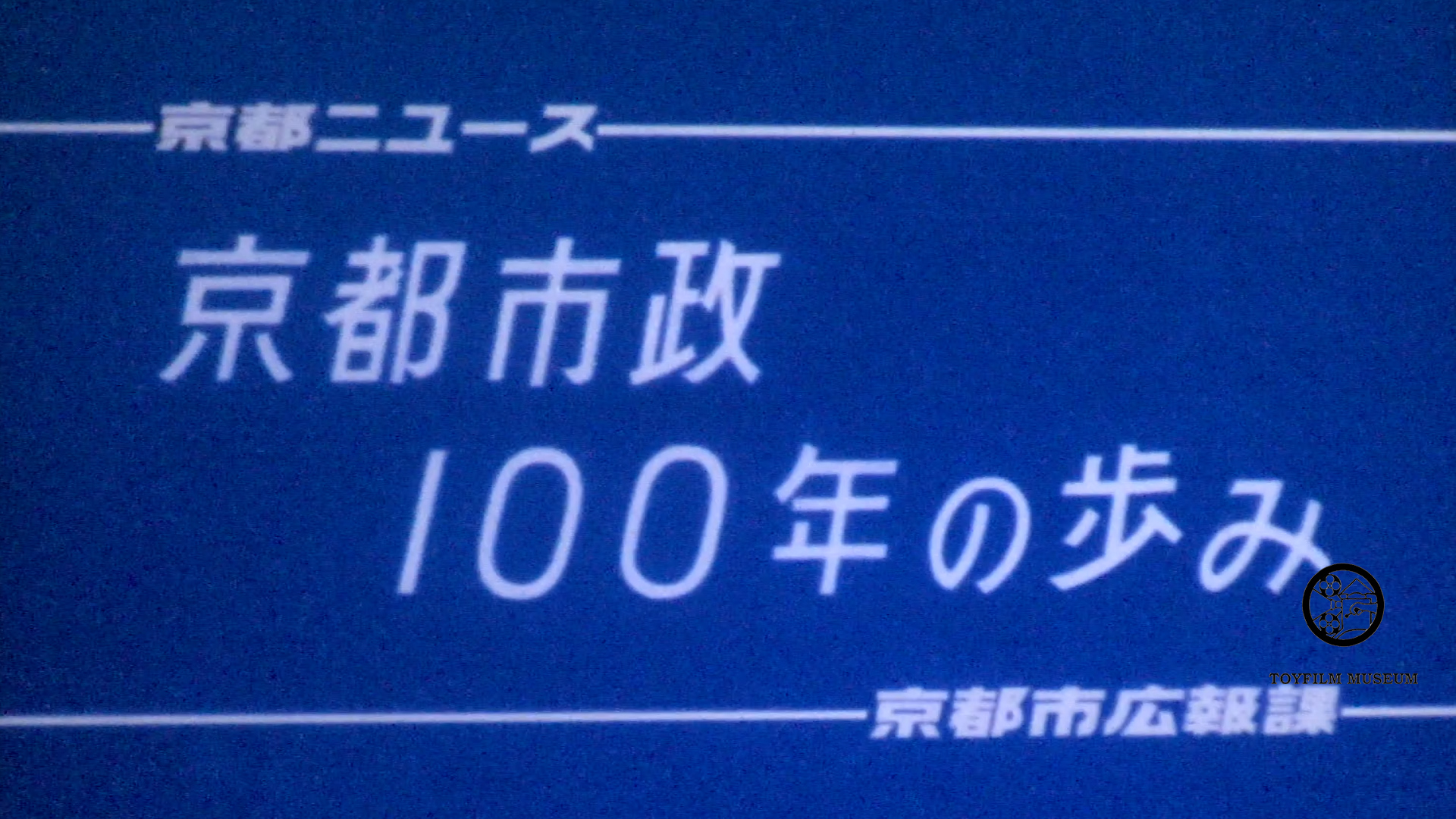
-
京都市政 100年の歩み 千年の伝統と文化が今に息づく山紫水明の街・京都。日本人の心の故郷と称えられるこの町は明治22年に京都市として生まれ変わりました。今年はこの市政施行からちょうど100年。歴史的な節目を迎えています。近代日本の幕開けとなった明治維新は、東京遷都という大きな痛手を京都に与えました。しかし京都の町衆は新しい時代を拓く人づくりをと、明治2年自らの手で全国に先駆け小学校を作りました。そして京都近代化の原動力となった琵琶湖疏水を開削。琵琶湖の水を京都に引き、船を通して交通の便を図る。不可能と言われたこの大土木工事は、時の知事・北垣国道と青年技師・田辺朔郎の熱意によって5年の歳月を費やし明治23年完成しました。更に疎水を利用して蹴上には我が国初の、また世界でも2番目の水力発電所を開設。疎水を通る船を台車に乗せて蹴上の坂を運んだインクライン。日本で初めてのちんちん電車。どちらもこの水力発電を利用したものです。明治32年、自治権を奪っていた市政特例を廃止させ、市役所を開所。初代市長に内貴甚三郎が就任しました。その後京都市は百年の大系といわれる三大事業に着手。明治45年に第2疎水が完成し、水道事業も開始されました。当時できた蹴上浄水場は、今も命の水を送り続けています。そして烏丸通や四条通を広げ、市電が創業しました。こうして京都は日本の近代化をリードし、大都市へと発展してきたのです。 現在京都市は人口147万人。市政施工当時のおよそ5倍となり、理想のまちづくりがさらに進められています。交通渋滞を解消するための地下化事業もそのひとつ。昭和62年には京阪本線地下化が完了。地上には都市計画道路や遊歩道が建設されます。また昭和56年には地下鉄烏丸線が誕生。昨年6月に京都―竹田間が開通し、1日およそ17万人が利用する新しい市民の足として定着しています。来年秋には北大路―北山間の北進工事も完成の予定。さらに今年、地下鉄東西線に着工します。未来へ向かうレールは着実に伸び続けています。琵琶湖疏水の開削に始まった京都市の100年。振り返るとその歩みには多くの困難を克服してきた先人たちの絶え間ない努力と情熱が秘められています。5年後京都は平安建都1200年を迎えます。平安神宮の造園を始め、都をどり、時代祭などが生まれた建都1100年。今、京都市では建都1200年に向けた、数々のビッグプロジェクトが市民の皆さんとともに進められています。市民の叡智とエネルギーを結集して伝統を活かし創造を続ける都市・京都をさらに発展させていこうではありませんか。
京都市政100年の歩み(216-1)
