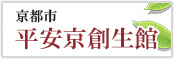このマップは、京都市平安京創生館に展示されている平安京復元模型・鳥羽離宮復元模型・法勝寺復元模型および上杉本洛中洛外図複製陶板に示されている内容を地図上に落とし、その位置関係を示したものです。さらに、秀吉の築いた御土居の位置も比較のため付け加えてみました。
同時に、古代京都の姿を概観することができるように試みてみました。弥生時代以前の重要な遺跡、古墳時代の主要古墳、飛鳥時代からの寺院跡、各地をつなぐ古道、桓武天皇が造営した長岡京と平安京、朱雀に広がっていた巨椋池、京都と強くつながっている宇治・淀・八幡・久世との位置関係、これらを含む各郡の条理などを復元してみました。時代的には主に3世紀から12世紀まで、約千年間の様子を示していますが、一部これ以外のものも含んでいます。
古代の京都は、「ヤマシロ」と呼ばれていました。『古事記』に山代、『日本書紀』に山背、平安京遷都以後は山城と記されます。山代は水田が広がる豊かな国、山背は奈良の都の背に位置する国、山城は都がある国をあらわしているようです。「京都」と呼ばれ始めたのは、平安時代の後期になってからです。京都の重層する歴史的空間を創造する一助になれば幸いです。
このマップの示す範囲は、左下の「山城国概略図」で示すように古代山城国の北半部にあたります。ベースマップは国土地理院発行の基盤地図情報などを利用し作製したもので、現在の京都の地形と重ねあわせて示してあります。