写本の「新しさ」
楮紙に書かれたくずし字が迫る、自分は古い文書であると主張する、深いにおいが鼻をつく――巡り逢えて良かった、と古文書に触るたび、触らせてもらえることのできる感謝と畏怖の気持ちが古文書に対して生まれる。判読できない文字もある。署名や宛所のない文書もある。難しい内容のものもある。しかし、文書はありのまま、自己のかつての存在を、現在に提示する──。
財団法人藤井永観文庫には、聖教(しょうぎょう)や古文書の写も多く収蔵されている。写とは、本(文書)を手書きで写したものであり、その写した本を写本(写)という。特に聖教を写す場合、書写者は、誰が所持していた文書をいつ、何のために書写したかなどの情報を奥書に書く場合が多い。聖教とは、本来は釈尊の教えを意味したが、広く師から伝授された秘説や仏典など、寺院社会で生成された仏教関係等の文書や典籍を指す。
聖教の奥書には、書写年代、伝来元、書写者、書写の動機など、書写者歴代に亙る情報が詰まっている。奥書に記載された歴代の書写奥書(以下これを書写歴という)は、本奥書(一番初めの奥書、多くは、原本撰者の奥書となる)から始まる。同じ内容の文書であっても、本奥書から年代が遠ざかるほど、現物自体の成立年代は、「新しく」なる。一般的に、文書は新しいものより古いものに価値があるとされるが、しかし、原文書の成立年代に対する書写年代の「新しさ」には、大きな意味がある。
書写歴を多く持つ文書は、それだけ長い期間、多くの人によって写されたことを意味する。そのため、内容の成立と写本の成立の間には、時代的な隔たりが生まれる。しかし、この時代的隔たりが意味するのは、その間、書写の必要がある文書として、重要視されていたことを意味する。それはいわば、各時代ごと(書写年代ごと)にリバイバルされた文書――すなわち写本の存在自体、その文書が「旬」の時代であったことを意味する。
祖本の「古さ」
祖本とは、数々の伝本の原本にあたる本であり、写本の元となった著者自筆本を指す。聖教の奥書には、祖本や祖師に対する書写者の想いや動機が記されている場合がある。
本展覧会で展示したNo.7『九曜秘暦』の奥書は、「本云、平治元年九月六日書了、興然/応永三年七月日以二理明房自筆本一、/令二模写一了、件写本依二祖師真迹一、令/レ寄二進慈尊院経蔵一了、/法印権僧正賢宝六十四」というものである。
この奥書には、本文内容に関わった二人の僧が登場している。すなわち、平治元年(1157)に祖本を「書写」した興然、応永三年(1396)に理明房興然の自筆本を「模写」し、写した元の本を勧修寺慈尊院の経蔵に寄進した賢宝である。解説文でも説明したが、興然は勧修寺慈尊院流の祖であり、賢宝は東寺観智院第二世院主である。賢宝は、写した元の本が「祖師真迹」であるため、勧修寺慈尊院の経蔵に移したと記している。
賢宝がいた東寺観智院の法脈は、勧修寺慈尊院流に連なる。そのため、平治元年から応永三年に賢宝が書写する時まで、興然自筆本が東寺観智院に伝来していた。この間、二三七年。その後、賢宝が祖本とした興然自筆本は勧修寺の経蔵に、賢宝が模写した本書は東寺観智院に、それぞれ所蔵された。以上は、奥書の情報から判明する。
賢宝が「祖師真迹」に見出した祖本に対する認識は、祖師興然に対する敬意、「真迹」としての超越的な価値である。賢宝の場合、自らが「模写」した本に比しての興然「真迹」である祖本の「古さ」とは、二次的に生じる勝ちである。賢宝の場合、本を単なる書写の対象として見ていたのではない。祖師興然や自らが所属する慈尊院流に対する想いの重みが、書写者である賢宝を動かしていた。そして東寺観智院と勧修寺慈尊院、それぞれが姉妹となる興然本『九曜秘暦』を共有し、真言密教法流としての絆が深まっていく。
時代を経たものを意味する文化財としての「古さ」と、写す前に成立していた祖本の「古さ」は、同じ「古さ」であっても全く意味が違う。それは決して同じにはならない。
写本の生成
一つの写本が成立するまでには、いかなる過程があるのか。図像集の場合、完成まで複数の人物が作品に携わっていることがある。
次に示すのは、展示No.4『曼荼羅集』の奥書である。「図画本云、/今此抄三巻、先師理明房阿闍梨興然往年雖/集レ之、諸尊色像未レ図レ之、且守二彼遺命一且/為レ散二象(衆)霧一、仰二両三之画云(工 )一、図二諸尊之/形像一而巳、有二所違一者後覧添二削之一、/権大僧都光宝/天福元年十月之比、年来所持本/書二制図像一畢、定真本也、/此抄三帖依二師命一書レ之、油紙図像同写レ之、/大法師隆聖廿三歳九臈 /此集三帖頗希也、尤可レ為二秘蔵一焉、/弟子僧覚恵即応レ励二志修補経/営一訖、後葉勿二容易一、且不レ可レ許二他見一矣、/延享第五戌辰歳五月十八日/ )一、図二諸尊之/形像一而巳、有二所違一者後覧添二削之一、/権大僧都光宝/天福元年十月之比、年来所持本/書二制図像一畢、定真本也、/此抄三帖依二師命一書レ之、油紙図像同写レ之、/大法師隆聖廿三歳九臈 /此集三帖頗希也、尤可レ為二秘蔵一焉、/弟子僧覚恵即応レ励二志修補経/営一訖、後葉勿二容易一、且不レ可レ許二他見一矣、/延享第五戌辰歳五月十八日/ 定額僧貫首勧修寺浄土院僧正賢賀世寿六十五法臈五十六」。 定額僧貫首勧修寺浄土院僧正賢賀世寿六十五法臈五十六」。
この奥書には、総勢六人が登場している。すなわち、撰者の興然、光宝、定真、隆聖、覚恵(1604〜?)、賢賀(1684〜1769)である。まず、本書の元となる曼荼羅を収集した興然、興然が収集した曼荼羅をまとめ諸尊形像を図した光宝、図像を写した定真、油紙に図像を写した隆聖、そして本書を秘蔵し修補経営した仁和寺真光院の僧覚恵、東寺観智院第十三世の僧賢賀である。
このように一つの図像集が成立するまで、幾人もの手が加えられていることがわかる。本書が制作される原動力には、「遺命」や「師命」という師祖に対する忠誠と義務、本書に対する「頗希」という価値観、「秘蔵」「勿容易」「不可他見」という本書に対するアプローチの仕方が存在している。かかる認識は、段階的に形成されるものであり、成立当初に一気に成立したものではない。本書三帖は、時代を経て生まれた本書の価値、それに付随して生まれた尊重行為によって生成されたものである。これらは、本書が質的に完成するまでの必要条件であったといってもよい。
興然が曼荼羅の収集に着手した時期はもっと前に遡る。しかし、初めの奥書の時期である天福元年(1233)から奥書最後の時期である延享五年(1748)まで、本書は総計五一五年以上もの時を経た奥書(歴史)を保有していた。奥書は、単に成立年代を見極める証拠だけではなく、いくつもの生成の段階を経た本書の有り様を示唆する一つの歴史叙述としても捉えられる。
写本の生成は、祖本が重要視された結果である。且つ、内容が長い歴史を生き抜く価値を保有し続けた、結果の姿そのものを証明している。文化財としての古文書の「古さ」と、「新しい」写本の価値は、一見相反する。しかし、文化財としての「古さ」も又、長い歴史を生き抜いた証そのものであり、かかる意味で同じ歴史的な生命力を保っていたといえる。
写が多く存在し、写が「新しい」時代のものであっても、その写本はそれだけ長い期間「旬」の時代にあった。写本は祖本の価値を未来に伝え、文化財としての「古さ」をも現在に証明する役割を担った、生証人のような存在であった。
現在の活字
パソコンが普及し、コピー(複写)&ペースト(貼り付け)が安易にできる現在。そこには、紙の手触りも、読めない文字も、時代を感じさせるにおいもない。手書きからワープロ、そしてパソコンへ。文書といえば、存在が既に活字であり媒体である。
文書の書写から修補、宝物から文化財へ、そして現在はこれらを保全する方向に向かっている。有形無形文化財をはじめとする原資料のデジタルアーカイブ化である。文書を傷めず、コンパクトに閲覧できる一方で、文書の手触りや息吹は、データの向こうへ遠のく。
――古文書に巡り逢えて良かった、というのは、原文書に触れ合える終わりの時期にわたしが生きているせいかも知れない。古文書は、存在自体が既に自己主張している。だからこそ、パソコンの画面に吸収されてしまった存在価値を、たとえば文書自身はどう思うのだろう。もう、何百年も書写歴が付け足されない………など。勿論、文書は何も喋らない。
しかし現代の古文書は、普段の仕事をデジタル画像に任せ、時々は展覧会で原文書の姿を披露するのだろう。写本の「旬」は、媒体を変えながらまだまだ続く。
 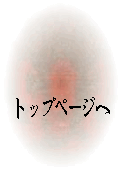 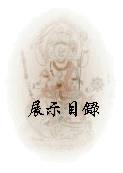
|