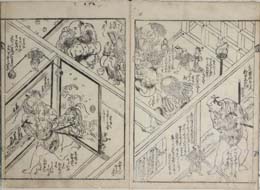| 子供絵本 |
78
|
黄表紙の表紙いろいろ
|
表紙の色から黄表紙と呼ばれるこの作品群は、子供だけの為のものではなく、同時に大人の読み物でもあった。草双紙の表紙は、その年ごとに各版元が工夫をこらした題簽で飾られ、黄表紙期(18世紀半ば~19世紀初頭)には多色摺の題簽が定着する。 |
たつのみやこせんたくばなし
78a 竜宮洗濯噺
|

16.8×12.6
|
絵師:勝川春朗画
版元:西村屋与八
年代:寛政3年(1791)
|
み みこし たんば しろあと
78b 見こし/\/丹波の城跡
|
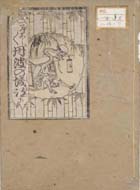
17.5×12.7
|
作者・絵師等:飛田琴太作 古阿三蝶画
版元:伊勢屋治助
年代:寛政6年(1794)
|
きょうがのこえどむらさき そのあとまくばばあどうじょうじ
78c 京鹿子江戸紫 / 其跡幕婆道成寺
|
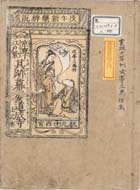
17.1×12.6
|
作者・絵師等:式亭三馬作 歌川豊国画
版元:西宮新六
年代:寛政10年(1798)
|