ごあいさつ
赤穂浅野家の浪士たちが主君の仇を報じたあと、幕府の命により全員切腹して決着を見たのが元禄十六年(1703)。ちょうどそれから三百年を迎えて、一昨年以来、「忠臣蔵」に関連した様々な催物が各地で展開されてきました。その掉尾を飾って立命館大学アート・リサーチセンターでは、浮世絵展ならびに国際シンポジウム「忠臣蔵と見立て」を企画いたしました。
「忠臣蔵」の名称は、もとは寛延元年(1748)に大坂で初演された「仮名手本忠臣蔵」という人形浄瑠璃の作品に由来しています。以降、この作品は形をかえて、歌舞伎や浮世絵、文芸など、ジャンルを越えて庶民文化の中へと浸透・展開していきました。歴史の中でおこった一事件、あるいは一戯曲でしかなかった「忠臣蔵」は、日本文化の中で「忠臣蔵文化」とも呼ぶべき豊饒な世界を築きあげてきたのです。また、「仮名手本忠臣蔵」の五段目・六段目・七段目・九段目という主要な段は、京都を舞台にしています。「忠臣蔵」も、京都なくしては成り立たないテーマと言えるでしょう。
当館が所蔵する浮世絵や版本の中にも、多くの「忠臣蔵」を題材にした作品があります。その中から特に「見立絵」と呼ばれる作品を中心に据えて、今回の展覧会を構成いたしました。「見立て」は、日本人の文化・芸術表現を説明する上で重要なキーワードの一つでもあります。今回は「忠臣蔵」を縦糸、「見立て」を横糸にして、さまざまに織り成される発想と表現の世界をお楽しみ下さい。
立命館大学21世紀COEプログラム
京都アート・エンタテインメント創成研究
「絵画と書物・書物と地域」
研究プロジェクト代表
立命館大学教授 赤間亮
忠臣蔵
と
見立て
デジタル展示
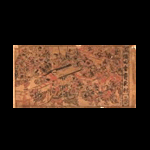 |
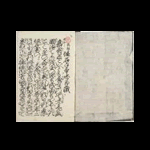 |
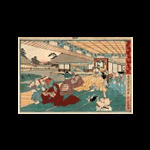 |
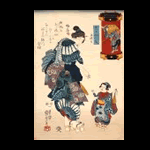 |
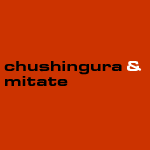
|
 |
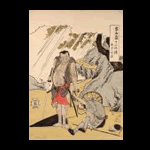 |
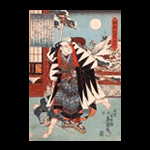 |
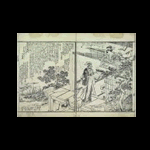 |